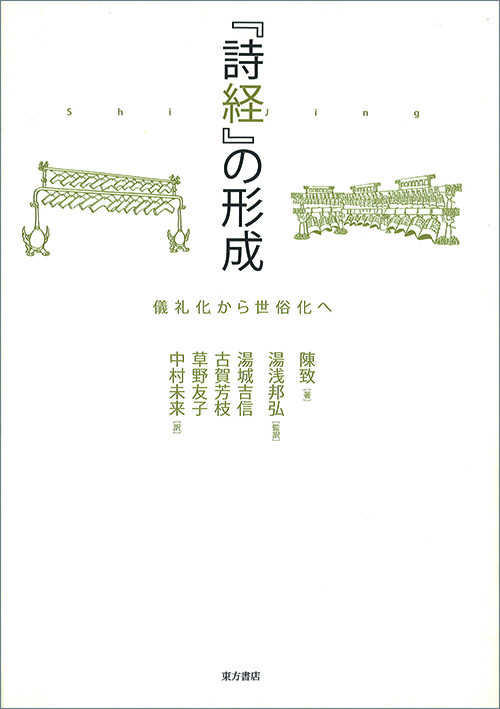
|
『詩経』研究への新視点
本年六月に東方書店より出版された陳致『詩経の形成――儀礼化から世俗化へ』は、二〇〇七年に英文で出版された著者の博論を元とし、二〇〇九年に中国語版として刊行された『従儀礼化到世俗化――『詩経』的形成』を、更に日本語に翻訳したものである。この経緯は興味深い。なぜなら、一つは漢字文化圏とは異質な文化背景をもつ言語での著作がベースであること、またそれが「中国語に翻訳」されたという現象、そして重訳の形をとりながら、日本という漢学の伝統を持つ学術界に専著として出版されたということ、これらが単純な学術書とは異なる古典学の困難を、端なくも示しているように思えるからである。この不思議な経緯から示唆された幾つかの問題については後述することにして、まずは本書の内容を紹介しよう。
本書は六章から構成される。まず第一章「研究の現状と研究方法」では、従前の詩経研究を概括した上で、本書の研究方法が示される。それは著者の所謂「音楽考古学」、つまり音楽の方面への視点を中核とすることを独自性とする。その具体的な対象として、楽器および楽章を中心に、考古・文献双方による考察が第二章以下に続く。第二章「庸・頌・訟(誦)――殷代祭祀の楽器・楽調と礼辞」では、「頌」は「庸」であること、殷周交代期の文化交流の中で、周王朝の統治者が「庸」楽を「頌」と称し、周が殷の音楽を改造しつつも受け継いだことを、卜辞と文献資料とを使用しながら説明する。第三章「雅楽の標準化」では、「雅」の語が周人の観念の中で「夏」と結びつく新しい伝統の創出であり、殷周交代期に周王朝が殷の楽曲を吸収しつつ新たに組み替えて「雅」を制作したという仮説を、「標準化」という表現を使って説明する。第四章「古文字の中の『南』および『詩経』の中の『二南』」では、「南」とは古楽器であり、周代前半期に江漢地区で流行した詩歌選集に由来する雅楽であるとする。第五章「『雅』の地方化」では、周が殷を征服した後、周による儀礼音楽の再編成の中で、王朝文化の地方化とともに「風」が「雅」の領域に取り込まれていったことを論じる。第六章「結論」は全体のまとめ。
漢代に『詩経』は経典となり、詩篇のみならず「風雅頌」がそれぞれ儒教理念の元におかれ、「風」とは諷諫、「雅」とは雅正、「頌」とは頌歌という方向で「詩の六義」が価値付けされていく。所謂経学である。一方で『詩経』の歌謡性を重視する詩経理解は、経学と並行して存在し続けた。また近代になると、経学否定の風潮下で、『詩経』は歌謡であり文学である、という視点から新しい詩経学が生まれる。その際に、風雅頌についても、「風」は凡祭(神降ろし)、「雅」は仮面舞踏である、というような民俗学的視点からの分析はあった。それに対して本書では、この詩経理解の根本に関わる「風雅頌」理解に、新たな仮説を立ち上げる。それが「頌」は「庸」、「雅」は「夏」、「南」は江漢の雅楽、という新説である。出土資料と卜辞解釈に基づく楽器や文字の分析は本書の眼目であり、更に古代史や地理学的視点を取り込むことで、説得力のある行論になっている。ただしかし、そこに直接的に結びつけられる文献資料の意味と解釈に関しては、疑問を感じさせる部分が時折顔を見せる。
本書の詩経研究史における評価を一言で言えば、「野心的な問題作」ということになろう。極めて新しい視点と、どうしても納得できない論述が同居し、大きく肯首共感できる部分と、飛躍の大きさに不信感を禁じ得ない部分とが交互に繋がっている。
例えば、殷周交代期において、周が新しい権威確立のために、殷の音楽を受け継ぎつつも、それを大きく改編したという主張は、王朝の創立期における「楽」の再編と伝統の創作という意味で重要である。また楽曲の集約と伝播を、中原・関中・江漢、そして周原という地域区分に基づいて論じた点は、『詩経』の詩篇の背景にある文化の相違を説明するのに有効である。これらは斬新な発見と言えよう。一方で文献資料の応用に当たっては、その文献の成立時期と背景を勘案すること無しに、論述に直接繋げるのは危険である。事実と理念、仮説と偏向とを含むのが古典文献である。また経典の主張は必ずしも「事実」でないという認識は文献学の基本である。その意味で、出土資料や文物に基づく分析が、時として直接文献資料に結びつけられ、そこから結論が導かれる行論には疑問を持つ。
つまり、このまま全てをまるごと肯定することは出来ないが、しかし非常に大きな発見と思われる仮説があることも確かである。野心に満ちた問題作なのだ。そしてこの問題はそのまま『詩経』とは何か、という大問題に繋がっていく。古典文献の記述は無批判に信じられるわけではないが、古典文献を取り込まずには論じられない対象として『詩経』は存在するからだ。
『詩経』とは何か、を説明するのは極めて難しい。中国最古の詩歌集という以上の説明は全て、立場と分析視角によって変化するものだからである。また『詩経』という呼称そのものも多くの説明を要する。我々が今『詩経』と呼ぶものは、古くは『詩』であり、漢代には「毛詩」であり、『詩経』という呼称は厳密に言えば朱熹以降のものである。英訳する場合にも、例えば本書の場合は The book of songs であるが、book に「経」の意味は無いし、「詩」は song なのか poem なのか、はたまた ode とすべきなのかといった具合に、呼称そのものに『詩経』理解の視点が反映される。
本書の著者は、『詩経』の詩を song と訳す。そこには著者の『詩経』に対する独自の視点、すなわち『詩経』を音楽として捉える視点が反映されている。『詩経』の詩は楽曲を伴って歌われるものであり、楽曲の背後には楽器の演奏があり、楽器の種類や楽曲の曲調には、それを生み出した時代的、地域的文化の背景がある。そのような考え方が、本書の独自な詩経理解において最も評価されるべき点なのだ。
『詩経』は詩であり歌であり、また楽器に併せて演奏される楽である。儒教経典になった後も、「礼楽」を支えると同時に、歌と詩の要素も平行して残る。音曲の失われた後は、文字として残された歌詞が大きな意味づけを持ち始め、音楽的要素への視点はそれに伴って後退する。その中で、唐初に集約された『毛詩正義』は、『荀子』楽論や『礼記』楽記を承けつつ、『詩経』の持つ詩と音と楽の要素の、それぞれの働きを総合的に説明しようとした大きな試みであった。評者は本書の論述の中に、この『毛詩正義』と類似する視点を感じた。
『詩経』を「楽」との関連で捉えようとする試みは、しかし実は古くから有った。『論語』や『礼記』を詳細に読めば、そこに言及される『詩経』は、詩としてではなく音楽としてあるのは明白である。そこに注目した詩経学、すなわち『詩経』を楽の視点から説明しようとする態度は、五経を総合的に捉えようとした経学者たちにも見られる。その中で注目したいのは、中国近代の朱自清『詩言志辨』である。これは『詩』が持つ音楽性を大きなスパンの中で論証した注目すべき詩経研究であるが、上述の『毛詩正義』と並んで、評者は本書の行論に朱自清との共通点を見る。引用文献も、行論の方向も類似しているのだ。これらは全て『詩経』の持つ歌詞の意味ではなく、音と楽の要素に注目した詩経理解として括られよう。
近代の詩経学が文学的視点に偏りがちな中で、そこからこぼれ落ちる『詩経』の多様性、特に音楽の要素を重視するという古くて新しい視点に、本書の意義はあるのだと考える。
さて、本書は英語―中国語―日本語と翻訳を重ねている。そこには、古典文献を英語で解説する際、あるいは漢語を日本語に直す際の「意味」の問題が生じる。「詩」に関しては上述したが、「楽」もまた同様に訳が困難である。「楽」は music とイコールではない。「楽」には「詩」と「音」とともに、演奏行為や儀礼という特殊空間を背後に持つ濃厚な儒教的意味がある。「礼楽」は儒教において目に見える形であり、精神であり理念であったわけで、それを掬い取る外国語(英語・日本語)は無い。翻訳作業はその過程で、古典文献中の一語の持つ「意」への理解を幅広く求める困難な仕事なのだ。その意味で、この問題を引き受けるものとして、本書の「附録」は原書とならぶ価値を持つ。日本語訳の際に加えられた「附録」は、本書の理解の助けとして加えられたものであるが、同時に『詩経』とは何かを理解する最も基本的な情報を、的確に分かり易く解説している。本書を学術的書としてのみならず、詩経学の良き入門書として、利用価値を高めるものとなっている。
(まきずみ・えつこ 二松学舎大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。

本書に関するコラムはこちら |
