馬季氏は、1934年北京生まれ。本籍は河北省・黄荘村。本名は馬樹槐。
小学生のころ寄席でのぞいた漫才に魅了され、新華書店に勤めたのちに出場した「全国従業員アマチュア演芸コンクール」でみごと優勝。漫才大家の侯宝林氏に見こまれる。56年、中央広播説唱団(放送演芸団)に入団し、プロの漫才師としてデビューする。
同年、中国共産党に入党。61年には、文豪・老舎が「侯派の継承者だ」として馬季氏を高く評価する文章が『人民日報』に掲載される。
66~76年の"文革"時代には、「古い芸術」である漫才も批判の対象となり、東北地方の「五七幹校」(幹部訓練学校)で労働・思想教育を受けるなどの辛酸をなめる。
その後は、創作漫才を次々と発表。漫才師、演芸作家として活躍するかたわら、全国政治協商会議委員(78年から4期)、中央広播文工団説唱団団長などの要職を歴任。日本訪問をはじめ、香港、台湾、アメリカ、東南アジアで海外公演を成功させるなど、中国漫才の発展と普及に大きく寄与した。 |
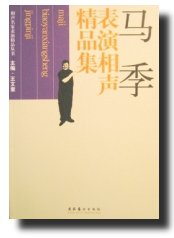 |
とりわけ、師匠の侯宝林氏をはじめ、劉宝瑞、郭啓儒、郭全宝ら先代のすぐれた漫才芸術をうけつぐ世代の代表として、「近現代の継承者」「橋渡し役」とも称された。
50年におよぶ"漫才人生"で、創作された作品はおよそ300。代表作に「登山英雄賛」「打電話(電話をかける)」「女隊長」「五官争功」など。民衆の生活を、明るく親しみやすい笑いで描き、人気をよんだ。
正規の弟子に、姜昆、趙炎、劉偉、馮鞏、笑林といった"全国区"の漫才師が17人おり、その勢力は中国の有名なマラソンチームになぞらえて「漫才界の馬(マー)軍団」と称された。
2006年12月20日、心臓病のため、北京市内の病院で死去。72歳だった。
推敲のあとが絶筆になったという『一生守候』からは、自伝を通して、中国漫才の移り変わりと神髄がうかがえるようで興味深い。
|
 |
 |
漫才も批判の対象となった"文革"時代――。
「侯師匠を批判する大字報(壁新聞)を、私も書いたし、師匠も私を批判した。しかし党員としては、上部の命令に従わざるをえなかった」
同志や友人、家族であってもかたき同士になる、異質な時代だったという。
「弟子の馬季が、師匠を平手打ちした」というウワサが広まったこともある。師匠の沈黙を尊重し、弁解を避けてきたからだが、本書で初めて真相が明かされる。「かつて師匠をたたいたことなど、一度もなかった。私はずっとこれまで侯先生を、師と仰いできたのだ」
折しも中国は50年代末から、伝統漫才の保存活動をすすめていた。それだけに"文革"による文化の破壊をくやしがるが、根っから明るく、前向きな馬季氏は語る。
「私にとって"文革"は迫害ではなく、財産だった! 私は幸いにもその階段を上りつめた! もし吊るし上げに遭わなければ、どうやって人間のさまざまな側面を知るのだ! 人間性を深く理解するというのだ?」
吊るし上げに遭い、毎朝のトイレ掃除の罰を受けながらも、いつかは再び舞台に上がることを確信していたという。 |
|
その後の80~90年代は、「創作のピークだった」(馬季氏)。水を得た魚のように「宇宙タバコ」「多層ホテル」など、時代をうつした新作漫才を発表していく。
乙のいなかへ、公演に行った甲。
――で、どこのホテルに泊まったんだい?
――多層ホテル
――多層ホテル? ……何階建てなの?
――200以上だろう
――200階? そんなに高い建物はないよ
――ちがうちがう 泊まるための手続きが200以上あるんだよ
(「多層ホテル」より)
|
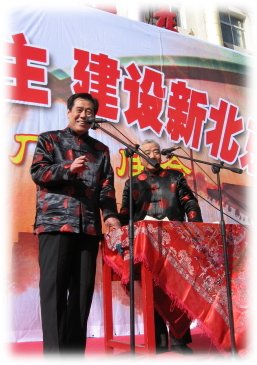
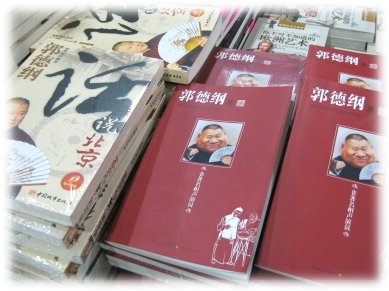 |
外国への訪問も、創作に大きな影響を与えたようだ。79年秋には「中国青年代表団」で初めて出国。行く先は、日本だった。
東京、大阪、奈良、京都、広島などの都市をめぐり、落語や漫才といった日本の演芸にも理解を深めた。あるとき、演芸を見ていると、日本の芸人が岸信介、田中角栄、大平正芳といった歴代首相のまねをした。歩き方から、話し方までそっくりなのだが「まったくもって驚いた。そして理解に苦しんだ」(馬季氏)。中国では、国家幹部を笑いの対象としたものまねがタブー視されているからだろう。
旺盛な好奇心と、鋭い観察眼をもって日本をまわり、「日本の漫才は、中国の"対口相声"(かけあい漫才)とほぼ同じ」「日本の芸人は中国の芸術から多くのものを吸収しているが、それに比べて我々は、日本からの学びが足りないのではないか?」と感慨を深める馬季氏。
訪日の成果は、日本人の"おじぎ文化"をユーモラスな角度でとらえた作品「彬彬有礼」(品がよい)に結実している。
晩年は、後進の指導に力を入れた。大衆の中から「生きたことば」を吸収し、作品に時代感を取り入れることも忘れなかった。そして、漫才の体系的な教科書づくりを説き、「文化的品格の向上」を訴えてやまなかった。
漫才と苦楽をともにし、70歳をすぎてなお「いかなる状況下であっても動揺しない、ホンモノの漫才師になりたい!」(本書)とのべた馬大師。あふれるばかりの情熱が、中国の大衆演芸を支えてきたことに改めて気づかされるのである。
書店のコーナーには作品集『馬季 表演相声精品集』(王文章・主編、文化芸術出版社)が山と積まれ、ファンの関心を集めている。地元紙によると、創作のプロセスや背景をときあかす新書の出版も計画されているという。
漫才の大御所といわれた馬三立氏も03年に他界されたが、いっぽうでは郭徳綱氏のような若手も台頭している。北京ではさいきん、新設の寄席「張一元天橋茶館」がオープンしたり、寄席はいずれも盛況だったりと、新たな漫才ブームが起きているようだ。
その死去は悔やまれるが、つねに時代と庶民をうつしとってきた馬季大師。自伝や作品集などを通して、中国漫才の"いま"を知るのも、意義深いことだろう。
|





