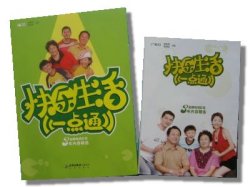 1.『快楽生活一点通』 1.『快楽生活一点通』
孫暁峰 張暁静主編 北京出版社 2006年11月初版
北京テレビ系で、2004年から全国放送された人気番組「快楽生活一点通」を書籍化したもの。祖父母と両親、楽楽くんの5人家族が登場し、暮らしに役立つ、とっておきの“知恵袋”を紹介している。
ホウレン草をつかって、白い衣類の洗いあがりをさらに白くする方法、自家製の美肌パックのつくりかた、クルマの中のいやな匂いを、フルーツで吸収する方法など、ふだんは見のがしがちな「へえ~」といった知恵が満載だ。
番組のダイジェスト版VCDもふろくに。お買い得感たっぷりの1冊となっている。
2.『人体使用手冊』(人体使用手帳)
呉清忠著 花城出版社
3.『美麗教主之変臉天書』(美の教祖の美顔神書)
伊能静著 接力出版社 2006年10月初版
映画にドラマ、歌もこなして大活躍の台湾アイドル・伊能静(Annie)。中学・高校時代を日本ですごし、台湾でデビューした彼女が、「美しい肌」を保つための最新コスメ事情を紹介する。
4.『品三国』(上)
易中天著 上海文芸出版社 2006年7月初版
5.『無毒一身軽』(毒素をなくし身を軽く)
林光常著 国際文化出版公司 2006年6月第3刷
著者は、台湾がん基金会顧問などの要職をつとめる健康教育の専門家。「毎日、水を3リットル以上飲む」「適当な運動で、睡眠の効率を上げる」など、からだや生活環境への配慮、気持ちの持ちようから「毒素(toxin)」を排除しようと訴える。
6.『人生若只如初見』(人生かくも初見の如し)
安意如著 天津教育出版社 2006年8月初版
サブタイトルに「古典詩詞の美しさと哀愁」とある。「詩経」「長恨歌」「白頭吟」「子夜歌」などの中国の古典名詩を、現代風によみといたエッセイ。
7.『新結婚時代』
王海鴒著 作家出版社 2006年9月初版
『牽手』(つれあい)、『中国式離婚』など、社会派の問題作を放ちつづける王海鴒の最新長編力作。めざましい変貌をとげる現代社会を舞台に、中国人の「食い違い結婚」をテーマとして、2世代3組の婚姻の本質にせまる。「結婚の倫理をつきつけ、自省をうながす」ヒューマンドラマであるという。
8.『長尾理論』(The Long Tail)
クリス・アンダーソン著(米) 喬江涛訳 中信出版社 2006年12月初版
インターネットの小売店では、たとえヒット商品でなくてもターゲットを絞ったニッチ(すきま)商品であれば、細く長く売れつづける。そんなネット小売市場の特性「ロングテール」を利用すると、ビジネスの方法は劇的に変わるという。著者は、米IT雑誌『ワイアード』の編集長。既存の経済界を震撼させた話題の書である。
日本では、早川書房から『ロングテール「売れない商品」を宝の山に変える新戦略』として今年9月に出版された。
9.『誅仙(7)』
蕭鼎著 花山文芸出版社 2006年11月初版
ネットの読者を中心に、爆発的な人気をほこるファンタジー武侠小説。『誅仙』の読書サイトへのアクセス数は、2003年の公開時からのべ3億回を数えるという。作者の蕭鼎は「ポスト金庸」との呼び声も高く、台湾・香港にも熱烈なファンが多い。
平凡な少年・張小凡が、厳しい鍛錬をかさねて武芸を身につけ、悪の権化の妖怪たちに戦いをいどむ。本書で7巻目となるが、物語はまだまだつづく一大スペクタクル長編小説だ。
10.『明朝那些事儿』(明朝それらのこと)
当年明月著 中国友誼出版公司 2006年9月初版
「だれが、易中天(テレビ歴史講座の人気講師)をPKに追いこめるか? それは『明朝那些事儿』しかない」と帯にある。
大手ポータルサイト・新浪ネットのブログが火を噴き、ついに書籍化。明代の皇帝から、王侯貴族、ふつうの人々までに命をふきこみ、小説仕立てにして歴史をひもといた。そこに、新しさと面白さがあったようだ。
本書は、明の太祖「朱元璋の巻」。「今年、大ブレイクする予感がする」(文学博士)、「中高生の必読の書にしたい」(教育者)など、多くの感動の声がよせられている。
|





