歴史上、伝承上の人名をつけたあだな・その4
佐藤 文俊
事例研究
C-1 『水滸伝』関連のあだな 宋江
■イメージ
宋江は山東の鄆城県の胥吏で、外見は色黒で小柄で頼りなさそうだが、一方で仁義を重んじ謙虚で、有能な人士を積極的に取り入れる人物というイメージをもつ。宋江本人は妾の閻波惜殺しの結果、処刑寸前に梁山泊の好漢に助けられ、梁山泊入りする。仲間の幹部は、宋の皇帝側近の四人の奸臣(高俅、童貫、楊戩、蔡京)や貪官汚吏の不正との戦いで、梁山泊入りした者が多い。
梁山泊集団の目標は「天に替わって道を行う」で、宋のために戦うことであるが、その前提に皇帝周辺の悪人を排除する意も含まれていた。首領の宋江はひたすら招安を求める路線を突き進み、その結果宋朝の命に従い遼等を滅ぼし、方臘の大反乱の鎮圧では多大の犠牲を伴った。皇帝に評価され出世する宋江等を恨んだ高俅等は、皇帝の下賜する酒に毒を盛り、宋江はそれを飲んで死亡する。
明終末期の宋江はどのように評価されていたのであろうか。『水滸伝』を賊書と評価する立場(1)では宋江は大賊首であり、同書を忠義の書とする立場(2)では忠義の首領となる。支配層の宋江評価は分裂していたが、明朝は崇禎末に賊書と指定し宋江を賊首とした。一方で当時、士大夫から大衆に至るまでの多くの人々は馬吊牌という札を用いた賭博に熱中し、宋江には「万万貫」という最高の数値が与えられていた(下図2)(3)。
なお宋江の肖像画の変遷について、佐竹靖彦氏は「胥吏的英雄の姿」(4)から、遼や方臘の乱等の指揮を通して「曹操や劉備とみまがう大豪傑」の如く描かれるようになったという(下図1)(5)。


事例(1)王中考
崇禎初年、陝西流賊の二大辺盗は東路の王嘉允、西路の神一元・神一魂兄弟であった。神一元等は慶陽府を中心とした陝西の山中を拠点として流動していた。神一元が犠牲になった後はその余党劉六等と、慶陽の大盗可天飛(本名、何崇謂)等が、深山の鉄角城を拠点にして農業と牧畜による自給の計(「分地耕牧〈『綏宼紀略』巻1〉)を模索し始めていた。この大集団の実質的指揮は何家老寨に拠点をおく可天飛であった。
崇禎4年10月、明軍は指揮系統の軸である三辺総督を、招撫を中心とした楊鶴から、掃討を軸に招撫を組み合わせる洪承疇に交替させた。この結果、神一魂を始めとした有力賊首が犠牲となった。5年8月、自給を計る可天飛等に、洪承疇指揮下で八方面から総攻撃が行われた。可天飛の有力部下を投降させ自軍に編成して攻撃に参加させたため、可天飛等の殺害に成功し、また八方面からの攻撃でも多くの戦果をあげた。その一方面を担当した総兵楊嘉謨の攻撃で死去した可天飛の幹部の一人と思われるのが表題の宋江をあだなとする王中考であった(6)。彼についてのそれ以上の情報はない。
事例(2)氏名不詳
崇禎14年2月、山東総兵楊御蕃の上奏中に以下のような記事がある。同年正月22日、賊首宋江から明軍の状況の探索を命じられた部下(「奸細」)王小等が捕まり、尋問された後処刑された。その後明軍に追跡され集団は手痛い打撃を受け、賊首宋江は火砲で攻められさらに鳥銃で撃ち殺された後、首を切断され押収された(7)。
事例(3)氏名不詳
崇禎14年5月、山東巡按李近古の上奏中に山東西部を拠点として運河周辺に出没する有力土賊一条龍と共に行動する土賊頭目に宋江の名が見られるが、詳細は不明である(8)。
現時点で収集した宋江をあだなとする事例は零細な三例のみである。陝西の初期流賊賊首の幹部一例と、宋江の地元山東の二例である。多数の好漢に慕われる宋江、ひたすら招安を求めるも除くべき奸臣の策動のもと、身内の犠牲を伴いながら宋のために忠義を尽くす宋江、こうしたイメージの影響について考察するには現在の収集事例では残念ながら不十分である。
事例研究
C-2 『水滸伝』関連のあだな 黒旋風(李逵)
■イメージ
李逵のあだなは、黒いつむじ風を意味する黒旋風である。江州の牢役人で上司は戴宗。二人は死刑囚の宋江を救おうと画策したため、明朝から死刑の判決を下されたが、梁山泊の頭領に救われともに梁山泊入りする。李逵は板斧二挺を振り回し、拳法・棒術の使い手である。性格は剛直で勇猛、純粋であるが行動は粗野で残忍、殺人が多い。宋江の意に反することが多々あるが、最後は常に宋江の仁義に従う。宋江の強い要望で、梁山泊108人の頭領が宋朝に招安された後、李逵は歩兵の頭領の一人として活躍するが、今そのことについてはふれない。
『水滸伝』中の李逵の役割について。「天に替わって道を行う」は先の宋江のイメージの項でも述べたように、忠義を尽くして宋朝のために戦うという内容であるが、梁山泊集団の成立の背景には、皇帝周囲の四悪人等を排除する使命もあった。しかし梁山泊を討伐に来た童貫、高俅は破れるも、彼らは宋江の強い招安希望により救われ、残る楊戩・蔡京もその地位を保ち梁山泊に敵対し続ける。
こうした状況に対して『水滸伝』の作家或いは複数の作家集団は、梁山泊頭領の、さらには『水滸伝』読者の不満を、李逵の一連の言動で代弁させた。幾つかの例を見よう。宋朝からの招安が認められ、梁山泊で証書が開読された際、招安に反対する李逵は詔書を破く(75回。百回本)。田虎との戦闘中のある日、迎春の儀で酔って寝ていた李逵は奸臣四人を斬る夢を見る。これを仲間に話すと皆手をたたきながら一斉に大声をあげて「愉快、愉快、そんな夢なら見甲斐もあるものだ」といった(93回、百二十回本)。次も夢の中の復讐話。皇帝からの毒入り御下酒(高俅等奸臣が毒を混入)を飲んで死んだ宋江、また宋江の道連れで死んだ李逵等が死後、梁山泊に徽宗を招いた。日頃の思いを徽宗に訴える宋江の背後から李逵が二丁の斧を振り回しながらおどり出て、四人の賊臣に煽動されて自分たちの生命を奪ったと怒鳴り、徽宗を殺そうとした。徽宗はここで夢から覚める(100回)。この数例からわかるように、四人の奸臣と徽宗への不満、梁山泊への帰郷願望は李逵の言動に集約される。しかし言動は常に宋江の宋朝への忠義に制約され、李逵の願望はわずかに夢の中で解消されるばかりなのである。

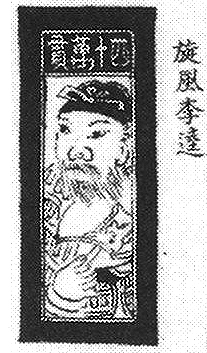
事例(1)氏名不詳
崇禎8年正月、明軍が捕らえた流賊の間諜(「賊諜」)の一人にあだな黒旋風が含まれていた(『平寇志』巻2)。
事例(2)氏名不詳
崇禎11年は多事多難の明にとって、一時的とはいえ有力賊首を含む多数の流賊を投降させるという成果を得た。そのなかで、太監盧九徳の率いる明軍が捕らえた流賊の一人にあだな黒旋風がいた(『明季北略』巻14)。
事例(3)氏名不詳
崇禎13年8月、再蜂起した張献忠に追従した曹操(羅汝才)を切り離そうとして、明軍の総指揮官楊嗣昌は投降した賊首金翅鵬の部下飛上天を遣わして明に再投降させようとしたが、張献忠も明軍に騙されるなと必死に彼を説得した。飛上天は直接曹操に会わず、張献忠の幹部の一人黒旋風に伝言を頼んだ。黒旋風は主人の張献忠には言わず直接曹操に告げた。これによって使者の飛上天が張献忠に拷問されることになった。この事態に危険を感じた黒旋風はからだひとつで明軍に投降し楊嗣昌に歓迎されるが、その後曹操を投降させるための使者として派遣された(『平寇志』巻3)。
事例(4)杜三
崇禎14年は李自成、張献忠を軸に流賊が華北・華中で再度活発になる年であり、その基底には地方反乱集団である土賊(土寇)の活発化があった。保定巡撫の楊進が北直隷とその周辺の山東西部、河南北部の土賊状況と明軍による掃討状況について20回に及ぶ上奏をし、兵部によるそれらの要約が残されている。その中に出てくる土賊の一つに山東の賊首・定咬金と有力部下の李逵(本名杜三)があって、重傷を負って捕らえられている。なお明軍がこの定咬金集団から押収した物に注目したい。
その中の一つの黄大旗には、混乱した国土を整理し安楽な国家(極楽浄土)を創る王(「整理江山安楽枉」)、同じく紅大旗にも天命に従う仁義の王(「順天仁義枉」)と書かれ、又部下に持たせた手旗には「官名」が書かれていたという。賊首定咬金とその幹部の李逵(杜三)について現在のところこれ以上の情報を得られていないが、一土賊が秩序を志向した事例と考えられる(9)。
事例(5)氏名不詳
順治初年は大流賊首、掌盤子は消滅したものの、清の支配下にはいらない残党や地方土賊が各地に存在していた。順治4(1647)年9月、陝西鳳翔府属の麒麟県にも「賊頭李養気、黒旋風、五闖王の馬歩約500余名」が存在していた(10)。
以上現在まで収集した李逵をあだなとした事例は流賊が三例、地方土賊が二例であるが中堅幹部や土賊に人気があることが伺える。
(その5に続く)
【註】
(1)左懋第の上奏文(本連載第十八回・註11)。すでに明中期の人、陸容が著した『菽園雑記』巻14で「宋江等皆大盗」と記す。明終焉の直前の崇禎14(1641)年に出版された、金聖嘆『水滸伝』70回本は、「悪人宋江をさらに悪党にした」(高島俊男『水滸伝の世界』十五、大修館書店、1987)等。
(2)李卓吾『忠義水滸伝序』。李卓吾は宋江以下108人の野盗集団を忠義の臣とした(本連載第十八回・註5、溝口雄三『李卓吾』集英社、1985)。「水滸者、忠義の別名」(陳章候『水滸牌』によせた王亹漫の〈頌〉)。
(3)水滸伝に登場する人物を描いたカードを賭博に用いた記録は、明中期の正統元年(1436)から弘治9年(1494)を生きた蘇州府大倉の人、陸容『菽園雑記』に記されている。遊学先の昆山県では「葉子を闘わす戯」、すなわちカード賭博が盛んで士大夫から彼らに仕える子供まで盛んに行っていた。札の万貫以上には『水滸伝』の人物が描かれ宋江は「万万貫」が当てられていた。陸容はこうした状況について宋江等以下皆大盗であるから、彼らを描いた札で行う賭博は掠奪行為と同じと危機感を表明している。
明末に盛んに行われた後世の麻雀の祖となる馬吊牌については大谷通順氏の研究がある。この賭博は知的戦略的判断を必要とする遊戯方法なので士大夫階級に好まれたという(大谷通順『麻雀の誕生』大修館、2016)。明終末期に至ると『水滸伝』を禁書とするよう要請した左懋第(前註1)は、都市の大衆(〈街市小民〉)が宋江等賊名の画かれた紙牌で、破産するまで財物を賭けていると危機的状況を述べる。
なお明末に広まった賭博、馬吊とは一セット40枚の馬吊牌から30枚を抜き出してカードの強弱を争う。牌はすべて紙幣と貨幣の単位が当てられ、四門からなる。餅子(文銭門、穴あき銭)11枚、緡銭(索子門、さし銭)9枚、万字門(万貫門、銭の単位)9枚、十字門(十万貫門)11枚よりなる。餅子・緡銭には水滸の人物を充てるが札の内には記さず、万字門・十字門の札の中には水滸人物を画く(大谷同上書、なお図2の宋江画は、同書内の馬吊牌(『京吊譜』)による。『東方』480号:本連載第四回)。
(4)容与堂本『水滸伝』第42回の挿絵。
(5)陳洪綬『水滸葉子』。なお陳洪綬の画く英雄図は従来の『水滸伝』の英雄のイメージを大きく変えるほどの影響力をもったという(瀧本弘之「〈水滸伝〉諸本の挿絵について」〈瀧本弘之編『水滸伝 中国古典文学挿画集成(三)』遊子館、2003)。
(6)「兵部題為恭報誅剿渠魁等事」(『明末農民起義史料』、崇禎6年の項)。
(7)「兵科抄出山東総兵楊御蕃題本」(『明清史料』壬・四)。
(8)「山東巡按李近古題本」(『明清史料』甲・一)。
(9)「兵部題〈保定巡撫楊進題〉」(『明清史料』乙・十)。
(10)「劉明偀報陝西及鄖陽農民軍情掲帖」(『清代档案史料叢編』六。中華書局、1980)。
(さとう・ふみとし 元筑波大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
