|
2011年1月、南方週末、南方都市報のベテラン記者、編集者だった長平(本名は張平)氏はジャスミン革命などが引き金となったメディアへの締め付け強化で、両紙を発行する南方報業集団を追われ、広州から香港に移住した。
ラジオ自由アジア報道(2011年12月7日)によると、会社側は長平氏に「筆を折って沈黙するか、これまでの立場を変えるか」どちらかの選択を迫ったという。報道によれば、長平氏の解雇には共産党中央宣伝部のトップクラスの人物が圧力をかけたとの見方も出ている。その後、長平氏は香港のテレビ局が発行する電子雑誌「陽光時務」の編集長に就任したが、香港政府は長平氏にビザを発給しなかった。引き続き中国当局からの圧力を受けたとみられ、「国境なき記者団」は香港当局に抗議のメールを送っている。さらに、長平氏が開設した微博(短文書きこみサイト)は一方的に削除されるなど、様々な嫌がらせの中、やむを得ずドイツ行きを選んだようだ。
北京で初めて会った時、「自分は新聞社で長年働いてきたので、どこまで書けば当局の規制に引っかかるか、その『尺度』はわきまえているつもりだ」と述べていた長平氏だったが、当局側の度を超えた規制強化の動きに、彼のような人物すら壁の外に追いやられてしまったのは、残念でならない。
さっそく、この記事を紹介するメールを長平氏にも送った。するとお礼と共に最近次のようなインタビューを受けたとご返事をいただいた。
“Is Democracy Chinese? An Interview with Journalist Chang Ping”
インタビューは前述した経緯のほか、彼の生い立ち、学生時代、天安門事件の時の状況などについて触れた後、今回の韓寒の文章でも問題になった中国と民主の問題について次のように答えている。
「中国には民主が必要だと考えており、中国は変革が必要だ。私は中国には民主主義が育たないという議論に本当に反対だ。中国は特殊で、中国人の素養(中国語では「素质」)は不十分なので、時間がかかるといった愚かな議論だ。民主主義は中国文化の中には存在しなかったという人もいたが、(中国文化圏の)台湾は民主化したではないか。すると彼らは台湾は特殊だという。だが烏坎(注:広東省陸豊市烏坎村)はどうか、彼らは自ら選挙を行ったではないか。烏坎は典型的な中国であり、烏坎が民主を実践できるのなら、中国の他の部分も同様(に可能)なのだ」
質問者の「韓寒のコラムについてどう思うか?」との問いにはこう答えている。
「韓寒は、中国の人々は素養が低く、もし民主を導入すれば暴力につながるから問題だと論じている。これは(中国)政府が長年宣伝してきた見方だ。まるで『あなたは泳げるようになるまで、泳ぎの練習をしてはいけない』と言っているようなもので、練習できないのだから泳げるわけがない。そして、提起した議論は真新しいものでもなかった」
「だが彼がこの問題を提起したのは興味深いことだ。このことは中国ではいかに政治的システムが制限されているかということを示したのだ。今我々が目にしているのは、多くの人々が、変革が起きることへの望みを失っていることであり、そして彼らはなぜそれが起きないのかの言い訳をしている。モラルの衰退が反対者らに対する暴力へとつながっているが、それは革命を手に入れられないからだ」と述べている。
正直、前回自分の書いた韓寒への見方と長平氏のそれとにあまり違いがないと知ってほっとした。
さて、長平氏がシンポジウムで述べたのは「被代表」という当時は耳慣れない言葉をめぐる議論だった。これは2009年末に広州市番禺区で起きたゴミ焼却場建設をめぐる問題だ。シンポジウムの発表によれば次のような経過だった。
09年11月、1000人以上の広州市民が同市庁舎前に集合、抗議活動を展開、これは1989年以来広州で発生した最大規模の抗議活動だった。この運動の原因は、番禺区に建設が計画されたゴミ焼却発電所への反対だった。政府は5年もの間、密かに建設計画を進め、住民は全く知らされていなかった。環境アセスメントなどの法的プロセスを経ずに、地元政府は建設を発表した。
番禺事件で大多数の住民がプロジェクトに反対していた時、地元紙「番禺日報」は1面に、番禺区の人民代表大会代表70数人が計画用地を視察後、「ごみ焼却発電所は民心工程(国民生活向上のためのプロジェクト)であり、政府がこの民心工程建設を加速することを大いに支持する」と述べたとの記事を掲載した。
このように、住民の民意に反して、勝手に一部の人間に「賛成」だと民意を代表されてしまう、これが「被代表」の意味だ。
抗議活動で住民は「不被代表」というスローガンを掲げた。自分の意思は誰にも代表されることはない、という表明だ。「このスローガンは公民個人の権利意識の自覚を意味する。『不被代表』によって初めて政府の役人は真の民意を知ることができるし、真の代表が生まれるのだ」長平氏はこのように述べている。
住民の抗議に対して、市側は態度を軟化、09年12月、番禺区の党委員会書記は住民に対し建設中止を発表した。広州市政府はさらに、今後住民の利益と密接に関わる重大な政策は、幅広く民意を聞き、十分な調査をすることを決めた規定を発表した。
だが中国国内の報道を見ていると、被代表は枚挙にいとまがない。例えばハルビン市で09年12月、水道料金値上げに関する公聴会で、市民代表の劉天暁という男性がペットボトルの瓶を投げつけるという事件があった。
出席した13人の市民代表のうち、下崗(レイオフ)された労働者として出席したのは、実は退職した同市の幹部だった上、唯一値上げに反対した劉天暁氏は発言の機会が与えられなかったことから、ペットボトルを投げつけて抗議したのだ。こうした偽代表を使って民意を偽り、一方的に政府の決定をごり押しする手法は番禺のケースと共通する。この事件は「瓶子門」(「~門」は「~事件」の意味で、米国のウォーターゲートから来ており、中国のメディア、ネットでしばしば使われる表現)としてネット、メディアでも広く伝えられ、同様の公聴会への批判が高まった。
この「被」という言葉が中国社会で広がったのは、09年ごろだ。本来なら「~される」はずのないことまで、「被~」とする表現が次々と生まれ、「被時代」という言葉も生まれた。中国のサイト「互動百科」は次のように説明する。
「被時代では、誰かが『☓☓される』ということは、必ず他人に『☓☓する』人がいるということだ。ある人の権利が主張することができず、勝手に侵犯される、その一方で他人を圧迫して権利を享受するものが必ずいる」。そして次のような「被」の数々を紹介している。
「被自殺」…2008年3月、安徽省阜陽市潁泉区の張治安書記が違法に農地を収用し、さらにはホワイトハウスのような豪華な庁舎を建てたことを告発していた李国福さんが、監獄内の病院で死亡したが、検察機関は「李さんは首つり自殺した」との調査結果を発表、家族はこれを受け入れなかった。(報道によると、その後張治安は汚職の疑いで逮捕され、1審で執行猶予付き死刑判決を受けた。)
「被小康」…「小康」とは「ややゆとりのある生活水準」の意味だが、09年2月、江蘇省が南通市管轄下の県、市にたいして小康に達したかどうかの電話民意調査を実施した際、地元政府は調査を受けた住民らに対し模範答案を事前に配布、家庭平均年収は、農民は8500元、都市住民は16500元であると答えるよう求めたという。その結果、元々は小康レベルにない住民が、一夜のうちに小康にされてしまった。
「被増長」…09年7月28日、国家統計局が今年前半の全国都市住民の平均収入は11.2%、農民は8.1%増加と発表、都市住民の伸びはGDPの伸び7.1%を上回ったが、「物価は上がっても自分の所得は増えていない。この数字は水増しではないか」と多くの人々が疑問を抱いた。
「被自願」…09年5月の新京報報道によると、重慶市銅梁県の保護者らが、学校に9000元の「教師節慰問金」を支払うよう要求されたと訴えた(教師節は9月10日、教師に日ごろの感謝や尊敬の気持ちを示す行事)。保護者が教育委員会に意見を述べたところ、「お金を返すのなら、教師を引き上げる」と告げられた。銅梁県教育長は取材に「保護者は自ら望んで支払った」と述べたという。
「被就業」…7月12日、西北政法大学の09年卒業生だった趙冬冬さんは、国内の著名なウェブサイトに、自ら知らないうちに大学が西安のある企業と就職協議書にサインしたが、このような企業は聞いたこともないと書き込んだ。一部の大学は学生の就職率が高いことを宣伝するため、このような水増しを行なっているとされる。
|
|
今月のことば
被代表:自分の意志が勝手に第3者によって代弁されてしまうこと。多くは世論操作のため、当局の都合のよい形で使われる。
被時代:被代表、被自殺、被小康、被就業など、「被~」が社会現象を表すネット流行語として次々と登場した時代状況を指す。自分の権利を第3者が勝手に左右されることは許さないという権利意識の向上もうかがえる。
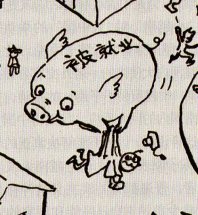
「~門」:事件、スキャンダルの意味で、米国のウォーターゲート(水門)事件から来ており、中国のメディア、ネットでしばしば使われる表現。
|





