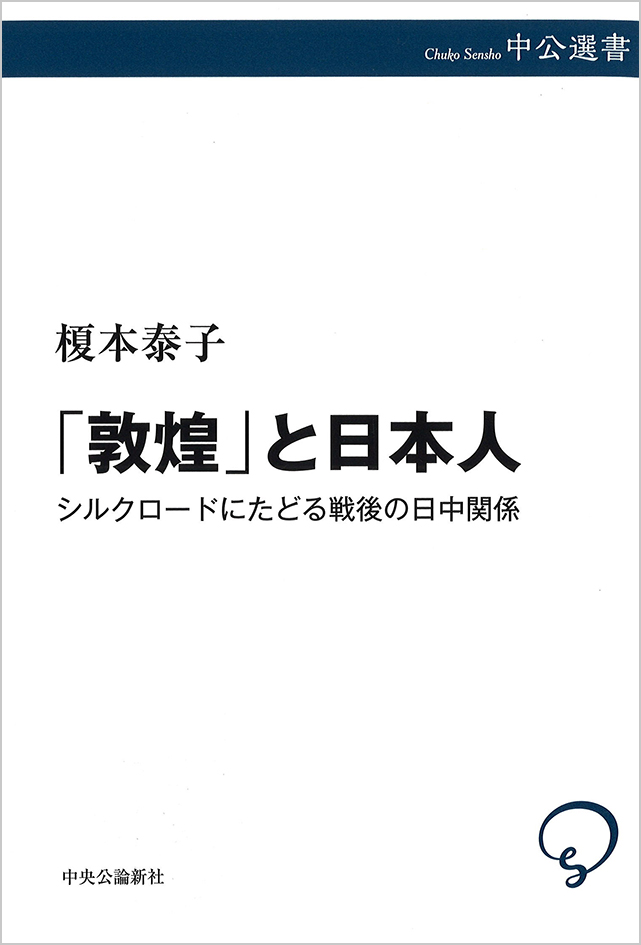
榎本泰子 |
著者・榎本泰子氏は、私にとってまず第一に、中国近代音楽史研究の大家である。氏の著書『楽人の都・上海』(研文出版、1998年)、『上海オーケストラ物語』(春秋社、2006年)は、政治史や文学・映画史に埋もれる形で日の当たりにくかった中国近代の音楽史における画期的な業績であり、前者はサントリー学芸賞と日本比較文学会賞を、後者は島田謹二記念学芸賞を受賞している。しかも、それらは研究書然としたいかめしい体裁を取らず、平易な表現と明快な論旨で、一般人が「研究」というものの恩恵を享受できるような形を取る。氏の姿勢と特質とをよく表しているだろう。
その榎本氏が『上海』(中公新書、2009年)を上梓した時には、それまでの氏の研究が上海を舞台としていたことを思えば意外の感はなかった。しかし、『宮崎滔天』(ミネルヴァ書房、2013年)の時には、ひどく意表を突かれる思いがした。そして今回は『「敦煌」と日本人』である。氏の学問的世界はどのように広がり、どこを目指しているのであろうか。『楽人の都』以来、氏の研究に注目し、多くの学恩を受けてきた私は、本書の刊行を知った時、何はさておきその点に関心を持った。
さて、本書は中国西域の都市「敦煌」の地理や歴史についての解説書ではない。タイトルの通り、日本人が「敦煌」とどのように向き合ってきたのかを考察したものである。
おそらくは4世紀から数百年をかけて作られ、大量の仏典が密封された敦煌(莫高窟)が、ペリオやスタインという西洋人探検家によって長い眠りから覚め、世界の注目を浴びるようになったのは、20世紀の初頭である。日本人は早い時期から敦煌文書の学術的価値に着目し、京都大学を中心として解読作業に大きな業績を積み重ねた。一方、敦煌に対する一般庶民の関心は、1950年代に井上靖の小説『敦煌』が発表されたことや、壁画の模写、仏像の写真を展示した「中国敦煌芸術展」が日本で開催されたことから始まり、1980年代のNHK「シルクロード」や小説『敦煌』の映画化によって頂点に達する。
このような歴史を、著者がどのように描いたか。目次を手がかりとして見てみよう。
第一章 井上靖と「敦煌」
第二章 日中国交正常化とNHK「シルクロード」
第三章 改革開放と映画『敦煌』
第四章 平山郁夫の敦煌
第五章 大国化する中国とシルクロード
第一章では、「敦煌」を日本の庶民に印象づける上で絶大なる影響力を持った小説家・井上靖を中心に、国交回復前の日中間で敦煌をめぐるどのような交流が行われたかを描く。関連人物として探検家・大谷光瑞、早くも戦前に『敦煌物語』を書いた松岡譲、井上の知恵袋であった京都大学教授・藤枝晃、日本人として戦後最も早く敦煌を訪ねた画家・福田豊四郎、北川桃雄などが重要な役割を果たす。
第二章では、それまで未踏に近かった敦煌の情景が、テレビの現地取材によって初めて日本人の目に入るようになるまでの過程が描かれる。「シルクロード」を企画したNHKディレクター・鈴木肇を中心に、西域と関係の深い小説家・中島敦を世に紹介し、自らもイラン、アフガニスタン方面のシルクロードに足を運んだ作家・深田久弥や、台湾籍の在日歴史作家・陳舜臣などを取り上げる。
第三章では、映画分野における日中交流と、映画『敦煌』の制作プロセスが描かれる。中国に対する強い贖罪意識から、損得を顧みずに両国映画の紹介に努めた徳間書店・大映社長・徳間康快を中心に、徳間の支援を受けた中国文学者・竹内好、映画監督・佐藤純彌などが登場する。
第四章では、画家・平山郁夫が、画業だけではなく、敦煌の文物保存や政治的な影響力も含めて描かれる。話題となるのは圧倒的に平山だが、大平正芳、竹下登といった大物政治家の動向にも目は向けられる。
日本人だけではない。敦煌の文物保存に尽力した画家・張大千や常書鴻、日中交流の中国側の窓口であった張香山、廖承志、更には鄧小平、趙紫陽といった首脳も、要所要所で存在感を発揮する。
ここまでの章には一貫性がある。小説、テレビ番組、映画、絵画と分野は違うが、それぞれの分野で大きな役割を果たした人々の動きを詳細に追うことで、主題である「敦煌」と日本人との関係をあぶり出しているということである。丁寧な調査と明快な構成、著者一流の平易な表現とによって、私たちは20世紀後半の純粋で真摯な日中交流の世界へと引き込まれて行く。著者が何のためにそれらを描こうとしているのかなどという小難しいことを考えなくとも、一幅の人間ドラマとして十分に読み応えがある。
著者も繰り返す通り、それらの時代、敦煌は「ロマン」の対象であった。「ロマン」とは、隔たりの向こう側に対する憧れの感覚であるだろう。約千年前に眠りに就き、政治的事情から訪ねることの極端に難しい場所であることによって、確かに敦煌は隔たりの彼方にあり、「ロマン」であり続けた。仏教伝来の経由地として、中国西域を日本文化のルーツに関わる場所と認識した日本人は、なおのこと強い思い入れをもって敦煌を見つめてきたようだ。
国交が回復し、文化大革命が終わり、中国が改革開放政策を取ることで、敦煌は一般人が容易に訪ねることのできる場所になった。手の届くものにロマンはない。同時に、敦煌自身も変質を始めた。
第五章がそれ以前の4章とまったく性質を異にするのは、そのような時代の差異によっている。著者は、敦煌ブームの最終章として1988年の「なら・シルクロード博覧会」を取り上げた後、自らの個人的な思い出も取り混ぜた中国旅行の歴史、天安門事件による対中イメージの急激な悪化、西域での核実験やウイグル族弾圧問題、韓国、台湾、シンガポールといった他のアジア諸国に対する関心の高まりに伴う、中国への関心の相対的低下、「一帯一路」政策の中での西域の地位、と叙述を進める。もはや主人公は存在せず、取り扱う問題は目まぐるしく変化する。一見「乱脈」と言ってよいほどだ。
だが、この章があることによって、著者の問題意識のありかは明瞭になっている。すなわち、著者の心の内には、決して良好とは言えない現在の日中関係や、国際社会における中国の振る舞いに対する憂慮がある。思えば、「はじめに」で著者は「『昔』を知ることは、現在、そしてこれからの時代を、どうやって乗り切っていくのかを考える契機となるはずだ」と書いている。著者は、異質な二つの時代を描くことで状況を相対化し、対立を緩和させるきっかけが生まれることを期待している。先立つ4章で、著者が30年以上前の日本人と敦煌との関わりを描くのは、決してノスタルジーではない。
二つの時代を相対化し、問題解決の可能性を探るという著者の考えに接する時、私の脳裏にふと浮かんだのは、一見突飛な『宮崎滔天』も同様の発想に基づいて書かれたのではないかということだ。著者には、研究は現実と関わり、現実に対して力を持つべきだという思いがあり、歴史研究が日中関係の緊張緩和に力を持つためには、少なくとも近代以降の中国もしくは日中関係を、広く眺め回すことが必要だと考えているようだ。ひとつの見識であろう。
ところで、著者は同じく「はじめに」において、「敦煌」に「胸をかきたてられる人と、そうでない人」すなわち、20世紀後半の敦煌ブームを知る人と知らない人との間には、「中国そのものに対する感情に大きな差がある」と指摘する。その上で、「中国に対するイメージが世代間で大きく異なり、知識や経験の面でも断絶があることは、今後の日中関係に影響を及ぼすのではないか」と危惧する。日中関係の改善という現実的課題を考えた場合、対中感情の世代間格差という問題を避けては通れない。そのように考える著者は、「本書には(中略)今日筆者が教壇で接しているような若者たちに『昔』を知ってほしいという願いがある」とも書き、読者として若者を期待する。
だが、私はむしろ逆のことを考える。現在の対中感情の悪さは、おそらく世代には関係がない。天安門事件以降しか知らない若者が、中国に対して良いイメージを持っていないのはもとより、敦煌ブームを知る旧世代も、領土や人権といった数々の政治問題を目の当たりにして、日中関係を前向きに考えることができていない現実があるだろう。しかも、かつて中国に対して夢や憧れを抱き、中国の人々と手を取り合おうとした経験を持つにもかかわらず、そのことをほとんど忘れ去ってしまっている。本書は、そんな夢と憧れ、協同の意識をリアルに思い出させてくれる。それは「実感」であり、若者が本書を読んだ時に得る「机上の知識」よりも、遥かに両国間の緊張緩和に向けて力になり得るはずだ。動機はノスタルジーでもいい。私は旧世代にこそ本書を手に取って欲しいと思う。若者は後から付いて来る。
(ひらい・たかし 宮城県塩釜高等学校)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
