「中国史史料研究会」について
◇研究会発足の趣旨
2018年に志学社を創業するにあたり、研究会を立ち上げようというのは当初からの念願でした。
というのも、前世紀の終わり頃から、各大学の中国史専攻などに紐づいた学会が院生の減少などで運営困難に陥ったり、あるいは継続はできているものの事務局の負担があまりにも大きい……という事象に対し、どうにかしなければならないという思いがありました。
私自身が、かつては大学院生として学会の運営に関わっていましたが、報酬がなかったり、負荷が大きかったのは悩みの種でした(そもそも、大学院生自体が経済的に不自由なものです)。しかし、研究者や愛好家が所属して情報交換をしたり、切磋琢磨したりする場として、研究会は必要なものです。私もそういった場で鍛えられたという実感がありました。
そこで、志学社という法人が運営元になることで、持続可能性のある仕組みでの研究会運営ができないか、と考えたのが最初です。会社の立ち上げと並行して、一年弱かけて賛同してくださる研究者の方々を募り、2019年の4月に発足しました。
◇対象範囲と活動
中国史史料研究会のカバーする範囲は広く、広義の「中国史」に関する、「史料」に基づいた研究であればなんでもOKとしています。つまり、殷代の甲骨文から、現代のゲームなどのコンテンツ、ネットの書き込みまですべての文字史料が対象の範囲となりえます。これだけ対象範囲の広い研究会は他にないのではないかと思います。
問題は、事務局などに古代史(先秦史)研究者が多く、少々偏ってしまっていることですが、これは今後の課題の部分でも述べます。
現在の主な活動としては、『中国史史料研究会会報』の隔月発行、不定期でのシンポジウム開催、2025年に創刊した会誌『中国史史料研究』の年一回刊行(目標)があります。
会報はエッセイや書籍紹介などの読みやすい記事が中心で、論文や研究ノートは会誌に掲載するという棲み分けを行なっています。
また、会報はスマホ閲覧に最適化したPDFでメールにて配布しており、郵送にかかるコスト、印刷にかかるコストを削減することで、支出を大幅に抑えています。かつて院生時代に研究室総出で発送作業を行なっていた経験を繰り返したくないという思いがありましたし、もしかしたら会員の本棚スペース捻出にも少しは貢献できているかもしれません。
会報では現在、モンゴル史の赤坂恒明先生に内蒙古赴任体験記を、(日本の)南北朝時代がご専門で、台湾大学に奉職されている亀田俊和先生に台湾在住研究者としてエッセイを連載いただいています。いずれも他の研究会では読めないような記事であると思います。特に、亀田先生の連載は、それを目当てに会員になっている方もいるほどで、日々の新鮮な台湾体験が人気です。
なお、現在の会員数は200人程度で、うち25%程度を学生会員が占めています。会費の安価な学生会員の比率が高いことも特色ですが、中国史に興味がある一般会員、特に女性の会員が多く、研究者の比率が低いことは特筆できると思います。一般読者、一般の歴史ファンに対して開かれた研究会でありたいというのが設立時の思いだったので、この会員構成はありがたく思っています。
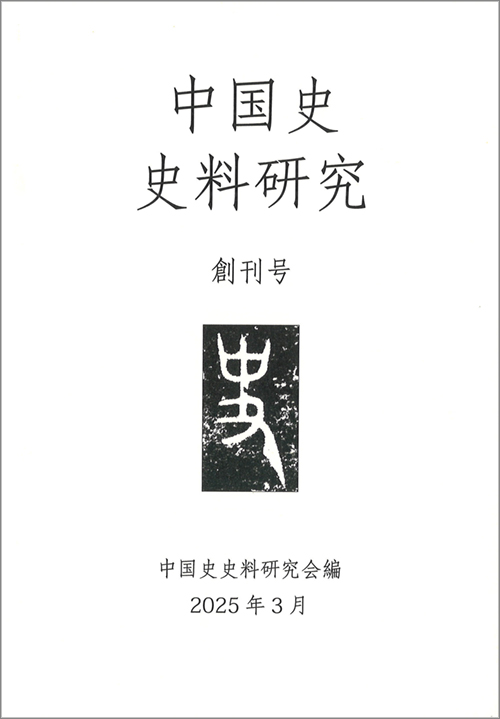
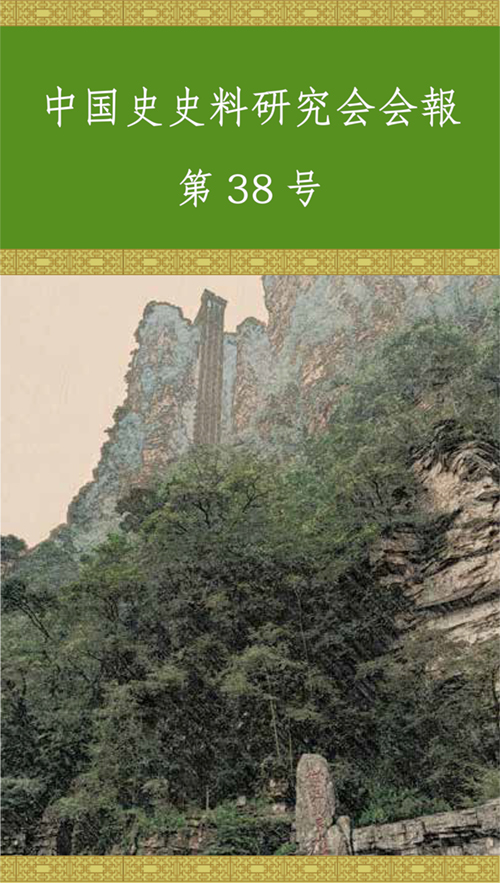
◇中国史史料研究会の特色
もうひとつの特色として、会費の支払いをクレジットカードに限定し、会報や会誌もPDFで配布(会誌の紙版は東方書店さんで購入可能、会報はKindleでも配信)、シンポジウムもオンライン参加可能と、すべてネット経由で完結するように設計していることが挙げられます。
これは、当初は運営コスト的な面から考えた設計だったのですが、瓢箪から出た駒で、降ってわいたコロナ禍でも会の活動を滞らせることなく運営できました。また、結果的に都市部以外の方や海外在住の会員の方が増えるきっかけにもなったようです。中国を中心に、海外在住の会員もいくらかいらっしゃいます。
シンポジウムは会員でなくても参加可能ですが、こちらもオンライン開催のため、世界各地からの参加者がいらっしゃいます。オンライン開催はコロナ禍で広まった習慣ですが、今後もそのメリットを活かしていければと思っています。
そして、設立の際に一番こだわったのが原稿料等ギャランティの支払いです。会報の原稿にはすべて規定原稿料を支払っており、会員からの投稿原稿が掲載された際にもお支払いしています。シンポジウムの登壇料も、それなりの額をお支払いできています。とにかく「持ち出し」や「手弁当」はいずれ限界が来るので、善意に頼らずにきちんとお金を支払おうというのは徹底しています。これも、法人が運営を行うからこそ実現できたメリットであると考えています。もちろん、すべての研究会・学会がお金に厳しくあるべきだとは思いませんが、当研究会のコンセプトとして覚えていただけると幸いです。
入会に制限はありませんので、会員になって投稿原稿が掲載されれば、事実上会費が無料状態になります。これまでに「白馬非馬の世界:ボーダレスの平和論」「研究者旧蔵書を読む:貝塚茂樹と仁井田陞」といった投稿原稿を掲載しています。
中国史関連でなにか文章を書いていて、広く読んでほしいという方は、ぜひ入会と投稿を検討いただければ幸いです(投稿規定は下に掲げるウェブサイトで閲覧可能です)。
◇今後の課題
法人が運営しているとはいえ、その法人が零細事業者であることもあって、新しい試みがなかなかできていません。
また、昨年はシンポジウムも開催できませんでした。先に述べた先秦への偏りの解消なども含め、今後の課題が多くあります。
特に中世・近世研究者が手薄な状況には設立以来悩んでいますので、これらの時代を研究している方はぜひご助力いただければと思う次第です。運営に関わる研究者の方が増えること、興味を持って入会してくださる会員の方が増えることは、それだけ会に厚みをもたらすことになります。
会員が増えて儲かった方がいいというのとは別にして、より多くのものを提供するために、会が大きくなればいいと思っています。
◇会報準備号
入会を迷っておられる方には、会報の準備号を無料で公開していますので、こちらをご覧いただけましたら幸いです。
中国史史料研究会会報 準備号 目次
創刊のご挨拶(佐藤信弥)
[回想録]亀田俊和の台湾通信:第1回(亀田俊和)
[学会報告]第29届 中国文字学国際学術研討会参加報告(佐藤信弥)
[紀行]興城古城(寧遠城址)紀行(綿貫哲郎)
[学術札記]前漢功臣伝抄:はじめに(平林緑萌)
[書籍紹介]岡本隆司『近代日本の中国観:石橋湛山・内藤湖南から谷川道雄まで』(池田修太郎)
[エンタメ]中国時代劇の世界:第1回『昭王〜大秦帝国の夜明け〜』(佐藤信弥)
研究会案内
執筆者紹介・編集後記
2019年度 中国史史料研究会役員構成
https://shigakusha.jp/assets/images/uploads/2019/05/beb71fa21afeee6169ea6dea8f2f68a4.pdf
◇ウェブサイト
入会は下記のウェブサイトから可能です。
(中国史史料研究会志学社代表/中国史史料研究会理事 平林緑萌)
*ウェブサイト:https://shigakusha.jp/hoc/
