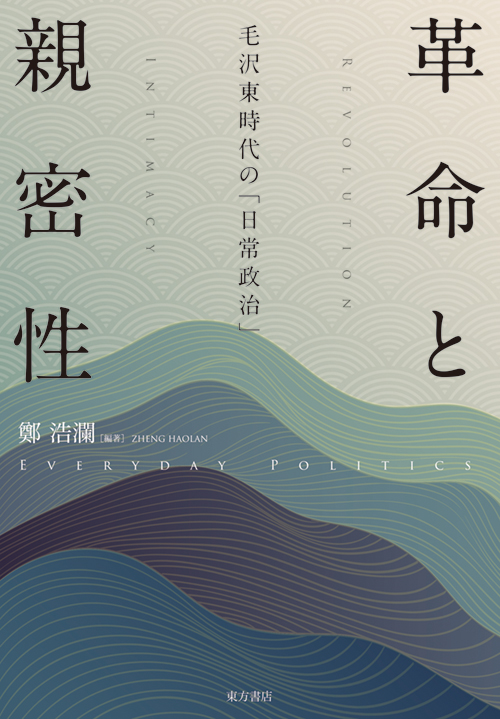
|
現代の中国は、革命の時代から一世代以上が経過し、社会主義の日々は遠い記憶の彼方に過ぎ去ろうとしているようだ。「魂にふれる革命」と言われた毛沢東時代(1949年から1976年)の革命は、権力機構の変化をもたらしただけではなく、人々の生きる場での身近な人間関係のあり方を大きく変え、運命を翻弄するものでもあった。
本書は、普通の人々の生からみたとき、毛沢東時代の革命とは一体、何だったのかを、親密な関係のあり方から解き明かそうとした論文集である。編者鄭浩瀾の「序章」によれば、親密な関係とは、一つには性や婚姻や家族にまつわる関係であり、もう一つは友人や同僚を含めた「他者との近い関係」であるが、いずれも感情や身体を伴う人間の生にとって不可欠な私人関係である。毛沢東時代の革命は、階級闘争の矛先をこうした親密な関係そのものに向けた。
農民にとって革命イデオロギーの内面化とは、革命によって出現した新たな階級秩序を理解し、それに順応して生きることであった。都市では、革命イデオロギーの受容のあり方はより複雑で、世代によっても多様であった。当時の「日常政治」は、人々が日常生活の中で政治権力を向き合いながら状況対応的に表出した実践そのものであった、と編者は言う。
以下、各章の内容を紹介し簡単にコメントする。
第一部「婚姻、性と権力」は、主として農村の婚姻とセクシュアリティをめぐる関係を考察する。第1章「革命とジェンダー関係:1949~1953年──江西省の離婚事例を通して」(鄭浩瀾)は、建国初期に婚姻法ができた中で、離婚を求める女性と対応する男性や幹部の対応を読み解き、権⼒を持つ男性はそれを⾏使して⼥性に対する旧来からの⼼情や⾏動を「階級闘争」という名で実行していた、という。
第2章「中華人民共和国婚姻法と革命軍人の婚姻問題」(丸田孝志)は、朝鮮戦争までの長期にわたる総力戦継続の中で、軍人である夫が不在中の妻に対する国家の対応をみる。事実婚や婚外婚を選択したり、離婚訴訟を起こしたりする妻たちに対して、国の対応は揺れ動くが、そうした中で婚姻文化に国家が介入してゆく。
第3章「人民公社期の農村における婚姻関係の変容」(李秉奎)は、1960-70年代の人民公社体制の婚姻をめぐる論考。家長の権威は低下して、村内の若い男女が知り合う機会が増えた一方、以前の通婚圏の中心であった集市(定期市)は1966-78年は制限されていて、結果、村内婚が増加した。とはいえ若者は自由に結婚を決めていたわけではなく、取り決め結婚(包瓣結婚)と自由恋愛の中間の仲介人の取り持つ結婚が増加した。
第4章「人民公社期の村落における両性関係──浙江省海寧市聯民村を事例として」(張楽天)では、著者の故郷の農村での人民公社時代の性をめぐる多様な状況が活写される。革命イデオロギーは性を語らず、性は罪で、汚れで、反動だった。しかしその村人への束縛は限定的で、村では多様な婚外関係が存在して村人はおおむねそれに寛容だった。革命の論理は性にかかわる人間の欲求を改造できはしなかった。
以上の第一部の各論文の論点で印象深かったことの一つは、人民公社体制を通じて村が地縁的集団になった、とされていることだ。中国の村落が共同体でなかったことは、夙に旗田巍が指摘して以来、日本の学界の共通認識となっていたといえようが、人民公社期に変化がみられたとしたら、現在はどうなのだろうか。もう一つは、幹部が権力を使って女性の性を占有することが、様々な場面で行われていたと指摘されていることである。
第二部「革命の論理と家族の絆」は、都市の知識人の家族関係が革命の論理のもとでいかに変容したかをみる。第5章「夫婦の感情と結婚生活──家族間の手紙に基づく分析」(魏瀾)は、ある夫婦が26年間に交わした679通の手紙から夫婦関係と感情を分析する。夫との関係に平等でロマンチックな愛情を求める妻と、政治的な進歩を求め「革命が愛情に優先する」「積極分子」である夫とは、それぞれの求めるものに距離があった。社会主義イデオロギーの内面化が、夫婦関係にどう影響したかを具体的に垣間見れるケースである。
第6章「ある小資産階級家庭の生存戦略と親子関係:1965-1972」(黄彦杰)は、上海の資本家家庭出身者が1965-76年に書いた705通の手紙から、政治の暴風雨の中での家族の戦略と彼の心情の変化を読み解く。人民共和国成立後、1950年代には多くの元資本家たちは快適な生活を続けられたが、文化大革命の風雨がそれを許さなくなった中で、対応も変化する。政治的パフォーマンスも含まれている手紙を読み解きながら、社会的上昇への希望と人々の生を支えていた親密関係が考察される。
こうした第二部の個人史料に基づく論稿からは、政治運動の日々の中で政治への関わり方を模索していた生身の人々の生活が実感される。
第三部「社会生活の空間における親密性と革命」は、職場や村落という生活コミュニティにおける多様な場面での親密性と革命の関係を考察する。第7章「若き女性同志たちの悩み──毛沢東時代に日記を書くこと書かないこと」(泉谷陽子)は、三人の若い女性が1950年代に書いた日記を分析する。当時、日記を書くことは党によって推奨される、国家に役立つ人材に自分を作り変えるためのものであった。それゆえ、真に私的なことは日記には書かれず、正しい態度、適切な行為だけが記されている。
第8章「政治と娯楽──建国初期の都市社会におけるダンスの興隆」(大濱慶子)は、建国直後から反右派闘争の時期にかけて、都市の人民が熱狂したダンスを取り上げる。日本のフォークダンスに似た「集団舞」は、中国の秧歌をソ連や東欧のダンスと融合させて業余の娯楽として広められた。ボディコンタクトを通して初対面の人と親密な関係を築き、均質な身体が構築されるダンスは、政治運動と表裏一体の娯楽活動として、大衆動員を可能にするものだった。
第9章「「おばあさん保母」から見る村落内部の託児活動──大躍進前後、黒竜江省の事例」(横山政子)は、大躍進期、女性を集団農業労働に参加させるために村々に組織された託児組織を論じる。1958年から爆発的に増加した託児所だが、その状況は場所によって多様であった。「おばあさん保母」も少なくなく、従来の村の親密な関係に依拠して場所や保母が確保されたのである。
第10章「「共餐」をめぐる革命と私的人間関係──1960年河北省の資料から」(小嶋華津子)は、公共食堂の「共餐(食事を共にすること)」から、そこにおける私的人間関係と、その革命や権力構造への作用を論じる。飢餓の広がった1960年を通じて公共食堂は推進され続け、民衆に最低限の食事を提供して生存を確保する砦としての意味を強めた。一方で、管理員・炊事員が私的関係を持つ者や権力者を優遇する行為が普遍的にみられた。また、公共食堂の外側で幹部による贅沢な官官接待などの「共餐」が広がっていた。幹部と民衆が共産主義的な共同体を構築する実験場であったはずの公共食堂は、民衆の家での「共餐」の場を取り上げた一方、権力の私物化、幹部の特権化を白日の下に晒すものであった。
第三部は、従来、注目が少なかった娯楽や村落の託児活動といった部分にまで視野を広げ、人民の生活の多様な場面から権力の生活への浸透の状況を浮かび上がらせている。
本書は、都市と農村の両方に目配りしているが、より精彩を放っているのは農村社会を扱った部分だろう。張楽天の描く具体的な農村の性のあり方や、鄭浩瀾の農村の親密性の私的な性格についての考察が、印象深い。鄭によれば、農村の親密な関係は本質的には権力に依存する私的な人間関係であり、不安定で、親密でない他者の生に対する無関心を内包するものであった。毛沢東時代の親密性は、現代のわれわれの自立的な個人間の身体的かつ感情的な感覚を他者と共有する親密性とは異なって、他者との関わりは家族を中心とする既存の社会関係の中で営まれていたのであり、そうした関係は権力構造に強く依存し、公権力の行使の場に浸透していった。親密な関係を持たない「他者」への関心から生まれる公共性は、そこからは生まれえない、と。
そのように書かれると、近代上海における公共性の成立を論じたことのある評者は、いま一度、都市と農村とは違うのか、毛沢東時代は萌芽としての中国の公共性を窒息させたのか、を考えざるを得ない。
以上のような私人間の関係を研究する際に、本書が使用したのは、新聞雑誌などの公刊物や党・政府の文献だけでなく、日記・手紙や口述資料やインタビュー記録などの個人史料、また離婚裁判資料などである。こうした貴重な史料の多くは、本書の著者の一人である張楽天氏が主任を務める復旦大学当代中国社会生活資料センターに収集されたものであり、本書は慶應大学総合政策学部の鄭浩瀾氏と張氏ら中国の研究者との2021年に始まった国際共同研究プロジェクトの成果である。鄭氏のグループは、先に『毛沢東時代の政治運動と民衆の日常』(慶應義塾大学出版会、2021年)を刊行されているが、共同研究を継続し、コロナ下で苦労の多い中、興味深い成果をまとめられたことに敬意を表し、さらに研究を深められることを期待する。
(こはま・まさこ 日本大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
