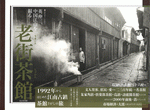呉覚農と中国茶業復興計画
「お茶といえば中国」「日本茶も元々は中国から伝来した」など、お茶の世界では中国は常に世界のトップランナーだったという認識が強いようだが、20世紀初めは中国茶受難の時代だったことをどれほどの人が認識しているだろうか。19世紀まで世界トップの生産量を誇っていた中国が、インド・スリランカに後れを取ったのが1900年頃であり、中国茶業は清朝滅亡などの混乱期に後退を続けていた。その危機的な状態の改善に努め、中華人民共和国建国後は重要閣僚にまで登った呉覚農について、簡単に書いてみたい。

上海 呉覚農記念館
先日8年ぶりに上海へ行き、そこに呉覚農記念館があること知り、知り合いの紹介で訪ねてみた。この記念館には呉の生涯について詳細な展示があり、そこには現代中国茶業の復興者として、また発展を支えた重要人物としての呉覚農が描かれていた。因みに上海のやや郊外にあるこの記念館を作ったのは急須の製造・収集家の個人だというのが何とも面白い。
呉覚農は1897年浙江省上虞県豊恵鎮で生まれた。17歳で浙江甲種農業専科学校(現浙江大学)に入学、1919年優秀な成績をもって日本へ公費留学を果たし、静岡の国立茶業試験場で茶業を学んだ(呉覚農が日本でどのような生活を送り、どのようなことを学んだかについては、残念ながら日本側に記録は残っていないらしい)。因みに国立茶業試験場は1918年に東京の西ヶ原より金谷に移転したばかりで、どの程度整っていたのかも分からない。
ただこの時期の本人の記述として「中国茶業の現状は暗澹としており、その最大の失敗は人材がいないことだ」と述べ、人材育成の必要性を痛感しており、また茶業改革の方策なども発表していることから、日本での研修で何らかの刺激を受けていたことは分かる。更には荒廃する農村、困窮する農民問題なども提起しており、当時の中国としては非常に高い意識を持っていたことが窺われる。
帰国後農学会の幹事として活動した他、開明的な書店開設に関与して魯迅や郭沫若らとの交流もあったというからただの茶業者の枠組みは越えていたかもしれない。一時茶業から離れたかに見えたが1931年上海の茶葉検査責任者に任じられ、翌年には安徽省祁門に中国初の茶業試験場を設立して場長となり、本格的に中国茶業の立て直しの旗振り役を担っていく。1934年には海外茶業視察で日本・台湾などを訪れ、茶工場、茶園、製茶機械などに注目し、その政策を参考としているのは実に興味深い。
.jpg)
呉覚農と胡浩川(呉覚農記念館展示)
1935年には胡浩川(祁門茶業試験場2代場長)と共著で「中国茶業復興計画」を発表。外国商会に牛耳られていた流通経路の改善を進め、個々の茶農家を纏めて合作社を作り、また機械化を進めて茶業の効率化を図り、世界からの遅れを何とか取り戻そうと奮闘する姿が見て取れる。更に戦時下でも人材育成に注力し、復旦大学(当時は重慶)に茶業専科を設け、多くの高級茶業人材を輩出し、中国茶葉研究所の所長を務めるなど、中国茶業への献身的な取り組みを行い、困難な状況下で多大な貢献をなしたとされている。

豊恵古鎮の街並み
呉は一体どんな生い立ちだったのかを知りたくて、先日呉覚農故居へ行ってみた。紹興東駅から車で1時間弱。かなりの田舎にやって来た印象だが、豊恵古鎮という老街が出来ており、予想外に雰囲気のある街並み、歴史的な橋などもあり、純粋に楽しめた。川沿いにある故居自体は閉まっており参観できないが、隣に記念館が建っており、そちらを見学した。

豊恵古鎮 呉覚農故居
この展示と周囲の様子から、なぜ呉覚農がこの街から出て全国的な指導者になったのか、その一端を垣間見たような気がした。特に茶業があるような地域には見えなかったが、この付近は100年以上前、紹興や杭州に繋がる川の物流でかなり栄えていたことが分かる。この豊かさが彼の教育をはぐくみ、この立地が茶葉に触れさせ、茶業に関心を寄せる源だったかと思わせる場所だった。
上海に戻る途中、杭州で中国茶葉博物館にも行ってみた。周辺には茶畑があり、その敷地は広く、龍井村にも近い。茶の歴史コーナーだけを丹念に見てみると、さすがに展示内容も多く、お茶の歴史も10数年前とはかなり状況が違っており、やはり新しい情報が反映されていた。最後に現代茶業に貢献した偉人たちがイラストで紹介されていたが、その中心にはやはり呉覚農がいた。これは単に地元だからではなく、ここは国家級博物館なので、国家が彼の功績を認めているということだろう。
.jpg)
中国現代茶業の偉人たち(一番大きなイラストが呉覚農)
戦後は中華人民共和国の建国時に農業部副部長、中国茶業公司社長など要職を歴任した呉だが、逆に茶業の現場からは離れていってしまい、文化大革命期には活動停止を余儀なくされ、不遇の時代を送る。改革開放期は「中国現代茶業の茶聖(レジェンド)」として称えられ、祭り上げられていたものの、何となく前半生の輝きはなかったかもしれない。ただ彼がいなければ現在の中国茶業の繁栄はなかったと言えるだろう。
▼今回のおすすめ本
1992年から2004年にかけて撮影された中国江南地方の茶館。息づく温もりと、静かに消えゆく日常をフィルムに刻み、江南の古鎮が紡ぐ時代の物語を丹念に描き出した写真家・英伸三の決定版。
――――――――――
須賀 努(すが つとむ)
1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。
blog[アジア茶縁の旅]