──東京と台北の映画祭から
吉川 龍生
2024年秋の映画祭シーズンは、中国語圏映画が充実していた。東京国際映画祭上映の中国語圏映画が前年比で激増し、存在感を増したことも大きい。東京・中国映画週間(10月22日〜29日)から始まり、東京国際映画祭(10月28日〜11月6日)、台北金馬影展(11月6日〜23日)、東京フィルメックス(11月23日〜12月1日)と、仕事の合間を縫って(時には台湾に飛び)劇場に通い、約1ヶ月間で辛うじて25作ほどを鑑賞した。しかし、何としても観たいと思っていた婁燁(ロウ・イエ)監督『未完成の映画(原題・一部未完成的電影)』は、台北でも日本でも予定が合わず鑑賞できなかった。他にも、金馬奨で最多の5部門を制した徐漢強(ジョン・スー)監督の『鬼才之道(原題)』も鑑賞機会に恵まれなかった。大きな話題になった作品は、他のレポートで取り上げられる機会も多いだろうという楽観的な推測をしつつ、本稿では自分自身がこれまで研究対象として注目してきた点や、文章として発表してきた内容を踏まえ、個人的な注目作について関連する事情にも言及しつつレポートしたい。
1.開心麻花のコメディ映画──東京・中国映画週間
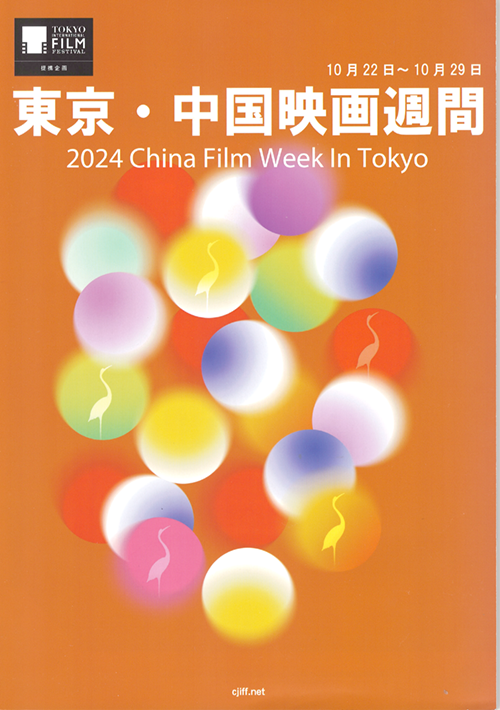
中国のコメディ映画(喜劇映画)は、個性派の女性俳優が主役を務める作品が出てきたり、やりすぎにならない程度の社会批判を取り込めていたりするところが興味深く、個人的に近年注目してきたジャンルであった(1)。特に、舞台でのコントを中心に実績を積み、映画製作にも進出してきたコメディ集団・開心麻花は、馬麗(マー・リー)というコメディエンヌを擁して何作もヒットをとばしていて、新作が気になっていた。
そのコメディの文脈で期待していた作品が、2024東京・中国映画週間で上映された開心麻花作品、閆非(イェン・フェイ)・彭大魔(ポン・ダーモー)監督『抓娃娃(じゅあわわ) 後継者養成計画(原題・抓娃娃)』で、ともに開心麻花所属の馬麗と沈騰(シェン・トン)のダブル主演である。実は大富豪の夫婦が、一人息子を甘やかさず貧しい環境で育てようと、何年にもわたって貧困家庭のふりをするという荒唐無稽な話だ。「そんなバカな」と思いつつも、主演二人の個性で笑いをとり、時にしんみりさせる抑揚が効いている。必然的に貧富の格差に焦点が当たるようなテーマで、社会批判の要素が増えた印象も残った。
いずれにしても、中国国内の興行成績は良く、2024年の夏休み時期ではトップ、年間でも3位というデータもある(2)。日本国内での上映もユニークで、9月初旬に、なんと日本語字幕無し(中国語音声/中国語字幕・英語字幕)で1週間限定上映があり、中国映画週間とほぼ同時期から日本語字幕版(映画週間のものとは別の字幕)での公開もされた。中国映画週間の観客も大半が在日中国人という印象だったが、日本語字幕の有無よりも話題性を優先して中国語が分かる人たちを呼びこもうというのは、中国国内で話題の作品をタイムリーに見て、日本に居ながらSNSを通じて盛り上がれるという意味でも、今後が楽しみな試みだと言えよう。本稿執筆時点で、春節(2025年1月29日)に中国国内で公開予定の烏爾善(ウーアールシャン)監督『封神:戦火西岐(原題・封神第二部:戦火西岐)』が、中国国内とほぼ同時のタイミングで日本公開されることが決まっており、それも日本語字幕無しの上映である。映画祭の話題からは外れるが、こうした興行形式が広まっていくのかも興味深いところだ。
2.陝西省のリアルな風景──東京国際映画祭
葉星宇(イエ・シンユー)監督『三匹の去勢された山羊(原題・三个羯子)』は、新型コロナウイルスの感染拡大の中、山羊(の肉)を仕入れるために実家に戻った男の顛末が、諷刺的なタッチで描かれている。上映が始まってまず驚いたのは、主演が恵王軍(フイ・ワンジュン)だったことだ。2023年第36回金鶏奨の最優秀児童映画に選ばれた白志強(バイ・ジーチアン)監督『撥浪鼓咚咚響(原題)』(2020年上海国際映画祭で上映/2023年一般劇場公開)という児童映画で主演していた俳優である。彼は『撥浪鼓咚咚響』で主演するまで運転手をしていて、演技の勉強はしたことがなかったと言われているが、特徴のある風貌で強烈な存在感を放っていて、記憶に刻み込まれるような印象が残っていた。
『三匹の去勢された山羊』は、ドローンを採り入れるなど撮影に工夫が見られ、その点も興味深かったのだが、何よりも陝西の乾いた大地に恵王軍がいるだけで、『撥浪鼓咚咚響』のシーンが脳内で同時上映されるような感覚にもなり、恵王軍の存在感たるや畏るべしと感じた。なお、上述の2作とも2000年代前半の中国インディペンデント映画のようなテイストもある。東京国際映画祭の会場で葉星宇監督に聞いたところでは、『撥浪鼓咚咚響』の白志強監督とは同郷で親しいということで、陝西省楡林出身の若き映画人たちが地元の風景や人物を巧みに利用し、記憶に残る秀作を作り上げていることに驚かされた。
出身地の甘粛省で映画制作を続け、口コミで大きなヒットにつながった『小さき麦の花(原題・隠入塵煙)』(2022年)を生みだした李睿珺(リー・ルイジュン)監督のように、葉星宇監督をはじめとした若き映画人たちも、地元・陝西の寒村を撮り続け、より大きな話題となるような作品を生み出す時が来るのでは、との期待も高まる。


3.移行期正義をめぐる議論──台北金馬影展
上映後のQ&Aも含めて、台北で一番印象に残ったのは、鍾孟宏(チョン・モンホン)監督『餘燼(原題)』だった。厳密に言うと金馬影展の上映ではなく、ちょうど一般劇場公開中の上映に、金馬影展に合わせて監督と出演者が登壇するイベントがあり、それに参加することができた。この形式の上映イベントは、『小雁與吳愛麗(原題)』が公開中だった林書宇(トム・リン)監督も盛んに行っていた。
『餘燼』の鑑賞に当たっては、否定的な感想を持つ人がかなり多いという事前情報をもって鑑賞することになった。連続して起こる殺人事件の背後に、台湾現代史の記憶が絡みつき、北米でのシーンも重要な意味を持つなど、なかなかスケールの大きな作品で、豪華キャストやスリリングな展開、迫力のあるアクションシーンもあり、2時間40分を超える長尺を感じさせない内容である。娯楽大作映画として完成度の高い本作が批判にさらされたのは、端的に言って、白色テロの時代の加害者を美しく描きすぎなのではないかと感じた観客が多かったからだ。実際、Q&Aで最初に出た質問が、まさにそれに関するものだった。
日本の上映後の舞台挨拶などでは考えられないほど厳しい質問が飛び交ったが、登壇した監督や主要キャストの莫子儀(モー・ズーイー)は非常に良く歴史を勉強していて、丁寧に受け答えしているのが印象的だった。こうした議論のかみ合ったQ&Aができれば、監督としては既に思惑どおりといったところだろう。
4.弱者・マイノリティーへの眼差し──東京フィルメックス
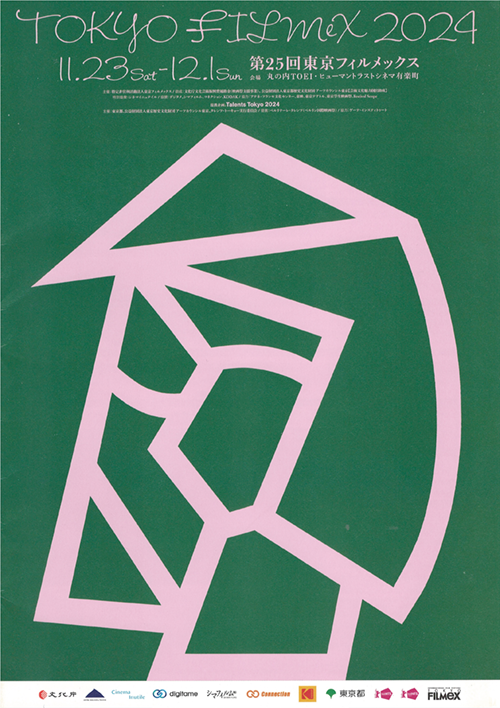
2024年秋の映画祭シーズンの個人的な締めくくりは、東京フィルメックスでの曾威量(チャン・ウェイリャン)監督・尹又巧(イン・ヨウチャオ)共同監督『白衣蒼狗(原題同じ)』だった。移民労働者・老人・障害者といった弱者・マイノリティーの残酷でグロテスクなまでの環境を緊張感のある映像で表象することに成功している。これが初長編監督作品という点には、多くの観客が驚かされたことだろう。
この作品が2024年秋の映画祭シーズンの締めくくりになったのは象徴的な気もした。『白衣蒼狗』は台湾を舞台にした作品(監督はシンガポール出身)だが、社会的弱者やマイノリティーに目を向けた作品として、中国(大陸)や香港の作品もあり、いずれも印象的な作品だったからだ。東京国際映画祭では、中国に暮らす脳性麻痺の若者の恋や成長を人気俳優・易烊千璽(イー・ヤンチェンシー)主演で描いた楊荔鈉(ヤン・リーナー)監督『小さな私(原題・小小的我)』があった。さらに、台北金馬影展では、香港を舞台に熟年女性同性愛カップルの死別と法制度の理不尽の現実的な問題を描きだした楊曜愷(レイ・ヨン)監督『從今以後(原題)』が深く記憶に残った。
対象や描き方はまさに三者三様だが、弱者やマイノリティーの人々が抱える問題を見つめていこうという問題意識のようなものは共通しているように思う。中国語圏映画を見わたしたときに、こうした作品が近年増えてきている印象は持っていたが、優れた作品がこれだけ揃い地域的な広がりもあったというのは特記に値する。世界的に不寛容な政治権力も目立ちつつあるこの時期に、こうした傾向が続いていくのかも、興味深い点であると思う。
【注】
(1)中国のコメディ映画については筆者の前稿「中国語圏映画雑感──第19回大阪アジアン映画祭と両岸三地の近作から」でも言及した。また、『東亜』(霞山会)掲載の拙稿「電影中国」2024年6月号と9月号では、喜劇(コメディ)映画について、映画史的な考察も含めて論じた。
(2)「猫眼」など[最終確認:2025年1月23日]。
(よしかわ・たつお 慶應義塾大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
