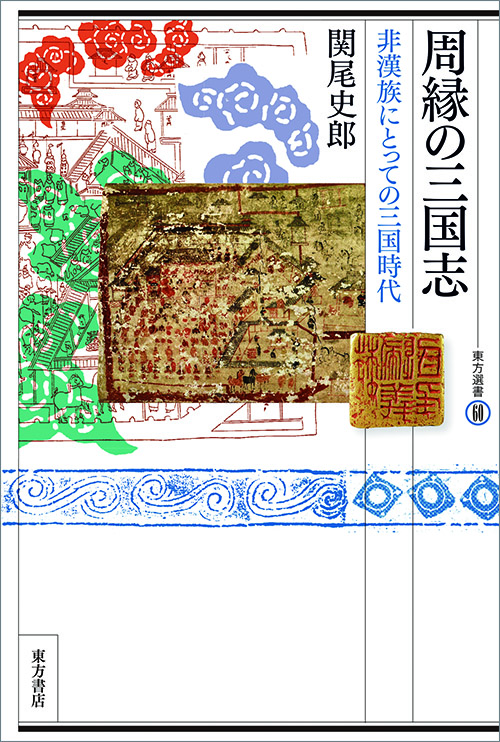
|
「東アジア世界」のなかの三国志
「三国志」の人気は根強い。ごく最近も、諸葛亮を題材とした『パリピ孔明』(四葉夕卜原作、小川亮作画)なる作品が反響を呼んでいると聞く。二世紀末から三世紀にかけて、分裂し混迷する中国社会のなかで、生存をかけて苦闘した人物たちの姿は、現代においてもなおそれに触れる者の心を捉えるところがあるのだろう。
しかし、その時期に躍動したのは漢人の英雄たちだけではない。日本では「魏志倭人伝」の名で知られる部分を含む陳寿『三国志』巻30には、倭のほかにも烏桓(烏丸とも)、鮮卑、扶余、高句麗などの非漢族集団が記録される。さらに『三国志』全体、あるいはそれ以外の三国時代史料にも視野を広げていくと、魏・蜀・呉三国と接点を有した非漢族集団やそれらに出自を持つ人物は実のところ少なからず見いだされる。
本書『周縁の三国志――非漢族にとっての三国時代』は、そうした様々な非漢族に焦点を当てて三国時代史を捉えなおそうとするものである。著者の関尾史郎氏(以下、著者)は2019年にも東方選書シリーズの一冊として『三国志の考古学――出土資料からみた三国志と三国時代』を上梓し、文献史料とは異なった角度からの三国時代史像を提示している。両書はいずれも著者が長年取り組む非漢族史研究、敦煌・トルファン学、出土文字資料研究あるいは図像分析などの成果に裏打ちされ、また「三国志」の時代を多角的に理解するというコンセプトも共通する。『三国志の考古学』を未読の方には、ぜひ本書と併せ読むことをお勧めしたい。
以下、本書『周縁の三国志』の内容を簡単に紹介するとともに、その特徴について述べていく。なお、詳細な目次は東方書店ウェブサイト(上記)で閲覧可能である。
まず序章「『東アジア世界』と三国時代」では、かつて西嶋定生氏が提起した「東アジア世界」論(後述)を踏まえて本書の目的が示される。すなわち、三世紀における中国は「秦の始皇帝が中国世界を統一して以来、初めて訪れた政治的な分裂」という状況にあった。諸王朝は引き裂かれた世界の再統合を目指して抗争し、そのなかで周縁部に存在する非漢族諸勢力との関係を重視した。このことの影響を非漢族の側から捉えなおすことが本書の目的である、とする。
続く全四章の本論は、おおむね節ごとに主要な非漢族勢力を一つ取り上げて順次検討を加える形をとる。
第一章「三国鼎立と非漢族」では、中国北部・北東部に居住した烏桓、南東部に居住した山越を扱う。いずれも後漢時代には郡県制が敷かれた領域の内部に居住するようになっていた非漢族である。それゆえに二世紀末以降、中国世界の混乱と分裂によってまっさきに深刻な影響を被ったことが跡付けられる。このうち山越については、著者自身による複数の実証論文に基づいて、本書のなかでもとくに明快な解説が展開される。
第二章「鮮卑と高句麗」は、中国北部・北東部に居住した鮮卑、中国北東部及び朝鮮(韓)半島の一部を勢力圏とした高句麗に焦点を当てる。烏桓が早期に打撃を受けたのち、華北一帯を統治した魏は鮮卑・高句麗の両者と直接対峙した。また、魏と抗争する蜀や呉も、戦略上これらとの接触を図った。さらに、のちの時代を視野に入れると、高句麗は四世紀に楽浪方面まで勢力を広げ、鮮卑拓跋部は五世紀に華北を統一する(北魏)など、いずれも三国時代以降に存在感を強めていく。このことも展望しつつ、三世紀における鮮卑の大人軻比能や公孫氏政権、毌丘倹の高句麗「征討」などの事項を軸に諸勢力の関係を活写する。
第三章「諸葛亮の『隆中対』」は、諸葛亮が劉備と初めて対面した際に語ったとされる「隆中対」(『三国志』巻35諸葛亮伝所収)の精査から出発する。文中の「諸戎」「夷越」について、それぞれ涼州(中国北西部)の氐など西戎、交州(ベトナム北部)の越族に比定し、まず交州の状況を整理する。続けて、氐と魏・蜀との関わり、西南夷(中国南西部、四川以南)と蜀・呉(交州を介して西南夷の居住地に接する)との関わりについて、蜀の北伐・南征とそれに対する魏・呉両王朝の動きに注目しつつ検討する。
第四章「クシャン朝と倭」では、中国世界から地理的にやや離れるクシャン朝(大月氏。アフガニスタン・北インドの一部)及び倭(日本列島)が主題となる。魏が倭の卑弥呼を「親魏倭王」に封じたことはよく知られるが、クシャン朝の王・波調も「親魏大月氏王」に冊封されている。重厚な研究史を整理・批評しながら、クシャン朝と倭とを併せて論ずることによって魏の政策意図を分析する。親魏大月氏王冊封と親魏倭王冊封とは個別の情勢によるとの見通しを示したうえで、なお検討を要する課題を指摘する。著者自身が「おわりに」に記す通り、非漢族側の実情に関する記述は他の章と比較して簡素であるが、本稿後段に述べるように本書全体の問題意識と密接に関わる一章でもある。
終章「非漢族にとっての三国時代」では、本論各章に述べられた諸勢力の動きが「東アジア世界」の形成という文脈に位置づくという結論が示される。西嶋定生氏以来の「東アジア世界」論を踏まえながら、本書の議論はそれらを異なる角度から見直し、また一層具体的に事象を解析するものであって、これにより、「三国志」の時代に中国世界・周縁諸勢力双方の情勢が連動したことが明らかになる、とする。
以上のように首尾一貫して「東アジア世界」論という問題意識に貫かれていることは本書の特徴の一つといえる。西嶋定生氏により唱えられた「東アジア世界」論とは、中国世界を一国史的に捉えるのではなく、その周縁部・外部も含めて歴史事象の連関を理解しようとする歴史世界論であった。近年、こうした方向の議論としては、中国世界と内陸アジアとの連関を重視する「東部ユーラシア(または東ユーラシア)」論も勢いを持つ。一方、西嶋氏の「東アジア世界」論は日本の歴史を世界史的に理解しようとする問題意識を帯びるものでもあった(西嶋定生『中国史を学ぶということ――わたくしと古代史』(吉川弘文館、一九九五年)など参照)。現在においても、日本社会に軸足を置いて研究活動を展開する以上、広域的歴史世界を論ずるうえで日本の存在を重視する、あるいは日本史領域との協力を重視するという立場から、引き続き「東アジア世界」の枠組みを用いる論者は少なくない。本書における「東アジア世界」への問題意識もこうした動向のなかに位置づけられよう。また、そのように考えればこそ、中国世界から地理的にやや離れた勢力を扱う第四章の意義及び本論各章の体系性が明瞭となるだろう。
本書の特徴としてはもう一つ、詳細な史料引用を挙げることができる。例えば、第三章での「隆中対」の精読をはじめ、袁紹が偽作した版文(第一章第一節)、周魴(後出の周処の父)の提案(第一章第二節)、呉と高句麗の接触過程(第二章第二節)など、やや長い引用を敢えて掲げ、文脈をくみ取りながら注意深く議論を進める部分が随所にみられる。また石刻(第二章第二節の毌丘倹紀功残碑、第三章第三節の姚立買石門券ほか)や断片的な文献(第一章第二節の周処『陽羨風土記』、沈瑩『臨海水土志』ほか。なお、本書四〇頁などで『臨海水土志』の撰者を「沈塋」とするのは誤記か)など、陳寿『三国志』を補完する史料も豊富に盛り込まれている。さらに、そうした史料の解釈や事実関係の復元については、先行研究を丁寧に挙げながら議論がなされる。本書に関連する時代・テーマを学び、あるいは研究しようとする読者にとっての参照価値はきわめて高い。
もっとも本書には、このように高い専門性を持つことのいわば副作用であるが、読者に対する要求がやや高いように思われる面もある。本書が扱う主題及び史料の性格上、学説史・概念の整理や史料批判及び文脈理解に関する記述が不可欠であることはもちろん評者も深く同意するところである。とはいえ、例えば冒頭に挙げたような「三国志」コンテンツをきっかけとして本書に関心を持った読者は、学術研究の文脈を前提とした硬派な記述に戸惑いを覚えるかもしれない。また、三国を取り巻いた非漢族諸集団の全体像やそれらの生活・社会習慣について、概説的あるいは民族誌的解説を期待して本書を手に取った読者にも、学説史と史料分析をベースとする行論が難解に受け止められることはありえよう。そのような向きには、図版を多数掲示する著者の前作(先述)、あるいは本書凡例所掲の『三国志』日本語訳などを参照し、記述対象をイメージしつつ読み進めるのも一法かもしれない。
また、学説史の重視とは表裏の関係であろうが、本書の構成においては地理的系統性が必ずしも強固ではない憾みがある。例えば、中国東北部から朝鮮半島(公孫氏政権、烏桓・鮮卑・高句麗・扶余・韓など)に関する記述は第一章第一節・第二章・第四章第二節に分散しており、順に読み進めていった場合、地域史・民族史の全体像を把握するにはやや労力を要する。関心の置きどころによっては、通読よりも章節単位で順番を入れ替えた読み方が適するかもしれない。
もちろん、以上に記したことが本書の瑕疵であるというのではない。根強い人気を持つ「三国志」を題材としながら、高度な内容を盛り込んだ本書であればこそ、著者の意図が少しでも多くの読者に齟齬なく理解されるべく、いささかの留意点を挙げたものとして諒解いただきたい。
繰り返すが、本書の目的は、非漢族に焦点を当てた分析を通じて「東アジア世界」における三国時代史像を描き出すことにある。その先には、「三国志」をたんに外国の英雄物語として受容するだけでなく、「東アジア世界」という枠組みのなかで日本列島の歴史と関連付けて理解することが展望される。このような意義を持つ本書が多くの読者を得ることを願って擱筆する。
(にいつ・けんいちろう 信州大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
