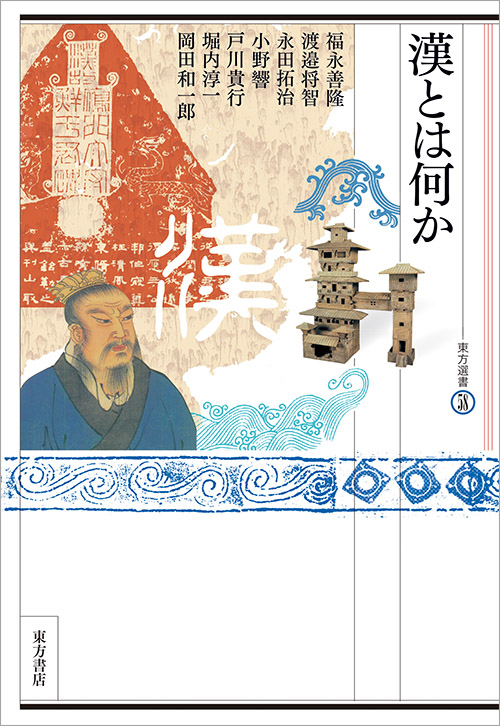
|
「漢」の規範化と相対化
『漢とは何か』という書名が東方書店のSNSで初公開されたとき、半ばネタだとは思うが、『漢とは何か』と勘違いする人が続出した。しかし、本書は、目次をみれば分かる通り、三国から唐代までの「漢」王朝像を検討し、どのように認識されていたのかを論じた概説書である。すなわち、『漢とは何か』ではなく、『漢とは何か』である。
小ネタはさておき、一王朝名にすぎなかったはずの「漢」が、漢字や漢族のように文字や民族、はては「おとこ」の意にも用いられるようになったのは、確かに不思議と言えば不思議である。本書は、そうした「漢」概念の拡張と東アジアへの拡散を議論する基礎を固めるため、各時代の「漢」王朝認識を掘り下げ、その規範化過程の解明を図ったチャレンジ精神あふれる書物である。
以下、各章の内容を要約した後、若干のコメントを付したい。
第一章「集団から帝国へ――前漢」(福永善隆)では、「漢」の出発点である前漢に焦点をあて、支配者層・官僚機構の変遷を人材登用制度(郎官・察挙)から読み解く。コラム「劉邦の伝承とその影響」では、前漢の初代皇帝劉邦の伝承と五行説の関係およびその変遷を簡潔にまとめている。
第二章「懐旧と称揚の狭間――後漢」(渡邉将智)は、後漢初期は前漢の制度のみが「漢」制ととらえられていたが、後漢中期には後漢の制度も「漢」制とみなされるようになったことを指摘する。コラム「孫呉から見た「漢」制」は、呉の丁孚撰『漢儀』は、「漢」制を呉の制度の淵源として位置付け、呉の正統性の補強を図ったとする。後漢(特に末期)と呉の税制の連続性を指摘した柿沼陽平氏の研究(1)とリンクする内容である。
第一章・第二章は、各王朝の「漢」認識を検討する前段階として、前漢・後漢における「漢」王朝像について、最新の研究を踏まえて論じている。その際、儀礼・対外関係・文化などではなく、制度(主に官制)に焦点をあてたのは、執筆者の専門領域であるという理由のほかに、各王朝の「漢」認識を論ずる際に、制度が一つの鍵になるという意識があったのであろう。
続く第三章「「漢」を継ぐもの――三国西晋における「漢」」(永田拓治)では、三国・西晋における歴史叙述を論ずる。西晋の陳寿撰『三国志』において、漢魏禅譲の叙述が簡素であったのは、禅譲を支える讖緯思想を摘むためだった可能性を指摘する。また、尊晋のための尊漢という叙述姿勢が後の「漢」的意識の源流とする。コラム「「漢」的時間の継承――時の支配」は、夏暦(立春が一月となる陰暦)を正朔とする「漢」の時間軸が各王朝に踏襲されたことを指摘。
第四章「「漢」との距離感――五胡十六国」(小野響)は、五胡諸政権の「漢」との距離感の違いに着目する。「漢」とのつながりを前面に出して漢を建国した劉淵(匈奴)、単に漢を国号としたにすぎない李寿(巴族)、匈奴を強調して敢えて漢を名のらなかった前趙の劉曜・夏の赫連勃勃。そして夷狄が中華の君主として臨むために、「漢」制だけでなく、西周の制度をまとめたとされる『周礼』や魏晋の制度を参照したことを論じ、「漢」が多様な淵源の一つとして規範となりつつも相対化されたと述べる。コラム「蜀漢という漢――劉淵と劉曜から見た漢帝国」は、「漢」皇帝への諡号に注目し、匈奴劉氏による漢から趙への国号変更が王朝存立の根幹にかかわる改革だったことを指摘。
第五章「漢から周へ――東晋南朝」(戸川貴行)では、礼楽(特に雅楽)に焦点をあて、漢魏と南朝の間の断絶と伝統の創造について論じ、さらに斉・梁にかけて正統性の根拠が『周礼』に求められるようになったとする。そして、その背景に『周礼』を参照した北魏の孝文帝改革への対抗意識があったことを指摘する。このことは、南朝・北朝双方で「漢」の相対化が進んでいたことを意味している。コラム「天下の中心の測り方」は、首都建康の日影の長さをめぐる南朝の試行錯誤を描く。
第六章「儀表としての漢――北魏の領域と漢の領域」(堀内淳一)は、北魏と南朝の封爵制度に注目し、皇子の封地の分布を比較し、北魏前期の独自性として領土外(かつ漢代の辺境の郡)に封爵(すなわち虚封)を与える事例があることを指摘する。そして、北魏は中華皇帝としての正統性を主張するために、「漢」の領域すべてを支配しているかのように振る舞おうとしたが、徐々に虚封に基づく正統性アピールの必要性が減り、遠方への冊封が減少したとする。これを読んで評者は、北魏初の道武帝が国号を魏(「漢」から正統性を継いだ王朝名)にしたことや、「子貴母死」(後継者を決めた後にその生母を殺害すること)を実行する際に前漢武帝の事例を踏まえたことを想起した。北魏前期には、封爵以外にも「漢」の制度や故事が意識されていたのは間違いない。コラム「北魏と南朝の元号」では、南朝では漢と同じ元号がたびたび使われる一方で、北魏では魏晋と同じ年号を使うケースがあることを指摘する。
第四章から第六章では、遊牧・牧畜民が華北を支配し、遊牧世界と中華世界が対立から融合に向かう過程で様々な模索がなされた五胡北朝・東晋南朝における「漢」認識が語られている。第五章では南朝において礼楽の正統性の根拠が「漢」から周に移行したと指摘されていたが、第六章のコラムを読めば南朝でも「漢」が無視されていたわけではないことがわかる。また、第六章では封爵の面で「漢」が意識されていたとしていたが、元号の点では魏晋の影響が強かったことになる。また、本書では言及されていないが、北魏の孝文帝改革の際には、「漢」だけでなく『周礼』・魏晋・南朝の制度が参照されている(さらに遊牧民由来の要素も融合している)。五胡北朝・東晋南朝における正統性や制度の淵源は、「漢」だけでなく、実に多様で複雑だったのである。
最終章にあたる第七章「漢王朝へのまなざし――唐王朝における先行王朝と故事」(岡田和一郎)では、二王三恪(先行する諸王朝の皇帝の末裔に封土を与えること)・王朝の徳運(王朝に五行をあてはめること)・「漢」の故事などに注目し、唐代にも「漢」が重視されたとする。ただ、本章でも述べられているように、二王三恪や徳運の点で唐が「漢」の継承を図ったのは、武周期(689~705)と玄宗の一時期(750~753)に限られている。確かに唐代には複数の正統観が存在していたが、唐朝は基本的に北魏(および西魏)―北周―隋―唐という正統観を維持しており、正統性の面で「漢」を意識したのは特殊事例といえる。また、『漢書』が好まれていたことも事実だが、「漢」の故事が制度整備に直接参照された事例は少ない。こうした点から、やはり南北朝時代と同様、隋・唐代にも「漢」の相対化は進んでおり、時折、「漢」が規範として表出することもあった、とみたほうがよいのではないだろうか。コラム「内から見た「漢」、外から見た「漢」」は、唐代と日本における「漢」の用例を簡潔に紹介し、漢王朝の意味ではなく、中国の歴代王朝や統治空間、そこに居住する人々の意として用いられたことを指摘する。
本書は、執筆者の専門を活かしつつ、各王朝の「漢」認識を検討した概説書である。各章とも最新の研究を踏まえており、読み応えのある内容となっている。ただし、第一章・第二章で論じられた「漢」の制度が魏晋南北朝の制度とどのような関係にあるのか、各章であまり触れられておらず、全体の統一感は希薄になってしまった印象を受ける。分担執筆という性質上やむを得なかったとは思うが、総論のようなものがあってもよかったかもしれない。
その一方で、官制・歴史叙述・礼楽・封爵・暦・日影・元号など様々な角度から時代ごとに「漢」認識を検討したことで、各王朝と「漢」の一筋縄ではいかない関係が浮かび上がってきたことも事実である。「漢」が後世の各王朝の規範となったことは、渡辺信一郎氏が「古典国制」(儒教的理念に支えられた「漢」制)の概念を用いて議論している(2)。確かに儀礼・制度を大枠でとらえると、そのように理解することもできる。しかし、「古典国制」の概念を過度に強調すると、魏晋南北朝時代に多様な淵源が混ざり合った結果、新たな制度・社会・文化が形成されて、隋・唐に至ったことが等閑視されることにもつながりかねない。この時代を把握する際には、「漢」の規範化と相対化の双方を意識する必要があるのだ。その意味では、大枠を始めに定めて議論するのではなく、敢えて多方面から各王朝と「漢」の関係を論じた点に本書の意義があるといえよう。
本書を通読すると、西晋崩壊から南北朝時代にかけて、「漢」が規範化されるとともに相対化されたことが窺える。しかし、その一方で、コラム「内から見た「漢」、外から見た「漢」」でも触れられていた通り、既に南北朝時代には、漢王朝や漢代の人々の意味ではなく、同時代の王朝や中国土着の人々を「漢」・「漢人」と呼ぶ事例や、「胡漢」のように遊牧民や西方の人々・言語と中国の人々・言語を対比させる事例が存在していた(3)。すなわち、王朝の正統性や制度面で「漢」の相対化が進む一方、社会では中国土着の人々を「漢」と呼ぶ習慣が徐々に広まりつつあったのである。その背景に遊牧世界と中華世界の対立・融合や、各王朝における「漢」の規範化があったことは間違いない。また、上記と同様の「漢」や「胡漢」の用法は、仏典にも見える(4)ことから、仏教の影響もあったかもしれない。欲を言えば、本書でもこうした「漢」概念の拡張と定着について、もう少し掘り下げてほしかったところであるが、これは執筆者のみならず、評者も含めた読者全般に投げかけられた課題とみたほうがよいかもしれない。
本書は、「漢」概念の拡張や拡散を議論する第一歩として編まれた概説書であり、「漢」概念の研究がこれで完成したというわけではない。今後は本書を踏まえた上で、思想・宗教・美術・文学・ジェンダーなども含め、より多様な角度から「漢」概念に対する検討が求められよう。本書の影響を受けて、更にわくわくするような研究が出てくることを期待したい。
【注】
(1)柿沼陽平「孫呉貨幣経済の構造と特質」(『中国古代貨幣経済の持続と転換』汲古書院、2018年)。
(2)概説書に渡辺信一郎『シリーズ中国の歴史① 中華の成立 唐代まで』(岩波新書、2019年)がある。
(3)例えば南朝の梁で編纂された『南斉書』巻47王融伝や巻57魏虜伝では、北魏領内に居住する中国土着の人々(秦漢以来中国に居住している農耕民=いわゆる漢人)について「漢人」と呼んでいる。巻59芮芮虜伝でも柔然と中国の言葉に通じた人物について、「通胡漢語」と表記している。また、唐初編纂の『北斉書』には、会話文の中でいわゆる漢人を「漢児」と呼ぶ事例が散見される。事実を踏まえているとすれば、東魏・北斉では「漢児」という用語が普及していたことになる。
(4)例えば梁代に編纂された『出三蔵記集』には「胡漢」の語が散見される。
(あいだ・だいすけ 明治大学等兼任講師)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
