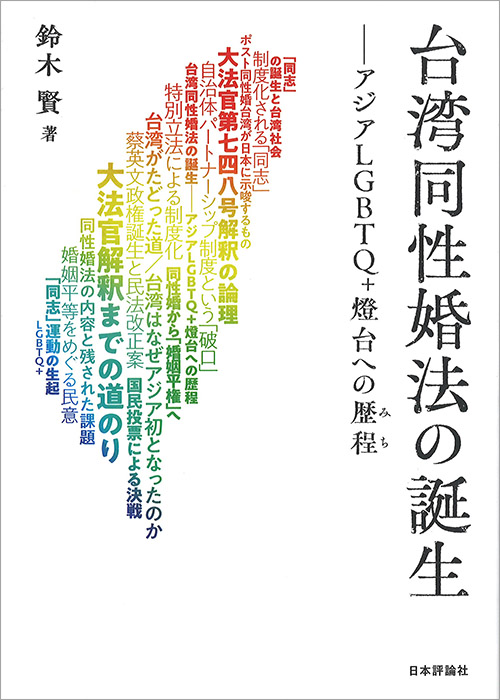
|
2019年5月17日、台湾の国会に当たる立法院。同性婚を法制化する特別法が審議され、その周囲を、大勢の支持者たちが取り囲んでいた。法案が可決されたその瞬間、大きな歓声が沸き起こった。早朝から降り続いた雨はいつの間にか止み、青空に七色の虹が美しいアーチを描いていた。あたかも台湾の前途を祝うかのように。
しかし、そこに至る道程は苦難の連続だった。
私は2017年から2021年まで、毎日新聞の特派員として台北に駐在していた。同性婚法の誕生については、その歴史や経緯も含め、現地で多くの当事者から話を聞いた。とりわけ、1980年代にたった一人で婚姻の平等な権利を求める運動を始めたレジェンド・祁家威さんについては、何度も時間をいただいて取材し、長文の記事も書いた。本書の筆者、鈴木賢さんにも節目で教えを請うていた。それでも「なぜ台湾がアジアで初めて同性婚を実現できたのか」という点を私自身がきちんと理解できていたのか、自問自答することは一度や二度ではなかった。
本書は、そんな私のモヤモヤを氷解させてくれた。法律の豊富な専門知識に加え、長年にわたり現地の運動家や団体と伴走してきた鈴木さんだからこそ、世に送り出すことができた書籍だ。それは法、歴史、社会、文化、政治など、あらゆる要素を網羅した上で、同性婚法の誕生に向けて台湾が歩んできた道程を分かりやすく読者に追体験させてくれる。
それだけではない。台湾社会が育んできた市民社会のパワーを存分に感じ取ることができ、読む者をわくわくさせてくれるのだ。日本社会の閉塞感をいかにして打破すればいいのか、そのヒントをも読者に与えてくれる。
本書には、日本でも著名となった台湾のデジタル担当相、オードリー・タン(唐鳳)さんが「より多様で、オープンなライフスタイルを求める台湾の姿」を描いたと推薦文を寄せた。タンさんの活躍ぶりは、多様性に富んだ包摂的な社会の実現を目指す台湾を象徴している。
だが同性婚というイシューについては必ずしもそうではなかった。台湾社会には儒教倫理や家父長制が隅々まで根付いており、同性愛は長年にわたり忌避されていたのだ。
では、何が台湾社会を変えたのか。鈴木さんはまず「同志」「性別」「婚姻平権」という三つのキーワードを挙げる。いずれも奥深い概念であり、簡単には説明できない。ここでは「同志」の概念について触れる。詳しくは、ぜひ本書を読んでほしい。
「革命はいまだ成功せず、同志よ、すべからく努力すべし」。これは孫文(1866~1925)が遺訓として残した言葉だ。孫文が率いた中国国民党や、中国共産党で、仲間を互いに呼び合う際に使われた。鈴木さんによると、この「同志」が1992年にまず香港で同性愛者を意味するようになり、台湾にも広がったという。
台湾では同性愛を意味する言葉として「同性恋」が長く使われていた。だが極めてマイナスイメージの強い単語だった。それまでは、同性愛について社会で語ることさえ憚られる空気があり、同性愛者は「存在しないもの」として扱われがちだった。だが「同志」という、中華圏で人口に膾炙した表現が、同性愛について公共の場で議論するハードルを引き下げたのだ。「同志」はやがて、LGBTQ+を含む幅広い概念を包摂するパワーワードとなっていく。
台湾では、蔣介石(1887~1975)の中国国民党が戦後、独裁統治を続け、戒厳令を敷いた。このため市民運動が花開くのは戒厳令が解除された1980年代後半以降である。女性、労働者、身体障害者、原住民(先住民) など、権利の獲得を目指す多くの運動が起きた。同志による運動は、女性運動から派生する形で展開した。鈴木さんは、運動史を丁寧にひもとき、政治を動かすイシューとなった経緯を「血みどろの闘争」と書く。その過程では、多くの命も失われた。
最初に立法院で同性婚に関する法案を提出したのは2006年、民進党の蕭美琴議員だ。2016年に総統に就任した蔡英文氏の側近であり、現在は台北駐米経済文化代表処(ワシントン)でトップ(駐米大使に相当)を務める。2012年にも民進党の尤美女議員らが中心となって法案を提出した。だが当時は、同性婚に消極的な議員が多い国民党が議会で多数を占め、いずれも廃案となった。
蔡氏は2016年の総統選で、婚姻の平等な権利を支持すると公約して当選し、立法院でも民進党が初めて過半数の議席を獲得した。同性婚を実現する環境が整ったかに思えたが、実際にはそうではなかった。蔡氏が率いる民進党にも法案に反対や慎重姿勢を示す議員が少なくなかったからだ。2016年には計4本の関連法案が議員によって提案されたが、最終的に成立には至らなかった。同性婚への反発が根強い中南部の選挙区から選出される議員らは、有権者からの圧力に抗しきれなかったのだ。
日本から見ていると、台湾の有権者は過半数が同性婚を支持していたように感じるかもしれない。しかし実際はそうではなかった。世論調査でも、反対が賛成を上回ることも多かった。
この状況を打破したのは、憲法裁判所に当たる大法官(15人の裁判官で構成)が2017年5月に示した司法判断だった。大法官は、同性婚を認めない台湾民法の規定が、人民の婚姻の自由と平等権を保障した憲法の規定に反すると断じた。その上で、2年以内に民法改正または関連法の制定によって婚姻の平等な権利を実現するよう立法府に命じた。法制定が間に合わない場合でも、行政機関は同性カップルによる婚姻の届け出を受け付けねばならないとした。
これは、三権分立がいかにあるべきか、というテーマと深く関係する。つまり、民主主義における多数の意見と、憲法が保障するマイノリティの権利が衝突した時に、これをどう扱うべきか、という問題である。悩み抜いた司法が根拠としたのは、長年にわたる草の根の運動であり、立法府において法案が棚ざらしにされたことだった。鈴木さんは「憲法によって保障される自由や権利が、多数派からコンセンサスを得られるまで待ってはじめて認められるわけではない。台湾の司法は人権擁護の最後の砦としての役割を果たした」と訴える。この問いかけは、日本の司法界に重く、深く響く。
鈴木さんは、台湾が国際社会の中で置かれた環境が同性婚の実現を促進した点についても、分析を加えている。台湾は、中国の圧力によって多くの国際機関から排除され、国交を維持する国はわずか14カ国。同性婚の法制化を実現することで、国内で人権侵害を続ける中国と対照的に、アジアにおける「人権の灯台としての台湾」の姿を示すことができた、というわけだ。実際に蔡総統は、同性婚法が成立した日にフェイスブックで「これこそが私たちの台湾、民主主義、自由、平等です」とアピールしている。こうした特殊な政治的側面が、同性婚実現を促したことは否定できないだろう。ただ、だからといって「台湾は特殊だから」と思考停止に陥るようでは、道は開けない。
この点で、本書が同性婚の実現後、台湾で何が起きたか(あるいは何が起きなかった)について詳しくリポートした第12章は、私たち日本人にとっても、極めて示唆に富む。というのも、台湾では保守層が「伝統的な家族観が崩壊する」などと主張し、激しい反対運動を展開したからである。2021年末までの約2年7カ月で、台湾では7182組の同性カップルが誕生した。だが、異性愛の家族がそれによって崩壊したという話は寡聞にして聞かない。世論調査では、同性婚への賛成が6割を超えるに至った。多くの市民は、同性カップルがいる社会に「慣れた」のである。反対派の叫びは杞憂に過ぎなかった。
日本でも保守層を中心に多くの政治家が「伝統的な家族の形が崩壊する」「家族のあり方の根幹に関わる」などとして、同性婚の法制化に慎重な姿勢を見せている。台湾と深い交流を続ける国会議員にも、同性婚の話となると慎重な議員が少なくない。こうした議員にこそ、この書籍を読んでほしい。そして台湾政府の人や、蔡総統と意見交換をする機会に、台湾の経験について質問してほしい。きっと、認識が変わる契機になると思う。
政治家はしばしば「国民の理解が十分でない」「様々な意見がある」などと述べて、議論を先送りにしている。しかし、多くの世論調査では同性婚を「認めるべきだ」と回答する人が多数派を占めている。例えば毎日新聞社と埼玉大社会調査研究センターが2021年11月~2022年1月に実施した世論調査で、「認めるべきだ」が46%、「認める必要はない」は16%だった。この傾向は若い世代に顕著で「認めるべきだ」と答えた割合は18~29歳で71%、30代が65%、40代も57%に達した。
だが、そもそも「国民の理解が進んでいない」ことが理由になるのだろうか。特定非営利活動法人「東京レインボープライド」共同理事の杉山文野さんによると、都道府県として初めて性的少数者のカップルを公認する「パートナーシップ制度」を導入した茨城県の大井川和彦知事はこう述べたという。「理解が無いからこそ、政治が実行し、それによって理解が追いついてくる。それこそが政治の役割だ」。まさにこれは、同性婚への反対が根強かった台湾で、蔡総統が実行したことに重なる。
鈴木さんは、司法の役割を述べる文脈で「憲法によって保障される自由や権利が、多数派からコンセンサスを得られるまで待ってはじめて認められるわけではない」と書いた。これは政治家にも当てはまる。性的少数者に婚姻の平等な権利が保障されていないことは、深刻な人権侵害である。その解消に取り組まないことについて民意を理由にするのは、政治の責任を放棄するに等しいのではないだろうか。
本書に推薦文を寄せたオードリー・タンさんは新型コロナウイルスの感染が広がり始めた頃、どの薬局に行けばマスクが手に入るのかが分かるマスクマップのシステム作りを主導し、トランスジェンダーという経歴もあいまって、日本でも広く知られるようになった。当時は多くの日本人が、パソコンもまともに使えない高齢のデジタル大臣を引き合いにこう嘆いた。「日本にもオードリーさんのような優秀な大臣がいたら」
だが、この嘆きはポイントが少しずれているように思う。オードリーさんのような人材が日本にいたとして、果たしてその能力をいかんなく発揮できただろうか。こうした有為の人材が日本の政治、社会において活躍の場を見いだすことができないとすれば、それはなぜなのか。台湾と日本では何が違うのか。その点を政治家や裁判官だけでなく、市民一人一人が自分の胸に手を当てて、考えることが大切だと思う。
人権、民主主義といった普遍的な価値観においてアジアのフロントランナーとなりつつある台湾。そのソフトパワーは、すでに日本を凌駕していると思う。日本と地理的、文化的に近い台湾から学べることは多い。本書は、その大きなきっかけをも、私たち読者に与えてくれるだろう。
(ふくおか・しずや 毎日新聞社 前台北特派員)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
