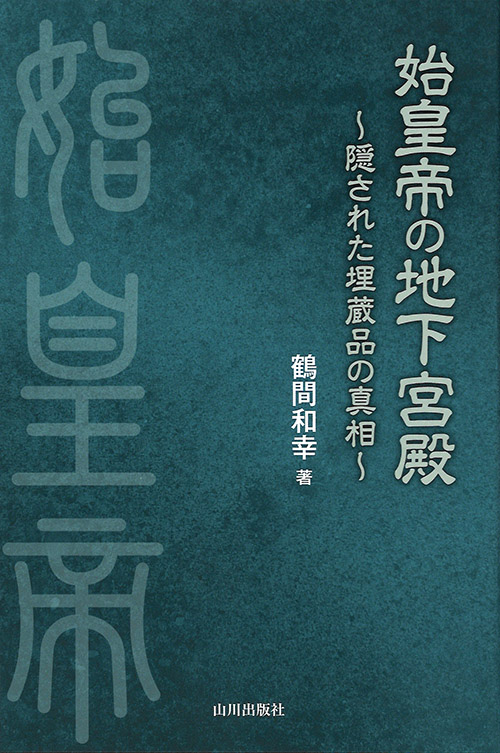
|
2001年、新世紀の始皇帝研究は、鶴間和幸氏の『始皇帝の地下帝国』(講談社。のち『始皇帝陵と兵馬俑』として講談社学術文庫に収録)によって幕を開けた。爾来20年、斯界をリードしてきた著者が、いよいよ始皇帝の地下宮殿に踏みこんだ。
もちろん、始皇帝陵はいまだ発掘されていない。よって本書は、タイトルから想像されがちな、出土品の解説本ではない。始皇帝陵や同時代の墓葬にまつわる最新の知見に基づき、地下宮殿とそこに隠された随葬品の真相究明を試みる、いわばヴァーチャル発掘の試みである。著者を先導に、読者は、地下30メートルの地下宮殿へといざなわれてゆく。
本書の全体は6つの章からなる。最終章を除く5つの章にはすべて「地下」と付くが、地下のことだけが延々と述べられるわけではない。むしろ、天空から陵園(を含む秦帝国)へ、陵園から地下宮殿へ、地下宮殿から墓室へとズームインしていく印象がある。
前掲した旧著原題と同じタイトルをもつ第1章「始皇帝の地下帝国」では、始皇帝陵の設計プランが示される。始皇帝の陵園空間については、近年、著者らによって衛星画像を用いた検討が進められ、渭水(北)・驪山(南)・驪山温泉(西)・戯水(東)に囲まれた10キロメートル四方にもおよぶ広大なものであったことが明らかにされた。この空間を、著者はギリシア・ローマの墓地群になぞらえて、「始皇帝のネクロポリス」と呼ぶ。「始皇帝のネクロポリス」の内側には、始皇帝陵の外城・内城だけでなく、それに附随した陪葬坑・陪葬墓が散在する。これら墓葬群の配置・性格を、立地・出土品の双方から読み解くことで、陵園全体の構成が俯瞰される。陵園のグランドプランに関するスケールの大きな議論と、各地点における具体的な発掘成果とが交差するスリリングな章だが、本書の性格上、考証過程を省略して結論のみを述べた点が少なくない。細部について知りたい場合、鶴間氏ら監修の『宇宙と地下からのメッセージ――秦始皇帝陵とその自然環境』(学習院大学東洋文化研究叢書、2013年)を参照することになるだろう。
第2章「小さな地下世界」と第3章「地下の小さな図書館」では、統一秦から漢代初期にかけての墓葬と出土品が紹介される。始皇帝陵の地下宮殿や随葬品の実像を推しはかるには、同時代の葬送習俗や土木技術、生活習慣などを理解しておく必要があるからである。第2章では睡虎地秦墓・龍崗秦墓・王家台秦墓といった湖北省の著名な秦墓とともに、咸陽周辺の小規模秦墓群も取り上げ、両者の共通点と相違点を浮き彫りにする。その一環として、湖北の秦墓に頻見する法制文書を中心とした簡牘が、咸陽周辺からは出土しないことにも言及される。第3章では、始皇帝の時代から間もない漢代初期を生きた利蒼とその家族が葬られた馬王堆漢墓(湖南省)に焦点を当て、法制文書以外の多様な書物のことと併せ、墳墓の構造や建築技術にまで説きおよぶ。よく知られているように、馬王堆漢墓からは利蒼の妻の遺骸がきわめて良好な状態で出土しているが、その理由についても、建築技術との関わりにおいて解説される。第2・3章は、1つ1つの墓葬からわかるさまざまな論点を個別にまとめているため、各秦漢墓の良質なガイドともなっている。
第4章「地下宮殿の構造」では、リモートセンシングによる始皇帝陵内部の調査結果や陵墓周縁部の発掘成果、秦公一号墓・前漢諸侯王墓の構造との比較など、さまざまな手がかりによりながら、始皇帝の地下宮殿の規模や構造を明らかにしていく。水銀で河川や海を作ったという文献の記載に基づき、墳丘地表面で検出される蒸発水銀の量や地下水面の高さから地下宮殿内部の様子を透視していくくだりには、心の昂ぶりを禁じ得ない。掘ることなくして内部の様子をうかがい知る、本書の手法の真骨頂がここにある。
第5章「地下宮殿の埋蔵品」では、秦極廟跡出土の秦封泥にみえる官名や『史記』李斯列伝の外国製品に関する記事を、考古学上の知見と照らし合わせ、地下宮殿に持ちこまれた「奇器珍怪」の比定を試みる。続く第6章「始皇帝の墓室」では、始皇帝の遺骸をとりまいていると思しき玉衣・印璽・剣、および遺骸の向きの問題について述べる。陵墓の最奥の状況や、そこに置かれた品々のことは、掘ってみなければわからない。それでもなお、現状において何を手がかりにどこまで想像することが可能かをありのままに示しているという意味において、本書は、「『埋蔵品の真相』を推しはかる手がかりの真相」に確実に迫っている。
先述したとおり、本書は、実際にはまだ掘られていない始皇帝陵の「ヴァーチャル発掘」である。従って、外側からはうかがい知れない内部に入れば入るほど、つまり後半にいけばいくほど、他の墓葬との比較に基づく想像や解釈がどうしても多くなる。著者の該博な学識と節度ある筆致によって、強引さはまったく感じられないが、それでもなお、異なる解釈が成り立つ余地もあることには、一定の留意が必要である。
例えば、第4章の後段では、『史記』秦始皇本紀の一節「上には天文を具え、下には地理を具う」の再検討が試みられている。それは壁画のことを言ったものではなく、二十八宿と方位を描いた2つの盤を重ねあわせた占具・式盤よろしく、天盤と地盤の重なる地を始皇帝の埋葬地として選んだ意なのだというのが、著者の主張である。天文・地理を意識した陵園プランが立てられたこと、始皇帝の埋葬地決定がその枠組みの中でなされたこと、それら一連の営為を式盤によって喩える表現があり得ることなど、個々の論点についての異論はない。地下宮殿の構造やスケールの大きさが、天井に天文を描くことを許さなかったという理屈もわかる。しかし、著者の説に従って秦始皇本紀の原文を読むと、地下宮殿ないし墓室の様子を具体的に述べるくだりの中で、この一箇所だけが埋葬地決定の論理を述べていることになり、前後が整合しなくなる。文献にありがちな誤解として『史記』を退けることもできるが、やはり今のところは、地下宮殿ないし墓室の内部かあるいは棺槨に、何らかの形で天文が描かれた可能性も残しておいてはどうだろう。壁画や漆画でなくともよい。棺材を玉片等で装飾して日や星のようにも見える文様を描き出した徐州獅子山漢楚王陵の例もある。
同様に、墓葬や随葬品に地域性の影響があるという著者の指摘には全面的に賛同するが、であれば、墓葬の構造や随葬品の材質などだけでなく、その背景にある制度についても、もう少し地域性を考慮しなければならないのではないか。一例として、第6章では秦始皇帝の印璽との関わりで、南越の「文帝行璽」が参照されているが、南越が秦の制度を一定程度とり入れたにせよ、楚・越とのつながりのほうがいっそう強く示唆されている(吉開将人「印からみた南越世界――嶺南古璽印考――」、『東洋文化研究所紀要』136・137・139、1998~2000年)ことに鑑みれば、その扱いには慎重でありたい。「文帝行璽」の印面の規格はそもそも「皇帝信璽」封泥と合わず、乾燥による封泥の収縮を考慮に入れたとしてもさらに大ぶりなものだし、「文帝行璽」の鈕はどうみても龍そのもので、漢の皇帝璽の鈕式とされる螭虎鈕(「螭」は龍の意にもとれるが、「虎」はあくまでも虎である)と同一のものとはみなせない(拙稿「魏晋南北朝皇帝璽窺管――玉璽・金璽と「伝統」の虚像――」、『中央大学アジア史研究』41、2017年)。のみならず、印面に「帝」とある時点で、「文帝行璽」の金質を皇帝の白玉質より格式を下げた結果とする説には疑義が生ずる。やはり「文帝行璽」には、秦・漢とは異なる論理に根ざした別系統の制度が作用しており、よって秦始皇帝の印璽とはきちんと区別して考えたほうがよい、ということになりそうである。無論、本書においても南越の制度が秦・漢と異なることについての言及はあるのだが、「どこがどう、なぜ異なるのか」が明確にされないので、予備知識のない読者は、南越帝の「文帝行璽」から始皇帝の印璽をイメージしてしまう恐れが高い。
さらに関連して、秦以降は始皇帝の墓葬の様式を至高のものとする認識が広く共有され、それと合わない漢代諸侯王の墓葬は何らかの制約の結果だと取れるような説明が第4章には散見されるが、始皇帝陵1つで、各地の文化的な伝統が根絶やしになるものだろうか。統一秦の記憶が漢初の人々に与えた影響とは、決して「継承」だけではなく、「反動」もあったはずである。そうした解釈を突きつめていくと、同時代の墓葬から得られる情報の中には、始皇帝の地下宮殿やその随葬品の推定よりも、むしろ相対化のために用いなければならないものもあることが、改めて浮かび上がってくる。だから最終的には掘るしかない、と言ってしまえば身も蓋もないが、いきなりそこまで飛躍せずとも、「始皇帝陵をめぐる解釈には、結局、統一秦や始皇帝の果たした歴史的意義に対する評価の問題がついてまわる」と結論することは許されよう。
始皇帝研究の最前線にある著者が、地下宮殿について考えるところを惜しみなく披瀝したのは、上述のような別の「解釈」を期待した上での、次世代に対するメッセージなのだと受け止めたい。どのような立場に立つにせよ、著者の後に続くわれわれには、本書で示された多くの情報を踏まえつつ、著者とは異なる解釈の可能性についてつねに思いを巡らし、来たるべき始皇帝陵の発掘に備える義務があるだろう。本書の読者の中からも、始皇帝陵の謎に挑まんとする新たな才能が立ち現れ、力を貸してくれるにちがいない。そのスタートラインとなるのが本書である。帯にあるとおり、始皇帝研究は、新たなステージへと踏みだしたのである。
(あべ・ゆきのぶ 中央大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
