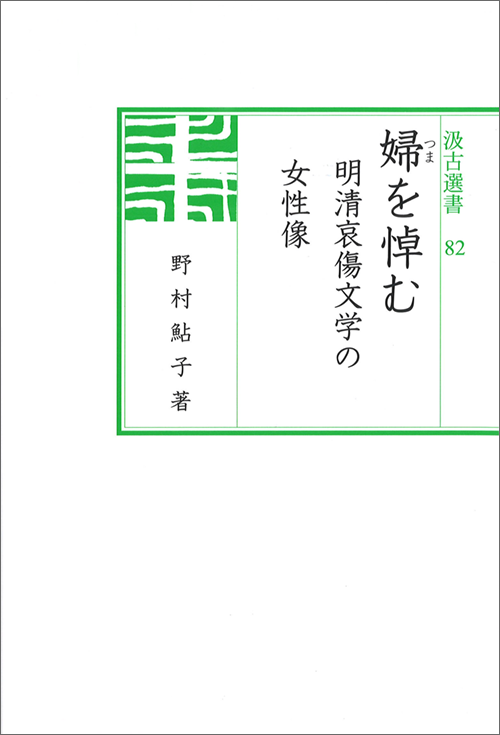
|
婦を悼むということ
『金瓶梅』第六十二回、病床に臥していた西門慶の第六夫人李瓶児が二十七歳でその生涯を閉じる。苦しむ李瓶児をなんとかして助けようと、西門慶は何人もの医者を次々に呼び寄せ、さまざまな薬を処方させ、廟に使いを遣って御符をもらい、道士を呼んで邪鬼払いをさせるが、効き目はない。道士に、自身にも災いが及びかねないためくれぐれも李瓶児の部屋へ寄りつかぬよう釘を刺されるものの、西門慶は「じっと我慢していられるわけがない。俺が死んだって構やしない、そばにいて、あいつと話をするんだ」と李瓶児のもとへ行く。「両の目からこもごも涙を流し、声を上げて」大泣きする西門慶、そして李瓶児も「両腕で西門慶の首を抱きしめ、おいおいと悲しげに長いあいだ、声も出なくなるまで」泣いた。朝方、李瓶児は静かに息を引き取る。
西門慶は、身体の下が血まみれだろうがお構いなしに、両腕で抱きしめ美しい頬に口づけして、ひっきりなしに呼びかけた。「ツキのないお姉さん、やさしくてまっすぐで、気立てのよかったお姉さん。どうして俺を置いてっちまったんだよ。この西門慶が死んだ方がましだったさ。俺もこの世に長く生きやしないよ。わけもなく生きてたって、なんにもならないもの」。部屋の中で、床から三尺も跳びあがりながら、大声をあげて号泣した。
『金瓶梅』全百回の中でも、とりわけ鬼気迫る回である。西門慶の悲しみは筆舌に尽くしがたく、食事も喉を通らない。その後、葬儀の準備、肖像画の作成、埋葬、法要と、李瓶児の死を巡る物語は第六十六回まで続く。西門慶は肖像画を見ては涙を流し、宴席で歌を聞いては李瓶児を思い出し、幾度も夢に李瓶児を見る。『金瓶梅』は何故に、李瓶児を悼む西門慶をかくも克明に描くのか。かくも魂を揺さぶる筆致で、かくも紙幅を費やすのか。その答えを求めて、野村鮎子著『婦を悼む──明清哀傷文学の女性像』(汲古書院、2025)を紐解く。本書の目的は、「明清における婦を悼む哀傷文学がどのように展開したかを考察し、その底流にある明清文人の女性像を示すこと」にある。亡き妻を悼む詩は『詩経』にも見られ、西晋には潘岳によって「悼亡詩」というジャンルが成立する。以降、中唐の韋応物や元稹、孟郊らによって悼亡詩は受け継がれ、あるいは革新され、宋代に至ると欧陽脩や梅堯臣によってその表現はいっそう多彩なものになる。悼亡詩は明清時代にも作り続けられ、前代に比べると圧倒的ともいえるほど作品数が増大する。しかし、「明清に至って妻を喪った文人は必ずといっていいほど悼亡詩もしくは悼亡詞を制作し、詩人は長編の悼亡組詩を作成した」にもかかわらず、「作品量が多いわりに明清の悼亡詩の文学史的評価はさほど高いとは言えない」という。もっともそれは、あくまで詩の表現や技巧に限定した評価であって、悼亡詩が盛んに作られたというその事実に目が向けられたものではない。そこに光を当てたのが本書である。
第一章「亡妻哀傷文学の系譜」では、悼亡詩、悼亡哀悼散文(墓誌銘、行状)、憶語体といった悼亡文学の系譜が、時代を追って概観される。
続く第二章「明清における悼亡哀悼文の展開──亡妻墓誌銘から亡妻行状へ」では、明清時代に至って盛んに作られるようになった亡妻哀悼散文が取り上げられる。従来、中国の士大夫は、悼亡詩という韻文、あるいは憶語という随筆小説の形で夫婦間の情愛を表現するものと理解されてきたが、憶語以前には、亡妻墓誌銘や亡妻行状といった散文の隆盛があり、特に生活のディティールを描く亡妻行状という文体の獲得によって、大切な女性との生活や感情が、よりありのままに描けるようになったことが示される。
第三章「明清における亡妾哀悼文」では、これまでほとんど扱われることのなかった「妾婢」に対する哀悼文が取り上げられ、「不正規な家族員」として副次的な地位に置かれた妾婢が、実際は士大夫にとってどのような存在であったのか、なぜ亡妾哀悼文のような文学が明清士大夫の間で広まったのか、それらを執筆するに至った彼らの心性について考察される。そこからは、決して単に子を得るための道具でも色欲を満たすための奴隷でもなく、起居をともにし、心を許すことのできるもっとも身近で親密な存在であった妾婢たちの姿が浮かび上がってくる。
続く第四章「明中期における亡妻哀悼の心性──李開先『悼亡同情集』を中心に」では、戯曲『宝剣記』の作者として知られ、また『金瓶梅』の作者候補の一人とも目される嘉靖年間の文人李開先による亡妻哀傷作品、ならびに彼が編纂した『悼亡同情集』という同時代人の亡妻哀悼文のアンソロジーを通して、明中期文人たちの心性が探られる。李開先自身、元配張氏と侍妾張氏に相次いで先立たれ、亡妻哀傷文学のもつ抒情に開眼し、悼亡をテーマとする作品を次々に制作したというが、『同情集』というアンソロジーが嘉靖期に成立した背景には、男女の情=夫婦の情ととらえ、他者の亡妻への悼念にも共感した文人たちの心性があったことが指摘される。
第五章「明の遺民と悼亡詞──艱難の中の夫と妻」では、明清鼎革期に作られた悼亡詩の名篇の中から、明の遺民として生きることになった三人の詩人の悼亡詩が取り上げられる。それぞれ異なる運命を辿った三人ではあるが、いずれも国家の滅亡という大きな歴史のうねりによって、個人の平穏でささやかな家庭生活が破壊された。妻を喪う哀しみは亡国のそれとオーバーラップするものであり、この時期の詩人にとって亡妻=亡国の象徴でもあったこと、「私」の領域である悼亡詩も、この時期においては「公」の要素を多分に含むものであることが指摘される。
第六章「清における聘妻への哀悼──舒夢蘭『花仙小志』を例に」では、清の詞人舒夢蘭の聘妻(病のために結ばれることなく世を去った婚約者)への悼亡に唱和した知人たちの作品、慰めの書簡、伝奇などが収録された作品集『花仙小志』が取り上げられ、清代士大夫の聘妻の悼亡に対する心性と文学のありようが考察される。清代には亡妻哀傷文学は隆盛を迎え、その対象は、亡妻や亡妾にとどまらず、嫁がずして亡くなった聘妻にまで拡大する。
第七章「明清における出嫁の亡女への哀悼──非業の死をめぐって」では、数は少ないものの、嫁ぎ先で非業の死を遂げた娘のために作られた作品が取り上げられ、明・駱問礼「章門駱氏行状」や、清・袁枚「哭三妹」五十韻が検討される。そこからは、ややもすれば家門の恥ともみなされる出嫁の娘の虐待死に対する、父親や兄の切なる思いが見えてくる。特に「章門駱氏行状」からは、娘の死を哀悼するとともに、虐殺を告発して娘の名誉を守ろうとする意図が窺えるが、これは「行状」という、元々は墓誌銘の執筆を依頼する際の提供資料であった自由な文体が、明清期に至って悼亡の文体として普遍化したことによって、はじめて可能となったのだと指摘される。
最後に、附論「前近代中国における女性同性愛/女性情誼」が置かれる。
悼亡詩、亡妻墓誌銘、亡妻行状、憶語体といった、これまでの明清文学研究ではほとんど顧みられなかった資料から見えてくる女性像とはどのようなものであったか。彼女たちは、「決して男性に従属する奴隷的存在などではなく、時に夫の『伴侶』として、『友』として、『同志』として、ともに日常を生きる『生活者』である。婦を喪うことは、その日常が消えることであり、自らの肢体がもがれるに等しいことだった」と野村氏は指摘する。筆者も強く同感する。
第六夫人李瓶児は、西門慶が最も愛した女性であった。なぜか。西門慶にとって、「伴侶」であり、「友」であり、「同志」でもあった、つまり最大の理解者であったからだ、と筆者は見る。死の直前、二人は互いに「我的哥哥(わたしのおにいさん)」「我的姐姐(わたしのおねえさん)」と呼び合い、李瓶児は西門慶の首を抱きしめてこう言う。
「目が明いているうちに、言っておきたいことがあります。あなたは立派な家産をお持ちですけど、頼れる親戚もなく独りぼっちで、手伝ってくれる人もいません。なんでもよく考えて、カッとなってはいけません。大奥様たちに、ご迷惑かけてはいけませんよ。あのかた、お身体がすぐれないのは、遠からず跡継ぎを産んでくださるのよ。そしたら家産だって、ばらばらにならずに済むでしょう。あなたは官職にもついているのだから、これからはどこかへ飲みに行くのは控えて、早めに家にかえりなさい。家を大事にしないといけませんよ。私がいて、朝な夕な諭してあげられたときとは違うんだから。私が死んだら、あなたになんでもきびしいことを言ってくれる人なんて、いるもんですか」。西門慶はこれを聞くと、刀で心肝をえぐりとられたよう。
李瓶児を喪った西門慶のくどいまでの哀しみの描写は、決して誇張でもフィクションでもない。そのことが、本書によって改めて理解できる。李瓶児の死が作品のクライマックスに位置づけられるのは、こうした哀傷文学の背景があったからである。悼亡の念の共有という時代の基盤があったからである。『金瓶梅』の作者、そして読者は、明清悼亡文学の担い手でもあったのである。余談だが、『金瓶梅』では、哀しみに暮れる西門慶を、正妻呉月娘や第五夫人潘金蓮が白けた目で見つめる。また下男の口を通して、西門慶が李瓶児を娶ったのも元々は金目当てだったことが明かされる。婦を悼む夫を描き切るだけでなく、その夫を見つめる周囲の冷ややかな目まで描くところに、『金瓶梅』の恐ろしさ、否、おもしろさがある。
*『金瓶梅』第六十二回の引用は、田中智行訳『新訳金瓶梅(中)』(鳥影社、2021)による。
(かわしま・ゆうこ 広島大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
