田中 智行
さきごろ下巻を刊行して完結した『新訳金瓶梅』(鳥影社、全三冊、2018~25)をめぐって、とびきりのエピソードを書けとのご依頼。芸もなくコツコツ翻訳してきただけの身には、毎日早起きして頑張りましたくらいの話しかないので困った。「地上の星」が聞こえてきそうな文体で苦労話を書こうかとも思ったけれど、基本的に楽しく訳した本なのに、急にシカツメ顔で努力の大切さを説き始めるのは、何か間違っている気がする。
もう二十年前になってしまった上海留学時代、韓国の留学生と、研究上のインスピレーションが湧かないという話をしていて、いまの自分は乾ききったタオルのようで、一滴の水が足りない。一滴の水さえ落ちてきたなら、あますことなく吸収してみせるのにと嘆きあったことがある。成果が出ないのは自分のせいではないという、たちのわるい言い逃れと思われるかもしれないが、当時としては切実な問題で、こんなことで大丈夫なのだろうかと心底不安を覚えていた。何とかしなければと思う反面、どうせ書くならばすぐれた着想の論文を書きたいとハードルを上げる心の働きもあって、一滴の水を待ちながら自縄自縛、じりじりと切羽づまりつつ傍目には漫然と過ごす、パッとしない日々が続くのだった。
思えば『金瓶梅』新訳は、一滴の水だった。
太田辰夫・鳥居久靖訳の『西遊記』二巻本で中国文学と出会った私にとって、いつか古典長編を全訳し、自分の訳文で新たな読者に中国文学の面白さを知ってもらうことは、十代からのあこがれだった。とはいえ四大奇書(『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』『金瓶梅』)にせよ他の有名長編にせよ、当時からすでに立派な翻訳が出ていて、私などが参入できる余地はありそうにない。『金瓶梅』については、最初に翻訳で読んだときの印象があまりよくなく、自分には合わない作品だと感じていた。
学部時代も終わりに近づいたころ、遅まきながら『金瓶梅』がすごい作品なのではと気づき、大学院での研究テーマにこの作品を選んだ。選んだからといってスラスラ読めるわけでは毛頭なかったので、学部時代を過ごした慶應の旧図書館にあった白維国と卜鍵による校注本全四冊をコピーし、他の版本と対照させつつ、辞典やら英訳やらと首っ引きで、一日数行ずつ読み進めていく。当初は校注本のコピーにあれこれ書き込んでいたのだが、コピーの余白への書き込みは見返すのに不便なので、途中から本文を書き写したノートを作るようになり、その過程で得られた着想に基づき、拙いながらも研究成果を発表できるようになっていった。
逆説的に思われるかもしれないが、そうして原文につきあい論文を書く過程で痛感したのが、新しい全訳の自分にとっての必要性だった。これはすでに大学に奉職してからのこと、苦心惨憺して『金瓶梅』第三十九回のノートを作成し、感じるところあってこの回についての専論をまとめようと思い立った。この回は、前半が道教儀礼、後半が尼僧による語り物上演という構成になっており、特に前半は道士が次から次に名を挙げる神様たちの儀礼において果たす役割を理解するだけでひと苦労だった。記憶ではたしか二、三ヵ月かけてノートを作り終えたのだが、では論文に取りかかろうと思い、書き込みを頼りにノートの本文を読み返してみると、唖然とするくらい読めない。それなりに納得しながら読み進めたつもりだったので、同じ箇所をもう一度読むのに、またもや苦労するとは想像もしていなかった。「今の自分にはここまでしか読めない」と思えたときにもうひと頑張りして、解釈を訳文として書き留めておけばよかったと臍を噛んだ。もっと言えば、それまで延々とノートを作ってきた本文すべてに訳をつけておいたならば、研究上の大きな財産になっていただろう。いや、時間さえかければ今から全文を訳すことも、不可能ではないはずだ──。
とはいえ『金瓶梅』は、公表のあてもなく訳し始められるようなボリュームの作品ではないので、そこからすぐに翻訳を始めたわけではなかったが、数年後に新訳の話をいただいたとき一も二もなく引き受けた背景のひとつに、そのような経験があったことは間違いない。いつかは全訳をと思いつつ二の足を踏んでいたところにもたらされた、まさしく一滴の水。タオルはカラカラになって水を求めていた。その時点での準備状況はといえば、すでに勉強しつづけること十数年でありながらノートは第五十回(全体の半分)にも及んでいなかったのだが、チャンスに後ろ髪はないとの言葉を信じ、『金瓶梅』全訳に、講義校務家事育児(順不同)を除くすべてを捧げることにした。
作品と作家の実生活とを安易に結びつけて論じてはならないとされるが、研究者の場合も、研究している作品からなんとなく人柄を想像されてしまうことはあるようで、いわゆる「やわらかい」分野を専攻していると、ときに研究者仲間からも「遊んでる?」などと訊かれることがある。いろいろお書きになっているけれど実体験はおありなんですか、というニュアンスなので、問われた側としてはなんらかの理論武装によって応答する必要が生じる。生活と研究上の関心とは別である、文学とは想像力による営みである、云々。
私の『金瓶梅』翻訳など、まさに生活は生活、作品は作品としか説明しようのないものだった。西門慶のように多くの女性とご縁があるわけでもなし、住んでいるのも広大な庭つきの邸宅ならぬマンションの一室。そもそも夜の場面で名高い作品であるのに、訳者はまだ幼かった子どもと一緒に早く就寝し、朝の四時台に起き出して、朝食までの二時間を翻訳にあてる生活だった。飲み会のたぐいにもほとんど出なかったから、「遊んでる?」と訊かれたらうつむくしかない。「享楽的な(面もある)作品を禁欲的に訳すところに緊張感が生まれる」というのがひとまずの言い分だったが、早起きしてお父さんが一生懸命訳していた難しそうな本の中身を、将来子どもたちが読んだときの反応が、やや恐ろしい気もしている。
そう、西門慶に比べて私の方がハッキリ恵まれていたのは、元気な子どもたちの存在だった。赤ちゃんが延々大泣きするのを俗に「ギャン泣き」というが、満一歳で亡くなる西門慶の息子の「怪哭」に「滅茶泣き」という訳語を当てたのは、この俗語(と我が子の泣きっぷり)を参考にしている。毎日読んでいた絵本の言い回しを訳文に取り入れてみた箇所もあり、人物のセリフのなかで「〇〇さんのところ」を「〇〇さんところ」と略すのは、ロングセラー絵本『ぐるんぱのようちえん』の顰みに倣っている。着手したころ住んでいた徳島には、子どもたちが「遊山箱」という重箱を持って春の行楽に出かける旧習があったと聞き、その言葉が気に入って「遊山用のごちそう箱」を訳文に登場させたこともあった。古典の訳本にあらわれた、ささやかな訳者の個人史といえるかもしれない。
徳島大学に勤務していたとき、私のポストの先々代にあたる竹治貞夫先生が研究室に残された私家版の自作漢詩集を読んでいたら、『紅楼夢』の英訳者ホークス(David Hawkes)の訪問を受けたとの記載をみつけて驚いたことがある(残念ながらこの詩集はいま手元にない)。そのホークスが英訳『紅楼夢』導言の末尾に記した印象的な一節は、ロイ(David Roy)の英訳『金瓶梅』導言にも、⻑年にわたり自らを励ましてくれた述懐として引⽤されている。私が学部四年のころ、将来『金瓶梅』を翻訳するとは思いもしなかった時期に読んで感銘を受けたその言葉を、読者のなかにいるかもしれない未来の大長編訳者に捧げて、この小文を結びたい。
私のただひとつ変わらぬ原則は、あらゆるもの──たとえそれが語呂合わせであっても──を訳出することだった。なぜなら[中略]「未完成」の小説であるとはいえ、これは偉大な芸術家が心血をそそいで書いた(そして書き直した)ものだからだ。それゆえ私はこう信じて疑わなかった。「この小説の中に私が見いだすものはすべて、なんらかの目的があってその場所にあるのであり、なにかしらの対処をしなくてはならぬものなのだ」と。いつも見事にやってのけたなどと言うことはできない。けれどもこの中国小説が私に与えてくれた喜びの、ほんの一部でも読者に伝えられたならば、私は空しく生きてきたわけではなかったのだ。
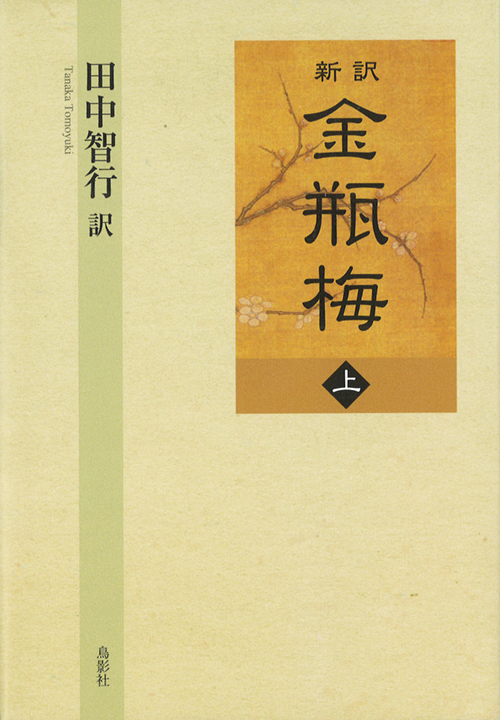
|
(たなか・ともゆき 大阪大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
