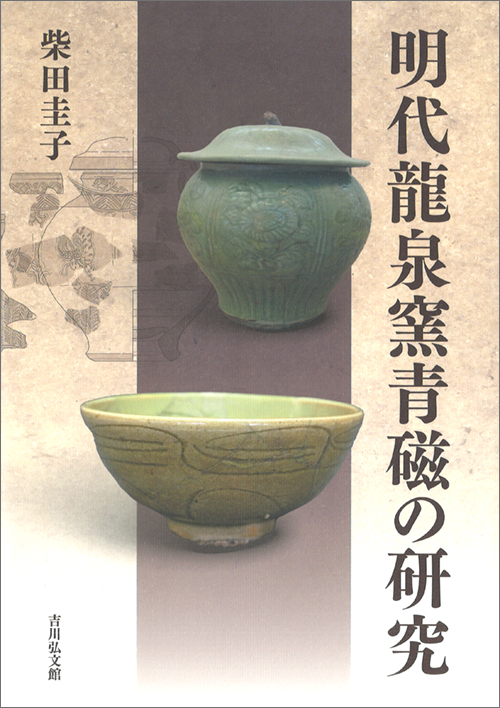
|
本書は明代の龍泉窯青磁に関する研究書である。龍泉窯は中国浙江省の西南部に位置し、粉青色や翠緑色の美しい青磁を生産した窯として名高い。その製品は中国国内のみならず、世界各国に広く輸出されており、とくに日本では多くの為政者や富裕層に好まれ、伝世した名品は今日でも各地の美術館や博物館で見ることができる。試みに日本の国宝に指定された中国陶磁を見てみると、その数は合計8件あり、日本の茶の湯文化を語る上で欠かせない天目茶碗が5件を占めるほか、残りの3件はすべて龍泉窯青磁である。ここからも、日本において龍泉窯がどれほど珍重されていたかが見て取れるだろう。ではその生産年代はというと、南宋(1127~1279年)が2件、元代(1271~1368年)が1件である。この背景には、龍泉窯が最も美しい青磁を作ったのは南宋~元代であり、明代(1368~1644年)には衰退するという認識が存在していた。このため、伝世品を対象とした美術史学の文脈で龍泉窯を語る際、明代以降について深く言及されることは少ない。
美術史学の俎上にのりづらいのなら、考古学はどうであろう。日本には極めて精緻な考古学研究の蓄積があり、龍泉窯青磁についても九州の大宰府や博多を中心に、各地の遺跡から出土する資料を分類し、編年を作る研究が行われてきた。しかし、それらはあくまで日本という消費地の状況のみを反映したものであり、生産から廃棄に至るまでのタイムラグや、日本人による取捨選択という要素が内在している。くわえて、明朝政府による海禁政策の影響により、日本で出土する明代前期の資料が少ないという状況も相まって、日本の考古学では明代龍泉窯青磁の全容を捉えきれていなかった。
だが近年、中国における陶磁研究が盛んになり、明代の龍泉窯青磁を巡る状況は大きく変化しつつある。その大きな画期となったのは、2006~2007年に行われた龍泉大窯楓洞岩窯址の発掘であろう。この発掘では、従来不明瞭であった元代~明代の青磁を包含した地層が確認され、生産地の出土資料による編年研究が可能になった。さらに、明代初期の宮廷用に作られた極めて良質な青磁が発見されたことも、大きな話題となった。楓洞岩窯址出土資料は日本でも展覧会が開かれ、龍泉窯は明代に質が悪くなり衰退するという見解は再考を迫られている。
さて、このように重要性が高まりつつある明代龍泉窯青磁に対して、考古学的な研究を行うとなった際、出土資料に恵まれた最適な地域が日本国内に存在していた。それは明朝政府と早い段階から朝貢関係を結んでいた琉球、現在の沖縄である。無論、これまでにも沖縄出土資料の分類および編年研究は行われていた。だが本書は、沖縄で出土した龍泉窯青磁を網羅的に集成しつつ分析を加え、それに中国など日本国内外で出土した関連資料を対照させることで、従来にない規模から明代龍泉窯青磁の実態解明に挑んだという点で画期的である。
前置きが長くなってしまったが、ここからは本書の内容を簡単に紹介していきたい。本書の構成は以下のとおりである。
第1章では、龍泉窯青磁に関する研究史の整理を行い、従来の研究が日本国内の遺跡から出土する資料の細分に注力するあまり、龍泉窯青磁の全貌が捉えられていなかったという反省に立ち、中国の生産地や日本国内外の様々な遺跡を総合的に検討することの重要性が述べられている。
くわえて、従来の研究で龍泉窯青磁の編年が不足している時代を抽出し、その結果として元代中期~後期(14世紀前葉~中葉)、明代初期(14世紀後葉~15世紀前葉)の編年を本書の課題として位置づけることが示されている。
第2章からは、具体的な編年の検討に入っている。まず注目している器種は、陶磁器の中でも一般的に数が多く、分類および編年研究を行うのに適した碗・皿・盤である。従来の大宰府や沖縄の研究で得られていた龍泉窯青磁の分類を踏襲しながらも、元代中期以降に出現するⅣ類と、明代初期に出現するⅤ類を細かく分析することで、その中間的な様式の存在を抽出している。これにより、従来の陶磁研究で「元末明初」と括られていた青磁について、より細分化できる可能性を指摘している。
第3章では、龍泉窯青磁の中でも典型的な大形品として知られる蓋罐(日本では「酒海(会)壺」と呼ばれる)に焦点を当て、その分類と編年を行っている。ここでも第2章と同様に元代と明代中期の中間的特徴を持つ製品の存在を指摘しており、明代初期の蓋罐の様相に言及している。
第4章では、久米島の宇江城城跡から出土した龍泉窯青磁の鳥文蓋罐について検討を加えている。著者は破片の実測と器形の復元を経て、本作品が明代中期(15世紀中葉)に製作された希少な作例であり、龍泉窯青磁における装飾技術の到達点に位置づけられると評価している。
第5章では、龍泉窯青磁の大瓶について複数の基準資料から編年を作り、それに首里城跡出土の資料を対応させることで製作年代の推定を行っている。その結果、首里城跡から出土した3点の大瓶は、明代初期に製作された可能性が高いと結論付けている。
第6章では、これまでに行った各編年を俯瞰的に捉え、明代初期~中期における龍泉窯青磁の特徴についてまとめている。まず明初期については、碗・皿・盤の多くに簡素化の傾向が見られる一方、明朝宮廷で使用された青磁と同様の特徴を持った精緻な製品も見られ、製品の質の二極化が起こっていたことを指摘している。そして明中期前半になると、青磁に施された刻文や印花などに加飾性と多様性が見られるようになる。この背景には、政府の管理を受けた官窯における生産体制の変化や、民窯の隆盛、景徳鎮窯の影響などがあった可能性に触れている。
第7章では、龍泉窯青磁から見えてくる琉球社会の実態、および琉球から他地域への影響について言及している。龍泉窯青磁の大形品のうち、とくに数が多い蓋罐に注目した結果、15世紀中葉以降は王城のみならず集落遺跡からも出土が確認できた。このため、琉球では蓋罐が様々な階層で受容されており、これが他地域には見られない琉球の特殊な傾向であると述べている。また、日本各地の遺跡から出土した龍泉窯青磁を分析し、その交易ルートを検討した結果、博多を通らずに本州以北へ物品を運ぶ九州東岸ルートが顕在化するなど、琉球の存在が日本全体の流通ルートに影響を与えていたことを指摘している。
以上のように、本書では沖縄の遺跡から出土した龍泉窯青磁の分析に軸足を置き、その詳細な分類および編年を行った上で、関連する諸問題について検討を加えている。このように書くと、従来の研究と何が違うのだと思われるかもしれないが、本書では沖縄出土資料の半ば悉皆的な利用にくわえ、中国で報告された窯址や沈没船、さらには小規模な墓葬や窖蔵の発掘報告までも分析の対象にしている。これまでに刊行された報告書にある関連資料はすべて利用しているのではないかと思われるほどの情報量と、それに基づく詳細な分析は、まさに圧巻の一言に尽きる。
今日私たちが美術館や博物館で古い陶磁器を見ると、当たり前のように生産年代が書いてあると思う。だがこの年代は、多くの研究者による研究の蓄積の成果であり、とりわけ考古学による編年研究は、その遺物の歴史的位置づけを明らかにするための「ものさし」を作り上げることである。本書はこれまでに年代の判断基準が不足し、「元末明初」という曖昧な言葉で片付けられていた時代の龍泉窯青磁を理解するための、重要な「ものさし」を提供したともいえるだろう。まさに龍泉窯研究はもとより、日本の貿易陶磁史や中世考古学においても指標となる研究であり、陶磁器に関心を持つ研究者にとっては必読の内容である。くわえて、引用された図版資料が多く、読みやすい文章で書かれているので、陶磁鑑賞を楽しむ愛好家にとっても龍泉窯青磁の知識を深めるのに有用な書籍である。
(あらい・たかゆき 町田市立博物館)
※現在休館中、2029年にリニューアルオープン予定
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
