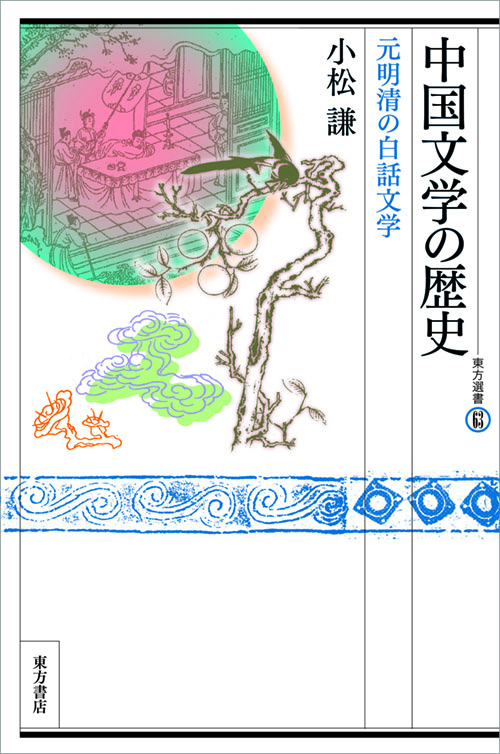
|
中国文学の「やさくわ」になるか
研究書、ともすればそれは難解で堅苦しく、軽い気持ちで手に取ろうものなら読者の心を容易にへし折ってくる。それはおおむね執筆者の数年、あるいは数十年にも及ぶ研究論文の集大成であり、対象とする読者もおのずから研究者を想定しているため、一般の読者からすれば、興味を覚えたとて(値段からしても)勢い手を出しがたい。
本書の著者である小松謙氏が2007年に汲古書院より出版された『「現実」の浮上──「せりふ」と「描写」の中国文学史』は、個人的にこれまで読んだ研究書のなかで最も面白く読んだうちの一冊である。その「あとがき」によると、これは大学での講義に端を発するもので、小松先生ご自身は「一般書のつもり」で、読者には「非専門家を想定」して書いたとおっしゃっているが、書籍そのもののたたずまい(とやはり値段)からして、研究書の棚に架蔵されるのがふさわしいように思われる。
そんななか、本書が東方選書として出版されたことの意義は殊のほか大きい。本書が主にあつかうのは元・明代における白話文学作品である(白話とは話し言葉の語彙を用いた書き言葉のこと)。第一部「金・元の文学」の冒頭には、そもそも白話とは何かを説く「一、白話文学前史」が、そして白話文学はいかにして興ったのかを説く「二、金の文学 白話文学の誕生」が置かれ、白話とは何なのかについて丁寧な解説が施されている。
これにより、中国の文学といえば史記・唐詩・三国志(演義)くらいしか聞いたことがない人も、あるいは「漢文・唐詩・宋詞・元曲」くらいは聞いたことがある人ならなおのこと、本書が詳述する元代の曲と明代の小説に関する章、つまり本書の核心部分へとスムーズに読み進めることができるであろう。日本人になじみのある『三国志演義』や『水滸伝』、『西遊記』などは本書の第二部でくわしく述べられているが、ここではあまり一般に知られていない、第一部「三、元の文学(一)曲の世界」の内容を取り上げて簡単に紹介する。
中国文学の流れを概括する謂いとして、上に述べた「漢文・唐詩・宋詞・元曲」のうち、前二者は日本でも相当なじみの深い言葉であろう。残る二つは、それぞれおもに宋代と元代に流行したメロディにのせてうたう歌詞である。この点で両者は本質的に同じものといえるが、著者はその形式的な差異を①異なる旋律、②『中原音韻』の体系による押韻、③襯字の使用、④白話語彙の多用、⑤套数の存在の五点に集約している(pp.10-13)。
このうち元代の曲をとくに際立たせる要素が、③から⑤の襯字(曲律に規定された字数のほかに加えられた字)、白話、套数(複数の曲をつなげた組曲)である。著者はそれらをわかりやすく読者に示すため、まず宋詞と大差ない例として楊果の【小桃紅】を挙げ、ついで、杜仁傑の【耍孩児】からはじまる套数「荘家不識构欄(田舎者 劇場を知らず)」の一部を引き合いに出す。いま試みにそれぞれの原文(後者は一部のみ)を見てみよう。
楊果
碧湖湖上采芙蓉。人影随波動。涼露沾衣翠綃重。月明中。画船不戴凌波夢。都来一段、紅幢翠蓋、香尽満城風。
杜仁傑
見一箇手撑着椽做的門、高声的叫請請、道遅来的満了無処停坐。説道前截児院本調風月、背後么末敷演劉耍和。高声叫、趕散易得、難得的粧哈。
また、白話語彙を縦横無尽に用いることで、日常の衝動がきわめて饒舌にうたわれるようになることも、元代の曲の大きな特徴である。著者はその一例として馬致遠の【耍孩児】にはじまる套数「借馬」を挙げる。ここでは一曲のみ、著者の訳と合わせて引用する(pp.31-32)。
近来時買得匹蒲梢騎。命児般看承愛惜。逐宵上草料数十番、喂飼得膘息胖肥。但有些穢汚却早忙刷洗。微有些辛勤便下騎。有那等無知輩。出言要借、対面難推。
最近西方の名馬を買うて、命のように大事にしておった。毎晩飼い葉をやること数十回、餌をやってよく肥えさせた。ちっとでも汚れがあれば、急いでこすり洗って、ちっとでも疲れたようならすぐに下りた。あの物のわからん奴らが、貸してくれなんぞと言い出しおって、面と向かっちゃ断ることもなりかねる。
実のところ、こうした作品はそれほど多くはなく、大半は楊果の【小桃紅】のように宋詞の流れを汲んだものである。だが、これまでの伝統的な詩詞と打って変わった興趣あふれるうたの数々を、伝統的な詩文の先にある中国文学の新たな一面を、本書を通して多くの方に知ってもらいたい。
古来、中国で「読書」といえば、それは勉強のことにほかならなかった。では、今日的な意味での「読書」、すなわち娯楽としての「読書」はいつ、どのようにして浸透していったのか? 著者はそうしたマクロな視点から、一般の読者に向けて白話文学作品を紹介してくれる。それは翻せば、個々の作品に対する著者の鋭くも膨大な実証的研究が一本の線となった結果でもあり、上述した『現実の浮上』や本書は、「文学史」というものが著述されてゆくさまをありありと見せてくれる。
昨今、書籍の値段(印刷代や紙代)が急激に高騰し、文庫本でも1冊1000円、新刊本なら2000円、3000円は当たり前という時代である。著者の知見の一部を2600円で垣間見ることができると思えば、これはバーゲンセールと言っても過言ではない。
本書が「学術エンターテインメント」と銘打つ東方選書に収められたのは故なしとしない。気軽に買えること、楽しんで読めること、それこそは本書が扱う白話文学作品のかつて目指したところだからである。実は本書そのものも同じはたらきを有していると思えば、なんとも興味深いではないか。本書の帯に大書される「娯楽の読書はここから始まった」の一文は、「ここ」、つまり本書を指すダブルミーニングなのであろう(と勝手に考えている)。
古典文学研究と白話文学研究のあいだには、いまなお大きな隔たりがあるように思われる。むろん膨大な中国文学史のすべてを考究することは容易ではないが、これから中国文学の研究を志す者なら、まずは安藤信廣氏の『中国文学の歴史──古代から唐宋まで』(東方選書56)と本書を合わせ読むべきであろう。そして本書を読んだあとは、ぜひ一歩進んで『現実の浮上』を手に取ってほしい。『現実の浮上』をすでに読まれた方なら、そのエッセンシャル版として本書を座右に置いておくのもよいであろう。
著者のやさしくくわしい解説に導かれながら、生気あふれてこなれた訳文を味わえば、読者はきっと新たな中国文学の魅力に気づくに違いない。おそらくは当時の人々も、生き生きとした白話語彙による作品を通じて、勉強ではない感動と興奮の読書体験を知ったのであろう。本書は、いかにも学術的な本らしいタイトルである。そして中身も確たる学術研究に裏打ちされた学術書である。しかしながら、往時の人々がはじめて味わった「娯楽の読書」を、きっと読者に追体験させてくれるであろう。
▼本稿でご紹介した書籍
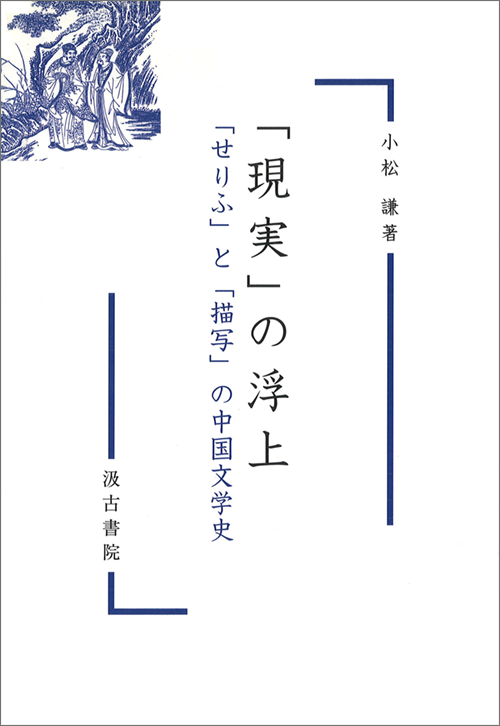 「現実」の浮上 「せりふ」と「描写」の中国文学史 「現実」の浮上 「せりふ」と「描写」の中国文学史(小松謙 著) 出版社:汲古書院 出版年:2007年 7,700円 |
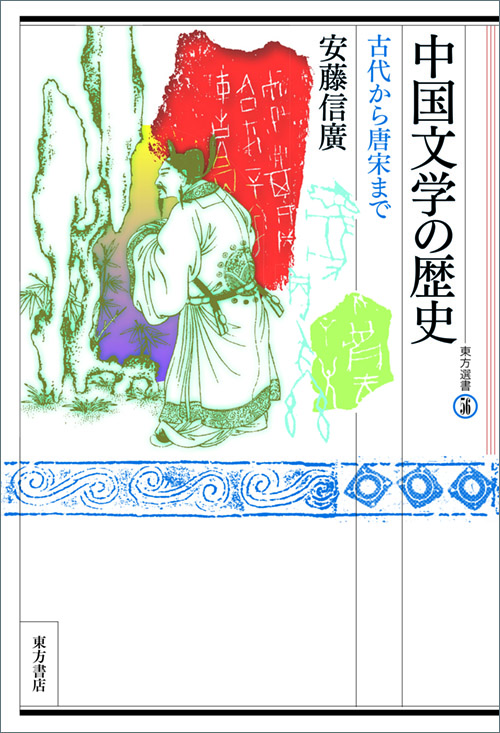 中国文学の歴史 古代から唐宋まで 中国文学の歴史 古代から唐宋まで(安藤信廣 著) 出版社:東方書店 出版年:2021年 2,640円 |
(ごとう・ゆうや 目白大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
