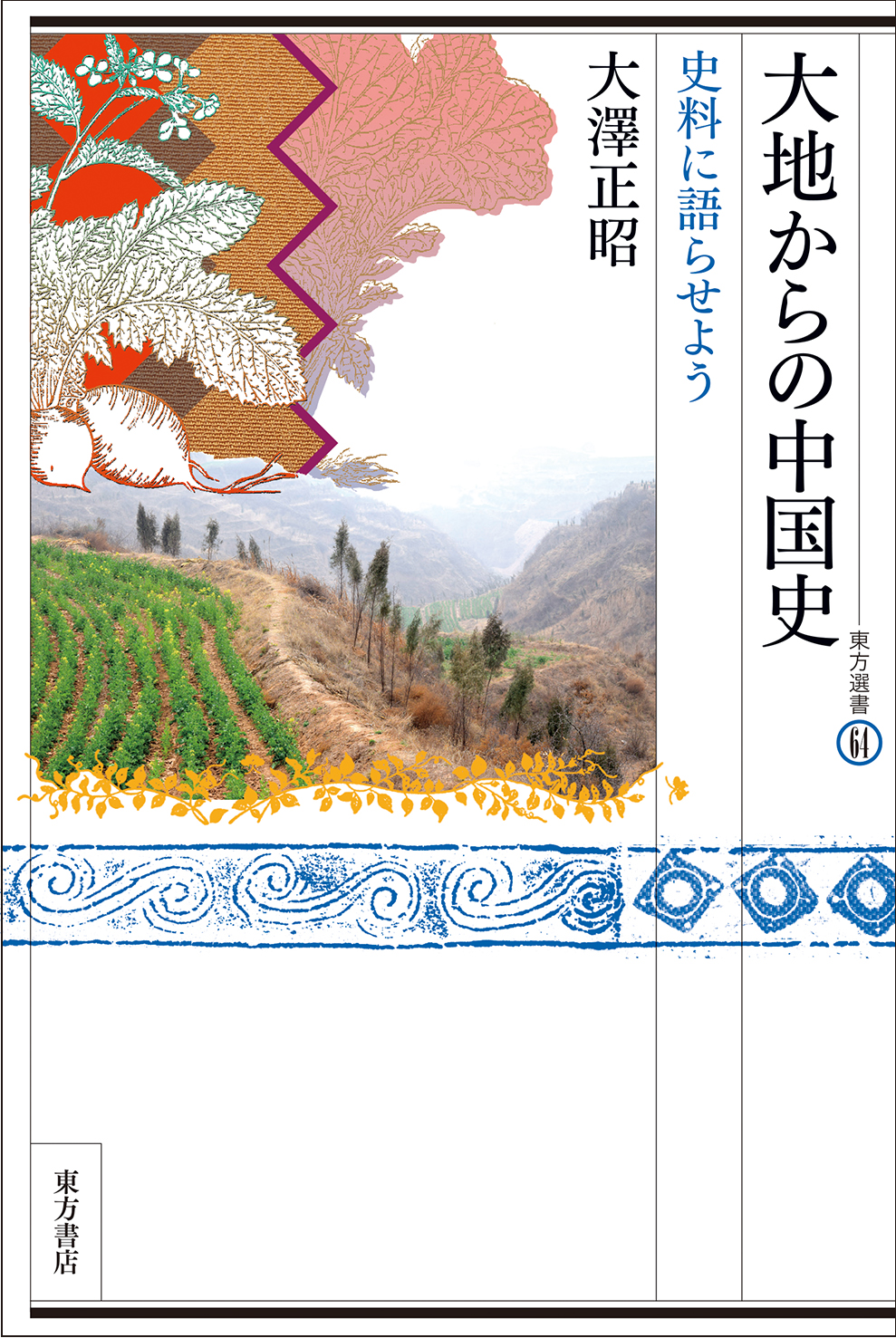 大地からの中国史
大地からの中国史
史料に語らせよう〔東方選書64〕
大澤正昭著
2025年1月
価格2,640円
『大地からの中国史』まえがきより
◆ 農業史の「概説」って?
さて私が想定する読者の対象は、大学の受験生・新入生から一般の社会人です。歴史の概説書というと、ふつうは政治史や制度史をメインに据えます。政治史とは、誤解を恐れずにいえば、王朝・国家の内部の、きわめて限られた範囲の皇帝・官僚たちの動向です。そうした少数者が国家の権力を握っており、徴税や戦争など一般の人々の生存を左右する政治をおこなうのです。ですから、そうした国家の本質を描き出し、その成り立ちに迫ろうとする概説書なら、それは歴史研究者にとってきわめて重要な課題です。このような鋭い問題意識をもって書かれた概説ももちろん多く存在します。たとえば渡辺信一郎氏の『天空の玉座』『中華の成立』、足立啓二氏の『専制国家史論』などはぜひお読みいただきたい成果です。けれども私の興味は国家や政治史の対局にある、圧倒的多数の人々、とくに大地に足をつけて生きてきた農民とその営みに向けられています。国家に対置される農民の歴史、これも重要な研究課題だと考えます。
彼らは〈愚民〉として支配され、抑圧されてきましたが、食糧・衣料の生産によって、皇帝や官僚たちが動かす国家全体を支えていました。農民がいなければ国家の歴史はなかったのです。ですが、彼らの歴史はほとんど注目されません。そうして当然、支配されてきた彼らに関する史料は多くありません。また彼らはいわゆる歴史のロマンなどとはもっとも縁遠い存在です。けれどもこの視点で研究を続けてゆくとさまざまな発見があります。これまでの歴史像とはかなり異なる歴史がみえてきます。この支配される側からみた歴史というテーマは、きわめて〈個人的な感想〉ではありますが、相当に魅力的だと思っています。私はさきに『妻と娘の唐宋時代』という本を書きました。その主人公は差別され、抑圧されていた女性たちでしたが、その史料に描かれた実態は、思い込みや虚像を打ち破るものがありました。差別・抑圧された側からみれば、いままでみえていなかった事実が浮かび上がってくるのです。本書はこれと通じる視点をもって研究した成果です。
中国の農業史というテーマの概説ですから、日本では類書がないと思います。もちろん専門書では天野元之助氏の『中国農業史研究』という巨大な研究書があり、私も座右の書として大切にしています。しかしこの本は専門書ですので、学説史の知識や漢文史料の読解力が必要になります。一般の人にはなかなか読みこなすことができません。農業という、人間に身近なテーマで、日々の食料に直結する問題を扱っており、とても興味深い研究なのに、もったいないことです。そこでもっと読みやすい本が必要だとずっと考えてきました。そうして私の農業史研究も深まってきたので、その成果をわかりやすくアピールしたいという思いが募ってきました。となると最先端の専門研究をわかりやすく、読みやすく書かねばなりません。これが難しい課題なのですが、私のこれまでの研究成果を見渡しながら、なんとか苦労して書き上げました。
◆ なぜ農業史なの?
〈いま〉という時点で、このような農業史の本を書くのはなぜでしょう。簡単に述べておきます。
このところ世界の農業をめぐる話題が連日ニュースになっています。とくに二〇二二年から続く、ロシアによるウクライナ侵略がその契機でした。ここで明らかになった世界の食糧需給関係は、私たちの目の前に危うい現実が存在する事実を突きつけました。たとえばウクライナから輸出されるコムギやトウモロコシの流通が妨害されたことによって、世界各地で食糧価格の高騰が起こりました。わが家がご贔屓にしているパン屋さんでも商品の値段が上がり、気のせいかお客の数も減ったようです。先進国ではまだ何とか価格を抑えていますが、アフリカ諸国では深刻な食糧危機を迎えているといいます。北のロシアの侵略行動が遙か南のアフリカで食糧危機を引き起こしているのです。これはいわゆる国際的分業の経済構造がもたらした結果です。簡単にいうと、たとえば食糧・原料の生産国と自動車など工業製品の生産国が役割分担しようという国際的な分業体制論です。この過程で後者の先進国が富を蓄積してきました。こうして先進国はその経済力を背景に食糧を買いつけることができ、発展途上国は食糧難に直面しています。でもその裏側をみると先進国は自国での食糧生産を軽視してきました。日本も食糧自給率が下がり続け、いまでは四割に届きません。かつて作家の井上ひさしさんは「いざとなったときに自動車が食えるのか?」と問題を投げかけ、日本の稲作、食糧生産を守れと訴えていました(『コメの話』など)。また農民作家として多くの作品を発表された山下惣一さんも農村の現実を告発しながら、農業の大切さを訴えました(『土と日本人』『村に吹く風』など)。私もこれに大いに励まされ、三〇年前に蟷螂(カマキリ)の斧にも及ばない『陳旉農書の研究』を刊行しました。これはいうまでもなく専門書でしたが、この本を通じて、まずは自分の食べているものにもっと関心をもとう、食べているものの成り立ちを知ろうと呼びかけてきたつもりです。ですがまったく私の見当はずれで、『陳旉農書』という無名の本に関する研究など見向きもされませんでした。出版社さんにはご負担をおかけしてしまいました。
とはいえこの本の出版に苦労するなかで、私の主張はしっかり固まりました。ある食品会社のコマーシャルに「人間の身体は食べたものでできている」というのがありますが、これはひとつの真理だと思うようになりました。私たちの身体は間違いなく食べものによってつくられてきたのです。ですから自分の人生を考え、よりよく生きようとするなら、何といっても食べものから出発しなければならないのです! と力説すると、ちょっと飛躍しているかなとは思いますが。でも、自分が生きている〈いま〉を知るために、歴史学の立場から〈食べもの〉に迫ってみたいという思いはいっそう募りました。これが私の農業史研究の最大のねらいです。
