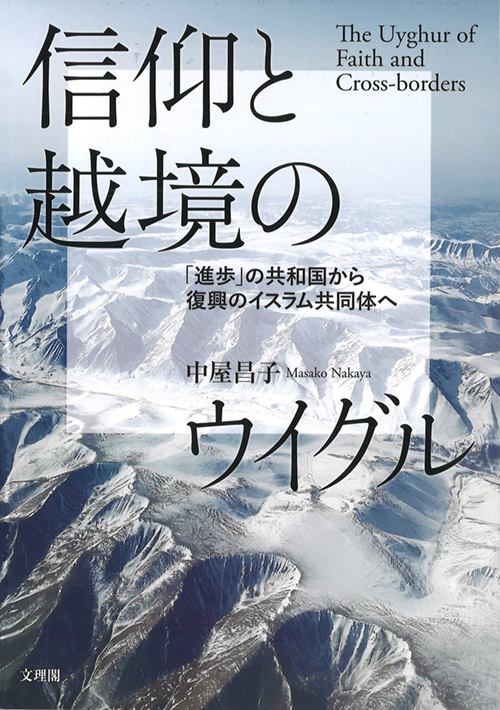
信仰と越境のウイグル
|
個人的な話から始めて恐縮であるが、中屋昌子氏と配偶者氏は、ご近所同士ということもあり、たまにコメダ珈琲で四方山話をする仲である。中屋氏は若い頃、中国に長らく留学していたことから、中国語に堪能であるが、結婚後、トルコにも長らく留学し、トルコ語だけでなくウイグル語もマスターしている。ある夜、配偶者氏と四方山話をしていた際、氏がちょっと失礼と断って、トルコ留学中の中屋氏にスカイプで電話をかけたのは、20年近く前のことだ。その時には、絆の強いカップルだなと思うだけで、中屋氏が評者の研究に大きく関わる珠玉の著作を書き上げるための準備をしていたなどとは思いもよらなかった。評者は、近年におけるウイグル族などムスリム少数民族への「ジェノサイド」に関する単著を執筆中であるが、本書に出会ったのは誠に僥倖だったと思う。
本書の構成について見ておこう。
序章
第1章 新疆における宗教統制の成立過程
第2章 新疆におけるイスラム復興と宗教統制
第3章 サラフィーのウイグル
第4章 民族主義者はいかにイスラムの覚醒を経験したのか
第5章 スーフィーはなぜトルコに来たのか
第6章 トルコで見出したイスラム共同体
終章
第3章以下について補足しておこう。第3章では、2009年7月の7・5ウルムチ事件以降、サラフィーのウイグル族が信仰の自由を求めてトルコへ亡命するに至った経緯について取り上げている。7・5ウルムチ事件とは、広東省でのウイグル族への暴力事件をきっかけに、ウルムチでウイグル族が漢族と衝突し、治安部隊の弾圧を招いたという事件である。サラフィーとは「コーランとスンナ(預言者ムハンマドの慣行)に忠実であること」などを強調する原理主義的なスンニ派のムスリムを指す。第4章では、文化大革命直前に生まれ、1990年代の「自由」な雰囲気を謳歌し、世俗的な民族主義に傾倒したウイグル族が、トルコ亡命後、サラフィーになるに至った顛末について明らかにしている。
第5章では、ウイグル族は元来、神との合一を目指すイスラム神秘主義教団の信徒であるスーフィーが多かったが、トルコ亡命後もサラフィーになることなく、スーフィーであり続けるウイグル族が、1980年に出国しトルコに至るまでの経緯について取り上げている。第6章では、7・5ウルムチ事件以降、トルコ社会の後援を受けながら、ウイグル族のディアスポラ・コミュニティが拡大してきた状況について明らかにしている。終章では、トルコにおけるウイグル族のディアスポラ・コミュニティのイスラム復興について総括している。
本書の特筆すべき点は、第一に、中華人民共和国建国から今日までの、中国当局による新疆における複雑な宗教統制の変遷に関して、手際よく整理したことにある。中央レベルの法規と自治区レベルの法規、及び正式な法規と暫定的な法規が入り混じるなどしており、整理するだけでも相当な難事である。以下に掲げる第1章の表1「宗教政策とイスラム信仰実践のせめぎあいの歴史」などは、研究者にとって必見だろう。近年、「ジェノサイド」に目を奪われがちだが、宗教統制のあり方自体は、基本的に「1958年の枠組みが現在まで引き継がれている」という。
| 1949~58年 | 1958年~現在 | |||
| 1966~78年 | ||||
| 信仰告白 | 〇 | 〇 | △(制度上は〇) | △(18歳未満は不可) |
| 礼拝 | 〇 | 〇 | △モスクで金曜礼拝があった | △2001年以降、官製説教テキスト。18歳未満はモスク入場不可。 |
| 喜捨 | 〇 | ザカート× サダカ△ ワクフ× |
ザカート× サダカ△ ワクフ× |
ザカート× サダカ△(モスクのみ) ワクフ× |
| 断食 | 〇 | 〇 | △(制度上は〇) | △18歳未満は不可 |
| 巡礼 | 〇 | × | ×(密出国は不明) | △2005年以降、官製ツアー以外は不法 |
| 教育 | 〇 | △宗教学校は北京に1校のみ | × | △公立のみ許可、私設宗教学校禁止。18歳未満への宗教教育は不可。 |
第二に、インタビューを通して、改革開放後にイスラム信仰ゆえに、新疆から逃れざるを得なかったウイグル族のディアスポラの歩みを具体的に明らかにしたことにある。その上、中屋氏が通訳を介することなくウイグル族とコミュニケーションがとれるためだろうか、インタビュー内容を要約して伝えていても、インタビュイーの躍動感まで伝わってくるのである。評者の拙い筆致では、躍動感まで再現することはできないが、興味深いインタビュイーの例として、第3章に出てくるウメル氏について見ることにしよう。
ウメル氏は2004年に中学校を卒業した後、小売商となり、00年代にわたって、仕事の傍ら、非合法の宗教的な勉強会に参加していた。そこでの学習内容は「商売の公正に関することや母親にはどのように対応しなければならないかといった一般的な内容のものであった」。しかしサラフィーとイスラム過激主義者を同一視する中国当局の意向を受けた「居民委員会によって、住民が集められて、家で集団礼拝をしていないか、断食をしていないか(中略)とチェックが入るようになった」のである。
ウメル氏が亡命に踏み切ったきっかけとは、仕入れのために広州に赴いた際に、通りがかりの漢族に棍棒で襲われ、派出所に助けを求めたものの、警察が「保護してくれなかった」ことである。またちょうどその前後に7・5ウルムチ事件も起こる。こうしてウメル氏は「『ここ』(中国)を離れてムスリムとして生きる道を歩もうと覚悟を決めたのであった」。両親は「行きなさい!私たちを忘れるんじゃないよ!」と背中を押して、5万ドルの現金をウメル氏に持たせてくれた。
ウメル氏は2013年に新疆を出発し、雲南省、ラオス、タイ、マレーシアを経由して、空路でトルコに入国している。「その道中は、パスポートを所持しないままの密航業者の『国際ネットワーク』を頼りながらの壮絶な移動であった」。道中の詳細については、本書をお読みいただきたい。なおウメル氏へのインタビューからも明らかなように、近年におけるウイグル族への迫害の原型そのものは2000年代に既に出来上がっていたと言えるだろう。
その他にも、興味深いインタビュイーとして、第4章に出てくるアフメット氏について触れることにしよう。アフメット氏は1964年に生まれ、80年代の自由な風潮の中で大学生活を送ったが、「友人に勧められてタバコや酒の味を覚える」など世俗的な生活を送るようになった。また計画出産やロプノールでの核実験などに反対して「積極的にデモにも参加した」。そのようなことをしていたにもかかわらず、アフメット氏は成績が優秀だったことから、85年に共産党に入党することができた。
アフメット氏がウイグル・ナショナリズムを信奉するようになったきっかけとは、トゥルグン・アルマス著『ウイグル人』に出会ったことだ。『ウイグル人』は、新疆が古来中国の不可分の領土であるという「『常識』を根底からひっくり返す内容であった」。アフメット氏は大学卒業後、独学でマスターした日本語の能力を生かして、日本人ツアー客のガイドをするかたわら、インターネットを通して、海外在住のウイグル民族主義者と連絡を取り合うようになった。アフメット氏はそうしたウイグル民族主義者の一人に「新聞に掲載された情報やガイド先で得た中国政府の動向の情報を送っていた」。アフメット氏は「世界のウイグル民族主義者たちと志を同じくする『同志』としてつながっていることに、たまらない高揚感を覚えた」。
さらにアフメット氏は、大胆にも観光バスの中で日本人ツアー客を相手に、運転手が日本語を解さないのをよいことに、「中国が新疆をいかに侵略し、ウイグルの本来の生活を奪ってきたか、ウズベキスタンのブハラからクムルまでは、テュルク系民族の領土であったといった内容の『特別授業』を毎度行っていた」。しかし2001年に「特別授業」が発覚し、アフメット氏は息子と妻を残して、クルグズスタンに逃れ、最終的にトルコへ亡命するに至る。アフメット氏はトルコで信仰に目覚めてサラフィーになり、マレーシアでウイグル族の亡命者への支援に携わるようになった。なおアフメット氏へのインタビューからも明らかなように、1980年代や90年代までは、中国当局によるウイグル族への監視は、近年とは比べ物にならないほど緩やかなものだったと言えるだろう。
最後に、本書への注文も一、二付け加えておこう。本書は専門書とはいえ、サラフィー、スーフィー、及び第5章で言及されるワッハーブ主義について、もう少し詳しい説明がほしいところである。ウイグル族にとって、スーフィーからサラフィーになる、ならないことが、どれほど特別な意義があることなのか、必ずしも読者に伝わっているとは言い難いだろう。またサラフィーとワッハーブ主義の関係についても、触れると良かっただろう。
また終章では、ウイグル族のディアスポラ・コミュニティがトルコで軋轢なく受け容れられている要因として、「民族的シンパシーもさることながら、より強い宗教的シンパシー」も挙げられるとしている。ならば、アラブ系の難民もトルコ社会において強い宗教的シンパシーによって受け容れられてきたのだろうか? 最近のシリア難民に対するトルコ社会の排斥は何に由来しているのだろうか? こうした諸点に関しても触れていれば、より説得力があっただろう。
(しばた・てつお 愛知学院大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
