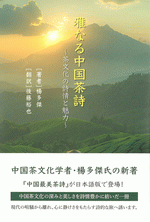龍神村の晒青緑茶
9年ほど前になるが、四国の後発酵茶を見学に行った帰り、突如徳島から和歌山へフェリーで渡った。同行者に「どこへ行くのか」と尋ねると、「和歌山港から龍神村へ行く」と言われて驚いたのをよく覚えている。その村で茶農家を訪ねて、珍しいお茶を貰ったが、どのような味だったかの記憶は曖昧だった。
龍神村についてはその少し前から「晒青緑茶(釜炒り後、天日干しする茶)を作っている」と研究者から聞いてはいた。そして訪問後に「あそこの茶の製法は、広東省河源とよく似ている」とも聞いていた。広東省河源は有名ではないが、確か客家が多く暮らす村。ここの緑茶は客家製法なのか。そうであれば、どのようにその製法は伝わったのか、ずっと興味だけは持っていたが、脚が付いていかなかった。

9年前(2015年)に訪ねた龍神村の茶農家
今回突然龍神村の名前が出て、再度訪問することになったのはまさに茶縁かもしれない。そのテーマは「日本に中国の山岳民族は居なかったのか」という何とも不思議なもの。実は広東から福建の山岳地帯に住む畲族は茶作りに大いに関係があり、彼らが数百年前に日本に渡ってきた可能性はないのか、という調査の一環だった。余談ながら四国に残る土佐碁石茶や阿波晩茶も畲族が中国からもたらしたのでは、と考えておられる研究者もいる。
何故龍神村かというと、その地名が中国を連想するというのは別として、晒青緑茶の生産の他、この付近で作られる豆腐が独特であること、また和歌山県内には「畲野(あらたの)」という地名(人名)がある、という情報があったからだ。豆腐も元は中国雲南省付近から伝播した食品として知られており、茶と似たようなルートで日本にもたらされた可能性もある。
高野山の宿坊で1泊して、翌朝バスで龍神温泉を目指した。この観光バス、乗客は筆者以外全員が外国人で熊野本宮を目指しており、龍神で下車したのは筆者だけ。この地の豆腐に魅せられて18年間、豆腐作りをしてきた小澤聖さんに迎えられた。早速小澤さんにこの地の豆腐の特徴を聞いてみると、「地元の大豆を原料に、地釜を使って薪で炊きあげて作る」という。

小澤さんの豆腐作りの釜
但しこれはこの地独特の製法ではなく、その昔はどこでもこのような作り方だったものが、効率性や機械化により、今や見られなくなってしまったということらしい。実際その豆腐を食べさせてもらうと、少し硬めで何だか懐かしい味がした。「この豆腐が残ったのは、実は山間地で貧しく、外で豆腐を買う余裕がなく、各家が昔からの自家製を維持せざるを得なかったからでは」という言葉にとても説得力があった。
そう考えると、晒青緑茶についても同じことが言えるように思える。江戸時代以前から、この地にはこの製法があったが、幕末から明治にかけて茶が重要な輸出品になると「天日干しの茶は品質が悪く、海外で不評のため生産禁止」のお触れが出ている。その後この地域では蒸し製緑茶である山路茶(さんじちゃ)が隆盛となった。
地元出身で単身アメリカに渡り、土木作業や鉄道工事で資金を稼いだ後藤伴次郎という人物は、海外貿易にも目を向けた商品生産を目指し、養蚕や製茶業に投資、製茶工場なども作ったらしい。だが山路茶も他県の銘茶に押され、大正末年頃にはその姿を消してしまったようだ。
和歌山には新宮の徐福伝説をはじめ、渡来人の話がいくつもあることから、龍神村付近にも渡来人がやってきて、茶を伝えたのでは? 龍神のお茶(ここでは番茶という)について、以前研究会に参加していた竹内雅一さんや正木吉紀さんに聞いてみたが、「龍神村に外国人が来たという話は聞いたことがない」と言う。更に「畲野(あらたの)」という地名(人名)についても、聞いたことは全くないと言い、またこの村でお茶がいつから作られていたかなどの歴史について、資料はほぼないと言われ、調査はここでとん挫してしまった。
龍神番茶の現状について尋ねると、「自家用では各家でまだ作っているが、県外はおろか、近所の道の駅や温泉旅館でも、今や買えないだろう」と言われてしまう。実際探してみたが、「偶におばあちゃんが持ち込んでくると販売することもある」というレアな商品になっていた。
「この地域の年配者には今でも茶粥を食べる習慣が残っており、その材料である番茶の供給がないので、自分で作るしかない」と聞くとなるほどと思う。ただ若者が殆どおらず、茶粥を食べる習慣も受け継がれていないため、近い将来年配者がいなくなれば番茶の生産も無くなるという悲しい現実に繫がっていく。

温泉旅館で出た茶粥
丹生ノ川という場所に、何故かこうろ種のような大葉の茶樹がポツンと残されている。龍神番茶は今ややぶきたなどの品種で作られると聞いたが、この茶樹は一体どこから来たのだろうか。そして丹生という地名、例えば愛媛の石鎚黒茶を訪ねた際も、JRの駅にこの地名があったのは偶然であろうか。やはり謎はどんどん深まり、解けることはないらしい。

丹生ノ川に残る大葉の茶樹
▼今回のおすすめ本
雅なる中国茶詩 茶文化の詩情と魅力
中国茶文化学者・楊多傑の新著『中国最美茶詩』が日本語版で登場!
中国茶文化の深みと美しさを詩情豊かに紡いだ一冊
現代の喧騒から離れ、心に静けさをもたらす詩的な旅へ誘います。
――――――――――
須賀 努(すが つとむ)
1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。
blog[アジア茶縁の旅]