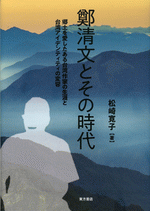
鄭清文とその時代 郷土を愛したある台湾作家の生涯と台湾アイデンティティの変容 松崎寛子 |
文学の「氷山」を愛惜し、慎重に探査する一冊
八木 はるな
鄭清文は1932年に台湾桃園県で生を受けた小説家である。台北商業職業学校と台湾大学商学部に学び、長らく華南銀行に勤めた銀行員作家でもある。1958年の文壇デビューから2017年に逝去するまでに、300篇近い短編小説と、長編小説を3冊、文芸評論集を3冊、童話集を5冊、さらに翻訳作品を多数残した。日本では代表小説「三本足の馬」のほか、童話集が2冊刊行されている(1)。
台湾では鄭は、李喬(1934~、台湾苗栗県出身の作家)と並ぶいわゆる「郷土作家」の代表と目されている。李喬自身は鄭のことを「悲劇の過程」の描写に長けた作家であると評したことがあり、葉石濤『台湾文学史綱』(1987)はこの観点を援用しながら鄭文学の価値を「人間の内面を透視する」点に見出した(2)。他方、陳芳明『台湾新文学史』(2011)では、鄭清文作品に通底する「反英雄崇拝」の思想が説かれ(3)、またヘミングウェイを信奉する鄭清文が、簡易な文体で深遠な意味を示唆する「氷山理論」の実践者であることも広く知られている。
それに対して本書の主旨は、鄭清文文学の読解を通して、台湾アイデンティティを考察することにある。すなわち第一部・第二部の作家論では、小説中の様々な表象を手掛かりに鄭自身の台湾アイデンティティが考察され、第三部の受容論では、台湾アイデンティティ言説の形成に鄭清文文学が果たした役割が考察されている。さらに鄭清文研究として本書が持つ独自性は、世界文学の地図における、そして台湾社会における鄭清文文学の位置づけを明示した点にあると評者は考える。本書は第一部・第二部を通して、ちょうど「西洋の文学の影響が強い」(249頁)という鄭の発言を裏付けるようにして、鄭の文学と、ヘミングウェイ、チェーホフ、カミュ、スタインベックの小説、さらにスウィフト、オーウェル、ルイス・キャロルらの児童文学とのインターテクスト関係を丁寧に解きほぐしていく。第三部では、中等教育とアダプテーションの現場に着目し、今日の台湾で鄭清文がどう読まれるかを明らかにしてもいる。特に第三部からは、鄭清文がいかに現代台湾の「国民作家」的存在たるかということ、台湾における台湾アイデンティティ言説と鄭清文文学の密接な関係が見えてくるだろう。
本書はむろん文学の研究書としてだけでなく、そのタイトルが示す通り、一人の男性台湾作家の伝記としても、また彼が生きた激動の時代を概観する台湾社会論としても面白い。何よりも著者による作品紹介の文章が秀逸で、その自然で的確な訳文と要点を押さえた解説は、誰をしても「鄭清文の小説は面白い」と容易に思わせる効果がある。読者が台湾入門者であれば、本書を通して台湾現代史を学びながら、「台湾人」という言葉が有する重みを知ることができるだろう。あるいは台湾事情に通ずる者であれば、著者とともに鄭の台湾アイデンティティを探求しながら、鄭自身がそのインタビューで語る言葉を自ら咀嚼することで、そもそも台湾アイデンティティとは何であり、「郷土」とは何なのか?「郷土を愛する」とはどういうことなのか?と、あらためて考える契機が得られるかもしれない。今後の展望を多く語る終章を含め、本書は全体で読者の様々な連想や着想を誘ってくれる刺激的な一冊なのである。以下では本書の内容を概括し、最後にいくつか私見を述べて結びとしたい。
第一部・第二部は、あたかも鄭清文が創造した「氷山」の実態を慎重に探査するかのごとく、鄭清文作品が内包するその時代特有の政治的意味を、「台湾アイデンティティ」という観点から照らし出さんとした作家論である。第二章ではまず、鄭清文の出自の特色と、鄭が1960年代に発表した初期小説の特徴が確認される。この時に鄭文学の核心となる「農村」と「旧鎮」という舞台背景、並びに「都市と農村、男と女、老人と青年、近現代と伝統等の二つの観念の対立」(28頁)という小説主題が現れたことが発見される。
第三章では、短編小説「我要再回来唱歌」(1979)を手がかりに、鄭が「歌を歌うこと」に込めた政治的意味が探求されている。ここでは、その前年の作品「女司機」との連続性や「我要再回来唱歌」に登場する台湾語歌謡曲《雨夜花》が示唆する政治的意味、あるいは当時の台湾で台湾語歌謡曲を描くこと自体の意味やこれまでの鄭作品の「音楽」形象全般など、幅広い問題に遡求した議論が展開される。
第四章は、短編小説「三脚馬」(1979)と「蛤仔船」及び「髪」(いずれも1989)、さらに中編小説『大和撫子』(2005〜06)の四作を手がかりに、鄭小説における日本統治期の記憶の表象を分析した章である。前三作は、語り手だった「私」が「物語が本題に入ると……一貫して聞き手の役割に移ってしまう」(63頁)点、及び「主人公と深い関わりを持つ女性も、それぞれスティグマを持っている」(70頁)点で共通しており、前者は「個人の記憶」を「集団の記憶」として語り継ぐことの困難さを表すものとして、後者はいわば「去勢された」台湾の暗喩として読めるという。晩年に著した『大和撫子』も依然として「傍観者」的叙述のままなのは、「鄭にとって、日本統治時代の記憶を集団の記憶として再現し、継承していくことは、民主化達成後の台湾においても、困難であった」(92頁)からだと説明される。
第五章では、長編小説『旧金山──一九七二』(2003)を手がかりに、鄭の「台湾アイデンティティの原点」が探求される。カミュやスタインベックとのインターテクスト関係が見事に実証される本章は、第一部の白眉とも言える。同作の女性主人公は、留学先の米国で深刻なアイデンティティ危機に直面している。彼女はゲイの米国人男性、台湾の外省人女性、レズビアンの白人女性の誰とも「同一化」できなかったが、唯一台湾の本省人男性とは「主体的にセックス」できた。しかしその上でやはりスティグマを持つ祖母の死をきっかけに、台湾の故郷へ戻ることを決意するのである。著者はこの結末に「一九九〇年代、民主化の波にのり、新しく生まれ変わろうとする台湾社会」の影を見て、「台湾アイデンティティ確立のためにも、秀枝は帰台前に、台湾アイデンティティを強く持つ恋人の陳有成と主体的にセックスをして、心身共に彼と同一化する必要があったのであろう」(114頁)と結論づけている。
第二部の第六章・第七章では、鄭自身が「政治童話」と称する児童文学作品の源流が追究される。藤井省三はこの部を「鄭氏が自らの台湾アイデンティティを模索しつつ、ネーションとしての台湾の子供を発見していく過程を明らかにしている」(ⅲ頁)と高く評価している。ここでは、まず初期の短編童話「燕心果」(1982)、「白沙灘上的琴聲」(1984)及び「鹿角神木」(1980)と長編童話『天灯・母親』(1997)の四作を手がかりに、(一)鄭の初期童話は、「海洋文化圏の中の台湾」を前景化して漢民族中心主義に異を唱える、先駆的なエコ・コスモポリタリズム文学であったこと、(二)いわゆる孤児意識やユートピアとは異なる、新たな郷土表象の実践であったことを明らかにした。また、童話集『採桃記』(2004)の分析を通して、「台湾の郷土を回復させるという使命を、台湾の子供たち、言い換えれば台湾の児童に負わせた」(160頁)鄭の姿が浮かび上がっている。
第八章は、鄭清文作品を中心に台湾の国語教科書における台湾文学の扱われ方を整理しながら、台湾アイデンティティ言説の変容について考察した章である。短編小説「我要再回来唱歌」は1999年から2008年にかけて、台湾でも比較的普及率の高い高校国語教科書に掲載されていた。著者によれば、1999年の台湾において、同作の教育的意味は明らかにその女性表象と郷土表象だけに見出されていた。この時の「郷土」という言説に「台湾意識」の色彩はなく、それはまだ背後に「中華民族意識を高揚させる」(186頁)という教育部の意向があったからだという。2005年に教育部の綱要から「中華民族」に関わる文言が消えると、同作の解釈にも「より大きな空間」が与えられ、「教師が……自由に問題を提起し……生徒が自由に討論、発言する」(190頁)ように変化したことが確認される。
第九章は、2010年の鄭清文アダプテーションである台湾語劇『清明時節』(呉念真監督、緑光劇団)に着目し、今日の台湾における鄭文学の位置づけを探った章である。原作の短編小説「苦瓜」(1967)と「清明時節」(1969)はどちらも女性を視点人物とする物語で、夫が不倫した挙句に自死し、未亡人となった妻が、最後には絶望を振り切って堅強に生きようとする姿を描いた小説である。評者が思うに、本章の論点は次のように総括できる。すなわち、六〇年代の原作小説は政治的干渉を免れるために「不倫」という角度から人間の内面を、特に女性の内面を描出せんとした試みだった。それが2010年になると、まずこれが台湾人のノスタルジーを喚起する「六〇年代台湾」の、今日ますます現実味を増した「不倫」の物語である点に観客動員の可能性が見出され、最終的には明白な「緑」(民進党友好)の政治性を帯びた舞台劇へと改編されたのである、と。だがより強調すべきだと評者が感じるのは、このことと「男性不在の中で男の影に怯えながら苦悩する女性の物語」が「苦悩する男性主人公を中心とする物語に書き換えられた」(238頁)こととの表裏一体性である。つまり、著者がいみじくも舞台劇版に対し「愛する男性が自殺し、残された女性二人のうち、まだ精神的に立ち直っていない年齢の若い不倫相手の梨花が七〇年代台湾の大転換期への不安を象徴しているとするならば、彼女よりも年上の妻、秀卿が「彼は今自由よ」と梨花を慰める様子は、やがて勝ち取るであろう民主化への期待を表しているとも言えよう」(229頁)と指摘しているように、六〇年代の女たちの小さな個別の物語──「「重視伝宗接代(先祖代々継承することを重視する)」という観念に疑問を持っていた」(215頁)鄭清文が提示した「家父長制を葬り去り、自ら新しい生活を切り開こうとしている女性」(216頁)たちの物語――が、いつのまにか男たちの大きな政治物語へと変えられたのである。この点にこそ今日の鄭清文受容の重要な特色が現れているのではないかと評者は拝察する。
本書の作家論を読むと、鄭は一貫して「個人の記憶」と「集団の記憶」との差異を見据え、その隙間の物語を描き続けながら、他方でまた祈るようにして台湾の児童に郷土再生の希望を託した作家であったことが見えてくる。そしてその揺らぎこそが本書のいう「鄭清文の台湾アイデンティティの葛藤」なのだろう。しかしその一方で、畢竟、鄭文学における台湾アイデンティティの表象や鄭の台湾アイデンティティそれ自体は、どのような特異性を持つのか?という疑問も残る。そのことを、あるいは大きな歴史的・社会的言説との距離を測りながら、より具体的な言葉で示していただけたらなお有り難かったと思う。この点に関して評者は、先の段落の指摘とも関連するが、やはり鄭清文の女性表象に対する深い考察の必要性を強く感じた。鄭の女性表象をめぐっては梅家玲「時間・女性・叙述──小説鄭清文」(1998)(4)などの先行研究があるが、それに対して本書はいわば、鄭の「女性小説」を「台湾アイデンティティの葛藤」という別の視点から論じ直さんとしたものだと言える。だが著者の企図とは別に、本書は全体を通して、鄭の「女性小説」の特性を示唆する議論に満ちている。たとえば第三章を読むと、鄭は一方で「言語」を超越した芸術として「音楽」を崇めつつ、他方で〈エクリチュールを持たない女の歌〉によって逆説的に自身の「言語」=アイデンティティを省察したのではないか、と想像したくなる。畢竟、台湾社会における《雨夜花》の解釈が「ある女性の悲劇という物語から、台湾の歴史意識へと展開していった」(42頁)という事実は、台湾アイデンティティの確立と〈エクリチュールを持たない女の歌〉の形象との関係性を示唆してはいないだろうか、と。また第五章を読み、女性主人公が本省人男性と「主体的にセックス」できたのは「台湾アイデンティティ確立のために…同一化する」ためというより、むしろ彼をいったん「征服」し、その上でそれよりもはるかに周縁化された、スティグマを持つ祖母に「同一化する」ためではなかったか、だとすれば〈スティグマを有する女性への同一化〉という観点から、鄭の台湾アイデンティティの特異性を考察できないだろうか、などと愚考したりした。
鄭清文の創作の背後にはいつも「台湾への愛」があったと次女の鄭谷苑は述懐しているが(5)、それに倣って言えば、本書には鄭清文という作家とその文学を慈しみ、その「氷山」に隠された声を代弁せんとする著者の愛に満ちている。それゆえだろうか、本書には時に論理が曖昧なまま作者の意図が断定されたり、結論が不明瞭に思われたりする箇所がある。しかし他方でこれが二人の乳幼児を「授乳しながら、そして寝かしつけながら」(270頁)紡ぎ出された、著者の執念と情熱の結晶であると知れば、感嘆せずにはいられず、こうした風格が本書の意義をいっそう高めるものだと評者は確信するのである。
【注】
(1)中村ふじゑ訳「三本足の馬」鄭清文・李喬・陳映真/松永正義ほか訳『三本足の馬──台湾現代小説選Ⅲ──』(研文出版、1985年)所収。岡崎郁子編訳『阿里山の神木:台湾の創作童話』研文出版、1993年。西田勝訳『丘蟻一族』法政大学出版局、2013年。
(2)葉石濤『台灣文學史綱』高雄:春暉出版社、1999年(再版)、131頁。
(3)陳芳明『台灣新文學史(下)』新北:聯經、2011年、559頁。同書の邦訳版は、下村作次郎・野間信幸・三木直大・垂水千恵・池上貞子訳『台湾新文学史 上・下』東方書店、2015年。
(4)鄭清文『鄭清文短編小説精選集四 最後的紳士』台北:麥田出版、1998年、3〜15頁所収。
(5)鄭谷苑「這個人,這一生」『文學台灣』第一〇六期、2018年4月、47〜54頁。
(やぎ・はるな 一橋大学研究員)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
