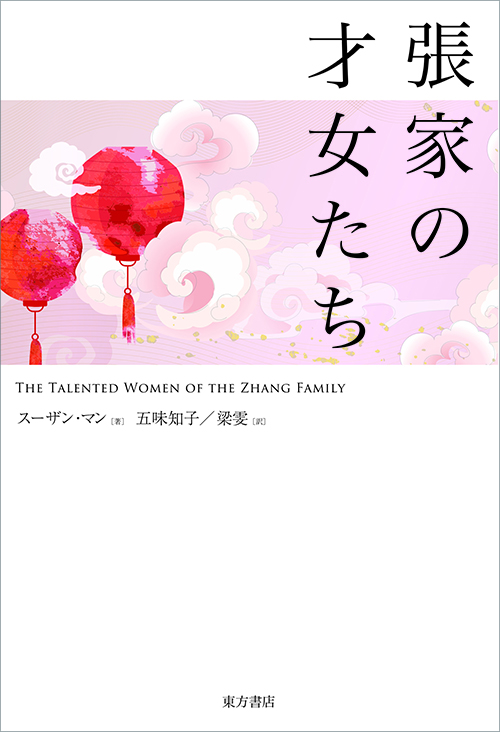
|
明清女性史研究の一里程標
スーザン・マン先生には1993年、イエール大学で開催されたWomen and Literature in Ming-Qing Chinaの会議ではじめてお目にかかり、その後AAS等の機会でしばしばごいっしょさせていただいてきた。いまマン先生のご著書『張家の才女たち』日本語版書評の依頼を受け、改めてマン先生のお仕事を振り返ってみた。日本語版所収の小浜正子先生の解説にも詳しいが、マン先生が最初に世に問われた著書は、1987年に出たLocal Merchants and the Chinese Bureaucracy, 1750-1950(Stanford University Press)である。この段階では女性史への関心は薄いようであるが、この本の内容は『張家の才女たち』の中で、とりわけ張琦と張曜孫の山東、武昌での役人生活の部分に強く生かされている。続いて1997年のPrecious Records : Women in China’s Long Eighteenth Century(Stanford University Press)。1993年にイエールの明清女性文学の会が開かれたように、このころにはアメリカの学界において、中国女性史研究への関心が高まりを見せ、マン先生はずっとそのリーダーたちのお一人である。この書物では、さすがに歴史家らしく、過去の中国の女性の生活をめぐり、その人生行路、著作、娯楽、仕事などについて論じている。この仕事が、本書の横糸になっているともいえるだろう。そして、2007年の本書The Talented Women of the Zhang Family(University of California Press)に至る。具体的な一家族を扱った本書と、その後2011年に出された、より理論的概括的なGender and Sexuality in Modern Chinese History(Cambridge University Press.これには小浜正子+リンダ・グローブ監訳 秋山洋子・板橋暁子・大橋史恵訳『性からよむ中国史 男女隔離・纏足・同性愛』平凡社 2015の翻訳がある)とを合わせて、マン先生にとっての明清女性史研究の集大成として位置づけることが可能であろう。マン先生は、2011年に出版されたBeyond Exemplar Tales : Women’s Biography in Chinese History , edited by Joan Judge and Hu Ying(University of California Press)の中で“Biographical Sources and Silence”と題する論文を発表しておられる。本書刊行の前年、2006年に開かれた学会で発表された論文で、いわば本書の骨格を述べられたものという気味がある。
マン先生は、歴史家ということになるのだろうとは思うが、歴史、文学、美術といった専門の垣根が比較的低いと思われるのが、アメリカの中国研究者一般の特色だと思う。なればこそ本書のように、歴史はもとより、文学、美術にも深くかかわる内容の著作が可能であったといえるだろう。とかく歴史だ、文学だと自身の殻に閉じこもりがちな日本の研究者に、本書が大きな刺激となることを期待したい。
なお、マン先生のご著書のうちPrecious Records : Women in China’s Long Eighteenth Century については、同じ2005年に繁体字中国語訳『蘭閨実録 晚明至盛清時的中国婦女』(楊雅婷訳 台湾左岸文化出版)と簡体字中国語訳『綴珍録 十八世紀及其前後的中国婦女』(定宜荘・顔宜葳訳 江蘇人民出版社)が刊行され、The Talented Women of the Zhang Family には、2015年に簡体字中国語訳『張門才女』(羅暁翔訳 北京大学出版社)がある。ほかにも2021年には、マン先生のご論文の中国語選訳『蘭閨史踪 曼素恩明清与近代性別家庭研究』(盧葦菁他編 復旦大学出版社)が出版されている。
このたび五味知子、梁雯両先生のご努力によって、東方書店よりThe Talented Women of the Zhang Family の日本語版『張家の才女たち』が刊行されたことは、まことに喜ばしい限りであるが、中国、台湾の動きと比べると、遅きに失したきらいもないわけではない。
さて、本書の内容に入ることにしよう。本書は、張家の男性である張琦に嫁した妻(湯瑤卿)にはじまり、その娘たち(張䌌英、張![]() 英、張紈英)、そして張紈英の娘である王采蘋、さらには張䌌英らの弟である張曜孫のもとに嫁してきた包孟儀(包世臣の娘)その他、張家の三代の女性たちについて述べられている「女性家伝」である。が、考えてみれば、女性は結婚して他家に出るのが通例であったかつての中国にあって、「女性家伝」というもの自体、本来存在するはずがないものなのであった。しいていえば、小説や演劇で知られる楊家将物語の中の「楊門女将」のくだりは、楊家に嫁いだ四代の女性たち(当然全員姓がちがう)が女将として敵と戦う物語であって、「女性家伝」といえなくもないが、それとても物語の一挿話に過ぎない。マン先生の本書の新しさはここに存する。そして、本書によれば、常州にあっては、この張家の場合のように、結婚しても女性がそのまま自分の家に住み続け、夫が妻の家で生活する「妻方居住」がしばしば行われたようである。このような家族形成の形がありえたことは、わたしにとっても驚きであったが、こうした形があったからこそ、本書のように三代にわたってともに生活した女性たちの「家伝」を書くことが可能であったともいえよう。
英、張紈英)、そして張紈英の娘である王采蘋、さらには張䌌英らの弟である張曜孫のもとに嫁してきた包孟儀(包世臣の娘)その他、張家の三代の女性たちについて述べられている「女性家伝」である。が、考えてみれば、女性は結婚して他家に出るのが通例であったかつての中国にあって、「女性家伝」というもの自体、本来存在するはずがないものなのであった。しいていえば、小説や演劇で知られる楊家将物語の中の「楊門女将」のくだりは、楊家に嫁いだ四代の女性たち(当然全員姓がちがう)が女将として敵と戦う物語であって、「女性家伝」といえなくもないが、それとても物語の一挿話に過ぎない。マン先生の本書の新しさはここに存する。そして、本書によれば、常州にあっては、この張家の場合のように、結婚しても女性がそのまま自分の家に住み続け、夫が妻の家で生活する「妻方居住」がしばしば行われたようである。このような家族形成の形がありえたことは、わたしにとっても驚きであったが、こうした形があったからこそ、本書のように三代にわたってともに生活した女性たちの「家伝」を書くことが可能であったともいえよう。
女性たちの伝であるからしかたないのだが、夫たちは科挙の受験のため、あるいは遠く離れた地で家庭教師になるなど、長期にわたり家を留守にしていたこともあって、全体として影が薄い。いや、影が薄いというよりも、実際に![]() 英の夫の孫劼は1845(道光25)年、紈英の夫王曦は1847年、䌌英の夫呉賛は1849年と、相次いで亡くなってしまうのである。マン先生はエピローグの章で、外で暮らすことが多い男性たちが早死にした背景についても考察しておられるが、読書人の家の男性として科挙に合格しなければならない、その精神的プレッシャーも、大きな理由の一つだったのではなかろうか。進士になった成功者であるはずの張恵言が、四十そこそこで突然亡くなってしまったのも、同様であろう。影が薄いとはいったが、もちろん清代の文学史で、張恵言にはじまる常州詞派はきわめて大きな存在であり、『詞選』は今日に至るまで広く読まれ、大きな影響を与えている書物である。本書には、そうした文学史の舞台裏を垣間見させてくれる意味もある。
英の夫の孫劼は1845(道光25)年、紈英の夫王曦は1847年、䌌英の夫呉賛は1849年と、相次いで亡くなってしまうのである。マン先生はエピローグの章で、外で暮らすことが多い男性たちが早死にした背景についても考察しておられるが、読書人の家の男性として科挙に合格しなければならない、その精神的プレッシャーも、大きな理由の一つだったのではなかろうか。進士になった成功者であるはずの張恵言が、四十そこそこで突然亡くなってしまったのも、同様であろう。影が薄いとはいったが、もちろん清代の文学史で、張恵言にはじまる常州詞派はきわめて大きな存在であり、『詞選』は今日に至るまで広く読まれ、大きな影響を与えている書物である。本書には、そうした文学史の舞台裏を垣間見させてくれる意味もある。
中国では古くから「夫は外を治め、婦は内を治む」という。例えば仁井田陞氏が、『中国の農村家族』(東京大学出版社 1952)第一部第六章「中国の主婦の地位と鍵の権Schlüsselgewalt」ほかにおいて、主婦の権威を象徴するものとしての鍵に着目されたように、とりわけ一家の主婦が家政において大きな権限を持っていたこともたしかであるし、石母田正氏が「商人の妻」(『歴史と民族の発見』東京大学出版会 1952)において、留守を守る主婦の、夫に対して堂々と自己の主張を述べて譲らない姿を驚きをもって語られたように、かつての中国の女性たちにもそうした一面がなかったわけではない。本書においては、張家の女性たちが、夫の不在という状況のもとで経済的に苦労しつつも、幅広いネットワークを利用しながら、みずからの刺繡や書などの才能によって生活を支えてゆく姿が具体的に描かれる。文化資本としての女性たちの才能は、生活のためにも必要であり、実際それが有効に働いたのである。女性たちの詩集が数多く刊行されたのも、才能の広告としての意味があったのかもしれない。ただ、女性たちの詩集が刊行されることは、明代においてはまれであった。明と清の間にいったいどのような変化があったのか。これも考えてみなければならない課題の一つである。
張曜孫が武昌で官につくと、姉たち、そしてその夫たちまでが、こぞって曜孫を頼って武昌に赴いた。一族の中から成功者が出ると、みんなが彼に頼るという宗族のシステムを如実に物語るものであるが、ここでは張家の兄弟姉妹関係にもとづいて、他姓の夫、さらにはその族人たちまでもがその恩恵に浴している点が注目される。
最後に、本書の中で強烈な印象を残しているのが、早世した長男張珏孫の婚約者、法嬢である。これはわたしの無知無学以外の何物でもなかったのだが、最初に本翻訳を通読したとき、法氏もいちおう婚約はしていたこともあり、「法嬢」の訳語でいいのかどうか、疑問に思ったりした。マン先生の原文は、おおむねMiss Faである(2011年刊行の論文にFaithful maiden Faといういいかたもあった)。ちなみに中国語訳は、少しばかりの「法家小姐」と大部分の「法氏」である。『光緒武進陽湖県志』巻九「旌䘏・節孝」の当該のところには、「(道光)二十八年旌武進(中略)貞女法氏 字張珏孫」とあった。「字」は女子の婚約。「節婦」「烈婦」ではなく、あくまでも「貞女」なわけだから、「嬢」で正解だったわけである。それにしても、『光緒武進陽湖県志』に掲げられている節婦、烈婦、貞女の数はおびただしいものがある。知る限り、多くの地方志では、一人一人行を分けて記載されていたようであるが、この常州の地方志では、紙面びっしり〇氏、△氏、×氏が並んでいる。女性の才能とともに、こうした節婦、烈婦、貞女たちの旌表が常州の宗族を支えていたのかと思うと、なかなか背筋が寒くなる。
このたびの翻訳出版によって、明清女性史研究の一里程標ともいえるマン先生の本書が日本に紹介されたことを喜び、訳者の五味、梁両先生をはじめ、広く翻訳に関わられたグループのみなさまのご努力を多としたい。
(おおき・やすし 東京大学名誉教授)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
