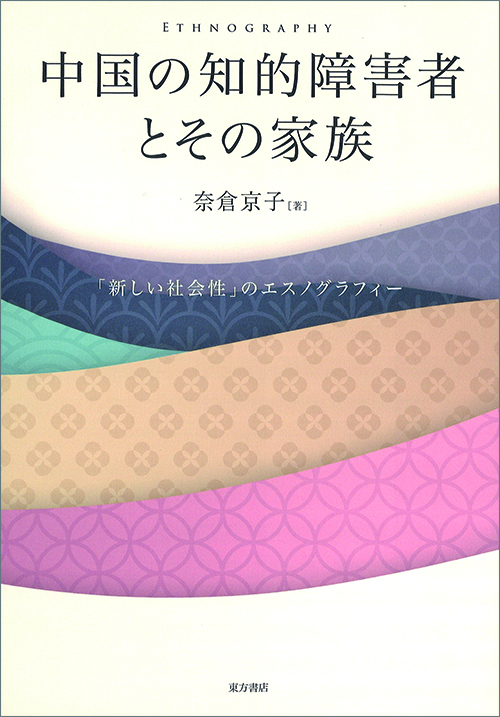
中国の知的障害者とその家族
|
本書は、中国の「ポスト社会主義的状況」における、「個人とその結びつき方」について「草の根の視点」から(p.ⅰ)捉えようとした労作である。そのために着目されたのが、「知的障害者とその家族の生き方」である。
なぜ、障害者に着目したのか。中国政府によって、障害者をめぐる問題は「国際的評価にかかわる集団の問題」と考え(p.ⅱ)られている。そのため、「西側諸国の思想・文化的影響を受けながら、一方で中国共産党の管理と指示に従って行動」(p.ⅰ)した先にある「個人とその結びつき方」を明らかにしようとする本書の課題がよりはっきりと浮き彫りになる対象として障害者が位置付けられている。また、「障害の有無よりも、労働能力の有無が重要」(p.51)とされる中国社会においては、安易に「障害者」全般を対象とすると、社会的「文脈」を十分に捉えることが難しいことが予想された。そのため、「知的障害者とその家族」に対象を絞り、本書は構成されている。
先述した大きな問いに応えるために、第一部において「①個人/家族と国家の中間的領域/組織の役割」、第二部において「②知的障害のある子をもつ家族の生の営み」について考察を行ない、「障害者とその家族の『新しい社会性』とは何かという問いを解明」(p.3)された。
「新しい社会性」とは、「一九七八年に開始された改革開放後、とりわけ当該政策から三〇年が経過した後の中国社会について、(中略)家族や階層を超えて社会関係を築くことのできる社会の性質」(p.1-2)であると、閻雲翔(2009)の定義に基づき示されている。他方、続く閻の論において、「社会が個人を受容するメカニズムが未発達である」中国では、最終的に、人々は再び「解き放たれたはずの家族や私的な関係網へ戻される」(p.16)ことが明示されている。それに対し、本書では、人々が、家族というセーフティーネットに戻されつつ、またそれを経由して、再び「新しい社会性」を見いだしていく生の営みが描かれていく。以下に、その概要を示す。
序章では、本書の背景・課題また調査方法が示される。第一部「中間的領域/組織の役割からみる『新しい社会性』」では、「機構」と呼ばれる「中間的領域/組織」に着目し、知的障害者とその家族に対する「機構」の役割が検討された。第一章では、「政府の障害観」が、行政資料を参照することで明らかにされた。第二章では、中国的ソーシャルワークである「社会工作」と「機構」がどのような関係にあるのかが整理され、両者は「社会の力」を発揮するための協働関係にあるものとして位置付けられた。第三~五章は、政府との距離が異なる3つの「機構」を対象とし、その役割と「新しい社会性」との結びつきが描き出された。たとえば、小学校に通うことのできない脳性麻痺のあるZさんが、少し年上で精神障害のあるSさんに、勉強を教えてもらうという場面が描かれ、「機構」のユーザーである障害当事者が、社会関係を編み直していく様子が捉えられている(第三章)。
第二部「障害者家族の『新しい社会性』」では、他者との関係や社会とのつながりの回復・調整がどのようになされているかについて、知的障害者家族(母親・父親・祖父母)の語りが検討され、主に「家族回帰」の「ゆらぎ」が論じられた。第六章・七章では、母親が「中間的領域/組織」とのかかわり、また、自らの職業キャリアを追求することを通して、「障害者の母親」ではなく、一人の母親として、自らを意味づけていく姿が記述されていた。第八章では、中国家族に特徴的である、障害者ケアに対する「祖父母の関わり」に焦点が当てられた。中国でのジェンダー規範の複雑性と、「中間的領域/組織」への関与を通じた、家族ケアへの意味付け直しが論じられた。第九章では、第八章までの対象者と異なり、幼少期に「中途障害」を負った子をもつ母親の語りに焦点が当てられた。父親の障害や貧困等の問題とともに、「中間的領域/組織」の役割やあり方が母親の視点から検討された点に特徴がある。終章では、「家族回帰」が、既存研究における「終始全面的に依存する行為が繰り返されるという消極的な意味合いのもの」(p.227)ではなく、「閉鎖的な『家族回帰』から、外へ開放していく通過点としての『家族回帰』へ変わりつつある」(p.227)ものとして提起された。そしてそれこそが、障害者とその家族の『新しい社会性』のありようであるとして本書が結実された。以上の各章より、評者がとくに考えさせられたことを以下に述べる。
第1に、「家族回帰」を「通過点」として捉えた点にある。本書においても参照されていた、日本の障害者家族研究では、支援費制度から現在に至る、大きな制度が整えられてきたにもかかわらず、ケアを担い続けてしまう母親の自明性が問い返されてきた。そして、「与えられた」ジェンダー規範に呪縛され、ケアを担い続けてしまうような「母親像」が描かれてきた。しかし、著者も述べるように「障害者の母親」といっても、人として、さまざまな側面を持ちうる。また、「ケアを担い続ける」行為自体も、そう単純ではなく、ケアを社会に委ねたり、また、引き取ったりといった動きのなかで、「担い続け」ている面もあるだろう。本書が、「家族回帰」を「通過点」であると論じたことは、家族ケアラーが、能動的にケアを担う存在であることを明らかにしたという意義をもち、その学術的インパクトは、実はとても大きい。
また、そればかりでなく、家族の「揺れ動き」を、“第三者の関わり”において描きだす研究設計によって、知的障害者こそが——受動的ではなく——主体的な存在であることを明示することに寄与したという意義ももつ。家族に守られなければ生きていくことのできないと思われてきた知的障害者こそが、自らの意思で、誰と繋がるのかを決められる主体であると明らかにすることにつながるのだ。たとえば、先述した「機構」と繋がり、「新しい社会性」を見出したZさん(第三章)や、「幼稚園を転園させたことで、幼稚園に馴染めず情緒が不安定になってしまった」(第八章)楊明さんの行為からは、なにものにも代えられない当人の意思の現れを文章で確認することができる。障害者運動などを公に行なうことが困難である中国においては、さらに、大きな意味を持つにちがいない。
第2に、本書が「語りがたく」・「描きがたい」ことについて詳細に明らかにしている点を取り上げたい。本論の最後の章タイトルにある「混沌」(第九章「『家族回帰』と中間的領域/組織のはざま——混沌と期待を語る母親」)という言葉に象徴されるように、本書では、全章にわたり中国の知的障害者をめぐる人々のアンビバレントな心の「揺れ」と出来事が中国的な障害観とともに包み隠さず綴られている。
中国の場合、女性が生産労働に従事し始めた社会主義建設の背景から、社会のなかに障害者の居場所を作らんとする動きがあった(p.46)。一方で、いまだ「母嬰保健法」や「婚姻法」では優生優育思想(p.59)が明白である。障害者とともに生きる人々の「混沌」とした語りの背景にはさまざまな中国的障害観がある。
日本国内に目を向けても、その程度は異なるが、人々が、“お茶を濁さざるをえない”状況に置かれることが多々ある。高齢者福祉において2019年に策定された『認知症施策推進大綱』には、相反するともいえる「共生」と「予防」という2つのキーワードが共存している。障害においても、自身や家族の障害を受け入れ、権利を主張しながら、リハビリテーションに励むことはよくあることだ。「ホームレス自立支援法」に関しても、「相模原事件」をめぐる世間の反応に関しても、話せば話すほどに、「混沌」とした状況に自らを引きずり下ろさなければならないことで溢れている。
では、なぜ、このように著者には語りを収集することが可能となったのか。評者は、著者が、障害者のきょうだいでありながら、「外国人」(p.31)であったからだと考える。本書の冒頭では、「ポジショナリティの問題」が、反省的に述べられていたが、「異質であるが親近感のある外国人」(p.31)としてその土地へ「外から」入ることのできた著者でなければ、このような人々と「語りがたい」ことを話し、さらに「描きがたい」ことをダイナミックに描き切ることを可能にし得なかったと思うのだ(評者も知的障害者のきょうだいであるが、母国の調査では、調査協力者にとって「親近感のある」他者になることが精一杯であろう)。その意味で、本書をライフストーリーという手法に位置付けた点も高く評価されるであろう。
末筆ながら、驚くべきことは、本書の大部分をなす質的データが、中国語を使用した調査を行ない得られていることである。ふさわしい土地(蘭州市)を選び、一からアポイントメントをとり、調査に臨まれているのだ。日本で生まれ育った著者が異国で成し得た功績は、強調してもしすぎることはない。
(そめや・りなこ 法政大学・日本学術振興会特別研究員PD)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
