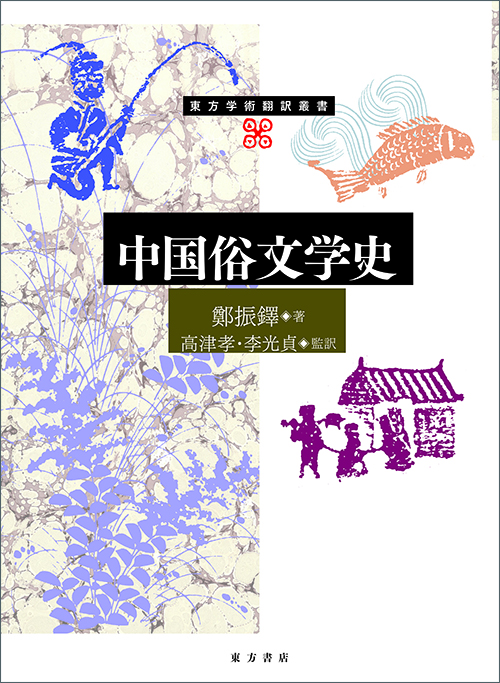
|
中国の文学は、二十世紀以降の現代文学を除けば、それ以前のものは、文言詩文を主とする古典文学と、白話小説、戯曲、講唱文学(韻文と散文による語り物)、民歌等の俗文学に大別される。ただし後者は伝統的にはいわゆる大雅の堂に登らざるもので、正式の文学とは見なされなかった。それが文学の仲間入りを果たしたのは、二十世紀初頭、西洋文学の影響による文学革命以後のことである。うち真っ先に取り上げられたのは白話小説と戯曲で、これは西洋文学ではこの二つが主要なジャンルであったことからすれば当然であろう。本翻訳書の原著である鄭振鐸『中国俗文学史』(一九三八)は、その二大ジャンルを除いた講唱文学、民歌、民謡等をもっぱら対象とする。それは一つには、それ以前すでに王国維『宋元戯曲考』(一九一五)、魯迅『中国小説史略』(一九二五)の専著があり、また鄭振鐸『挿図本中国文学史』(一九三二)でも小説、戯曲は扱われていたからであろうが、『中国俗文学史』は、俗文学にとってより重要で、かつ一般の認知度も低かった講唱文学等をはじめて本格的に紹介、概説することで、従前の空白を埋めた点に大きな意義がある。全書は、俗文学の定義を述べた第一章、『詩経』、漢代詩歌、六朝楽府等、従来の古典文学の中から俗文学的な作品を選んだ二、三、四章、当時発見されて間もない敦煌文献の民歌、俗賦、変文を紹介する五、六章、宋金代の萌芽的演劇である雑劇と諸宮調等の講唱文学を扱う七、八章、元代雑劇曲辞と同形式の散曲および明清代の民歌、宝巻、弾詞等の講唱文学について述べる九~十四章からなる。これによって中国俗文学の主要部分である民歌、講唱文学の全貌とその諸形式、および時代による変遷をほぼうかがうことができるであろう。
この本のもう一つの特徴は、一般の文学史に比べ、扱う作品の原文がはるかに大量に引用されていることである。章によっては大半が作品原文の引用で占められ、文学史的な解説以上に作品の紹介に重点が置かれている。これは当時新発見の敦煌資料や大収書家であった鄭振鐸自身が所蔵する宝巻等、今日と異なり多くの作品が一般はもとより研究者にとっても容易に目睹することができない文献であったためであり、当時としては時代的意義があったと言えよう。
評者は当初この書評の依頼を受けた時、これら大量の作品原文の引用をすべて翻訳することは無理だろうと予測した。引用された作品の多くにはテキスト、用語等にさまざまな問題があり、正確な意味を知ることが困難で、かつ日本語訳や参照すべき文献も乏しいからである。しかしその予測に反して、ほとんどの作品が翻訳されていた(省略された作品の一部は中国側の指定によるという)。しかも原著の引用には、草創期のものであるだけに多くの不備や誤りがあるが、本書では、もとより各章の訳者によって繁簡精粗の差はあるものの、訳注でおおむね最新の研究成果による補正がなされており、かつ各章末尾の「訳者解説」では、これまでの研究史や現在の研究状況が過不足なく述べられている。このような補正は、初期の研究であることを自覚していた著者の鄭振鐸自身が強く望んでいたことでもあった。引用の原文がないため、もとの文体を知りえないのは遺憾だが、それを望む読者は原著と対照して読めばよいであろう。
こうなってみると、原著より本書を読む方がはるかに有益ということになる。中国には原著にこのような補正を加えたテキストはいまだにない。本書を参考にした原著補訂版の刊行が望まれよう。また今後、日本語以外の外国語への翻訳にも本書は重要な価値をもつに違いない。昨今中国政府の政策により、中国側の関与と資金援助による中国学術書の翻訳出版が相次ぐ。本書も二〇一八年国家社会科学基金中華学術外訳項目による出版である。それらの成果は、総じて玉石混交の感なきにしもあらずだが、本書は間違いなく最も良心的で学術的価値の高い翻訳出版である。わずか一年で、これほどの作業を成し遂げた高津氏をはじめとする訳者諸氏の労苦を多とし、満腹の敬意を表したい。
最後に評者の感想を一つ記す。俗文学とは何かについては、中国でも異なる意見がある。定義は著述目的によって適宜定めればよいので、その問題には深入りしないが、鄭振鐸が冒頭で、「俗文学とは通俗文学であり、民間文学であり、また大衆文学である」、さらに宮廷や士大夫ではなく「大衆が好み喜ぶもの」と、「大衆」という語を繰り返し使っている点に注目したい。この「大衆」は、鄭氏が『中国俗文学史』の執筆を開始した一九三四年に上海で起こった大衆語運動とおそらく関係があるだろう。大衆語運動とは簡単に言えば、文学革命以来の白話文体が、欧化文体の多用等により大多数の民衆から乖離してしまった反省から、真に大衆が用い得る口語文体の確立を目指した運動である。それは白話文学の範囲をさらに拡大深化させた『中国俗文学史』とも軌を一にするものであった。大衆という言葉はむろん古代からあり、また仏教でも広く用いられたが、それが思想的な問題意識を帯びて使用されたのは、この大衆語運動がおそらくはじめてであろう。ではなぜ「大衆」なのか。
有馬学『「国際化」の中の帝国日本』(中央公論新社 二〇一三)によれば、日本では一九二〇年代にmassの訳語としての「大衆」の使用が急速に広まったという。中国の「大衆」は、この日本での使用の広まりに連動するものではないだろうか。日本で「大衆」が広まったのは、当時の日本社会が西洋のような階級社会ではなく、階層間の流動の多い社会で、「大衆」というやや曖昧な用語が適していたためであるという。それを言うなら、近世以降の中国は、日本以上に階層間の流動の激しい社会であった。簡単に言えば、科挙に受かり官僚となった士人が支配者、それ以外が被支配者で、両者の間には歴然たる懸隔があった一方、科挙に三代続けて合格するのは至難で、階層間の移動は頻繁であった。その結果、階層間の交流、融合が進み、中間層とでもいうべき階層が生まれる。白話小説等いわゆる俗文学の担い手と読者は、実はこの中間層に他ならない。それを士大夫の古典文学と民衆の俗文学に二分したのは、文学革命当初としては時代的必然性のあることであったろう。しかし現在の時点で考えると、その歴史的使命はほぼ役割を終え、むしろ厳密に二分したことの弊害が出ているように思える。卑近な例を挙げれば、中国文学の専攻者は、昨今の専門の細分化の風潮もあり、当初から現代文学、古典文学、俗文学に分かれ、前二者の専攻者は『三国志演義』や『水滸伝』ぐらいは読むかもしれないが、本書で扱われる分野にはおおむね無知で、かつ読まなくともよいと考えている場合が多いように見受けられる。その偏向が知らず知らずのうちに個々の研究の性格を歪め、さらには研究全体の停滞を招いているのではないだろうか。そういう意味では、本書は時宜を得た出版であると言える。本書を一つの里程標として、今後、中国文学の新たなパラダイムの模索がはじまることを望みたい。
(きん・ぶんきょう 京都大学名誉教授)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
