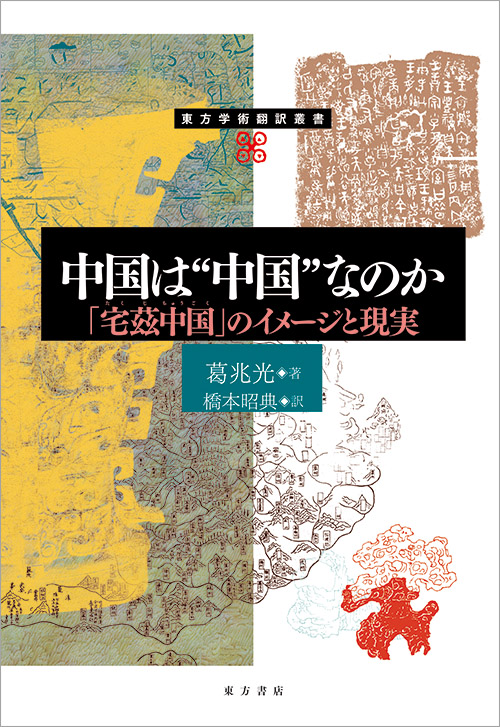
|
本書の原タイトルは「宅茲中国」(ここ中国に棲まう)という。翻訳タイトルの「中国は“中国”なのか」は、著者の葛兆光氏が本書を通じて挑み続けた問いを的確に表した巧みな名付けであり、訳者橋本昭典氏の苦心は高いレベルで報われている。
「中国は“中国”なのか」と問うことは、今日どのような想像を喚び起こすだろうか。中国という国のあり方が普遍価値からの逸脱であるとする警戒と危惧の声が「近代的普遍」の代表を任じてきた西洋から挙がり、日本にもそれに同調する空気が瀰漫している。だからこそ、この問いは否が応でもわたしたちを敏感に刺激する。しかし、「わたしはずっと、もとはヨーロッパの歴史からもたらされたものである描写方法を普遍的な歴史の統一的尺度とすることに強く反対してきた」(23ページ)とあるとおり、本書が求めているのは「普遍の描き方」に対する反省である。したがって、いまの空気に疑義を投げかけることが本書の問いを引き受けるために不可欠な態度であると言える。
今日、世界で次々に生起する新しい現実は、「普遍」だとみなされてきたものを脅かしている。しかし相対主義の虚無に陥ることなく、人類の幸福のためにわたしたちがしつこく「普遍」を求め続けなければならないのもまた自明だ。そうであれば、揺らぎつつある「近代的普遍」にすがりつくことでかりそめの安寧を得るのではなく、どこかに新しい普遍へと続く希望の道を見出さねばならない。「中国は“中国”なのか」という問いは、要するに、「普遍は“普遍”なのか」というもう一つの問いと表裏をなしている。
葛兆光氏は、普遍を装うもろもろの価値が形成されてきた歴史的経緯を問うている。その経路が「中国」であることは、単に著者が中国人であるからではない。「中国」が歴史のある時期まで「普遍」をみずから代表してきたからである。そして、このことと日本は無関係ではない。日本の近代化は「中国は“中国”なのか」の問いと共に進められてきた。琉球処分から始まって、日本の対外拡張は中国とその周辺を削って己のものとしながら進んできた。台湾植民地化、二十一か条要求、「満洲国」建国、「国民政府を対手とせず」、汪精衛政権などの親日政権や傀儡政権との関係強化などなど。これら一連の歴史を進めてきたのは長期にわたる日本からの一方的な侵略戦争であり、それを支持した学問と思想の狡智であった。本書は周辺からの視座によって「中国」とは何かを考えようとする。そうである以上、その周辺をめぐって角逐してきた近代日本は、本書の問いを複雑にする当事者である。
「中国は“中国”なのか」という問いに対する葛氏自身の基本スタンスは、「中国」が「漢族の中国」として保たれてきた歴史の連続性や文化同一性を認めるというものだ。葛氏は中国には一貫して「漢文化」があり、それが中国性の中心となってずっと存続してきたという。近代的な国民国家(ネイション・ステイト)が西洋で生まれる前からそうだったのである。より具体的には「東洋的近世」を画した宋代からは擬似民族的な統合の核が今日まで保たれていたと著者は考える。もちろんその後の歴史は単線的な民族国家史ではない。中国においては「国家」が「帝国」から生まれたのではなく、両者は相補うように包摂しあってきたのだ。こうして葛氏は国民国家を自明の前提とする近代的歴史叙述のありかたそのものを別の方向に転換すべく、中国がヨーロッパとは異なる史的構造を有していることを説明しようとする。しかし、そのための概念装置として依拠するのが「漢族」概念であるのは、ことの難しさを示しているだろう(念のため葛氏に代わって付言しておくと、「漢族」という呼称は中華人民共和国以来の民族識別政策によって登場したものなので、厳密には「漢人」と言い換えたほうが無難ではある)。北は東北三省から南は広西や海南に至るまで、言語も習俗もきわめて多様な人々が自らを「漢人(漢族)」だと認識している事実そのものの複雑さと多様さについて、本書は論じてはいない。ヨーロッパ全体にほぼ匹敵する広大な領土に住む人口の90パーセントあまりが漢族であるという事態は、いかように理解すればよいのだろうか。この一点を取っても「ヨーロッパの歴史がもたらした描写方法」を「普遍」的であると受け入れることの限界は明らかだ。
本書が扱うのは、宋代以降における中国の自他認識や世界観の変遷であり、その変遷をもたらした他者との接触の歴史である。北方民族の南下を所与の世界現実とした宋代における「中国論」と「正統論」の成立、元代から明代にかけて広がった異域との交流が生んだ域外怪異譚の数々、イエズス会宣教師がもたらした地球的世界認識などは、「自己を中心として四方の夷狄を見おろす「天下」」(67ページ)という見方を徐々に揺るがし、世界観は「イメージの天下」から「現実の万国」へと変わっていく(99ページ)。さらに、清朝の成立は周辺の中国観を変質させ、東アジアにはヨーロッパとは異なる特有の地域意識が形成されていく。朝鮮や日本は中国に代わってみずからを「中華」であると認識するようになり、自分こそが古代中華文明の理想像の正しき継承者もしくは保存者であると主張する。東アジアの「崩壊」過程である(182ページ)。ここには東アジアの歴史が「ヨーロッパの歴史」と異なっていることを歴史的に明らかにしようとする葛氏のモチーフが端的に表れている。東アジア海域は海路が多民族を結び合わせた点で地中海と同様だが、そこにはキリスト教のような「国家と皇帝権力を超越してアイデンティティを築く基盤」となる宗教はなく、その結果、「さまざまな民族や宗教、言語の境界が移動をくりかえし、それによって相互に混淆し、衝突を起こすような空間」にはならなかったのである(292ページ)。
中国が周辺の再定義を試みながら困難な体制転換の途にあった19世紀末から20世紀の初めにかけて、日本ではアジア主義が勃興する。アジアという「イメージの共同体」は「アジアは一つ」や「同文同種」のような「まぼろしのアイデンティティ」を生み、それは日本侵略によって「激しい反抗と拒絶」を引き起こす(206ページ)。そして、このような事態をもたらしたのは、「過去の中国の「天下の中心」というイメージの歴史の影響、そして当時の日本の現実の「覇道」や「覇者」という脅威の存在」(207ページ)に他ならなかった。著者は厳しく問い質す、「それなのにどうして「アジア」などというアイデンティティを真にもつことが可能であっただろうか」と(207ページ)。
日本は東アジア海域以外の地域においても周辺の再定義に介入した。東洋史学がそれだ。この帝国的学知は、漢人中国の周辺にある「満蒙回蔵鮮」のすべてを中国とは別個の実体として把握しようとしたのである。もちろん中国国内においても辺疆研究は活発に展開された。それは中華中心の「天下」イメージが世界観の基礎に置かれ続けてきた長い歴史から、「激しい反抗と拒絶」によって新たな国家像へと転換するプロセスにおける自己イメージのパラドキシカルな揺らぎの表れでもあるだろう。これは今日に至ってもまだ解消されることがないどころか、新しい歴史条件のなかで新たな問題を構成している。中国は解けない難題をうちに抱えながら、近代的国際関係の秩序との折り合いを模索し続けているのだ。
パラドクスはつねに周辺において顕著に表れる。それは、ユーラシア大陸の内奥で今日生じている軍事侵略、つまりロシアによるウクライナ侵攻においても同様だ。周辺は領域を輪郭づける。しかし、その輪郭は常に曖昧であるがゆえに緊張を孕む。そこには普遍的な正しさだけでは説明のつかない力が重たく作用している。それだけに、相対主義に陥ったとたん力だけが正当化されていく。皮肉なことに、近代文明の根底に力が一方的に正当化される現実を見出したのもまた、葛氏が批判するアジア主義であった。ならば、わたしたちはどこに普遍の基準を求めていけばいいのだろうか。
本書が周辺から中国を考えることは、中国性の中心にある力に対する内省を否応なく要求する。それは中国の読者に対する要求であるだけでなく、葛氏自身の歴史家としての自らに対するきびしい要求でもあり、わたしはそこに葛氏の懊悩をすら垣間見る。
翻って、本書の問いを受けとめるわたしたちはどうだろう? 歴史の内省は、今日の状況に対するわたしたちの姿勢につながる。であるならば本書とともにこの問いを問いながら、わたしたちがなすべき内省はもはや明らかである。日本が力に頼って周辺を弄ぶ歴史をかつて演じたことをくり返し再確認すること。それは、中国とともに平和を築く礎になるだけでなく、ユーラシアの、そして、人類の平和を希求する重要な第一歩である。
(いしい・つよし 東京大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
