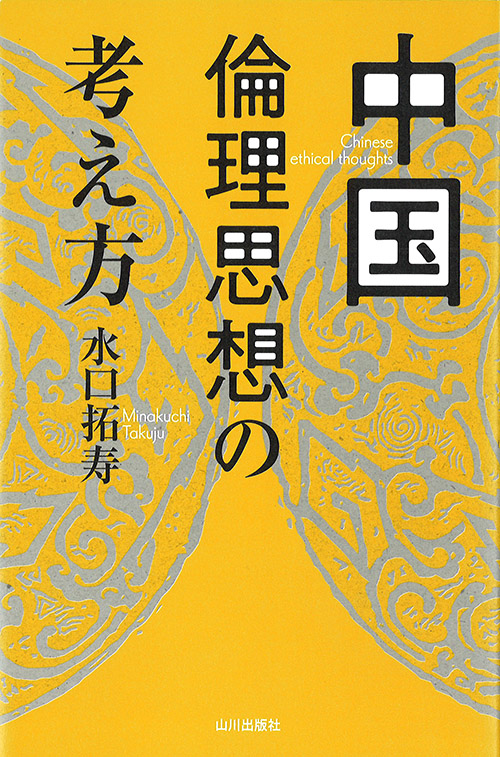
|
まず「はじめに」において、ここで扱う「倫理」という言葉について触れられる。ここではethicsあるいはmoralに対応した西洋に由来する意味での倫理を離れ、日本を含む東アジア地域に大きな影響を与えた中国の倫理思想について、特に春秋・戦国から漢の時代に確立された、倫理思想の基盤というべきものに力点を置き、「もっぱら儒教のそれを俎上に載せ」て、紹介していく旨が述べられる。
第1章「倫理を語ったのは誰か」では、周から戦国時代の歴史を概観する中で、倫理を説いた孔子をはじめとする思想家たちについて紹介する。中国の倫理思想の特色は、人と人との関係の上で成立するものと捉えていることであるという。「人と人との繫がりに関して、中国では倫理に加えて法と慣習が、強力な規範の役割を果たしてきた」が、倫理は「内発的で自律的な規範として人びとに共有される」ものであったという。
著者は孔子が理想として描いていたのは、周初の時代の封建制と宗族制であり、その根幹となるのは君臣の関係と父子の関係であると述べる。そして二つの制度の本質を、倫理に基づく人と人との繫がりとして受け止めたのは、孔子の創造によるところが大きく、聖人たち(文王・武王・周公)の智恵と精神は、詩・書・礼・楽を通じて保存されているから、そこから人類最高の叡智を汲み取れるとしたという。
そして墨家・法家・道家など他の学派との関係について触れたあと、儒家は君臣関係と父子関係の倫理をアピールすること、そして二つを有機的に組み合わせることを進めていったとする。漢王朝はこの儒教を国教として特権的な地位を与え、儒教側でも董仲舒をキーパーソンとして儒教の言論を整理し、その後一貫して中国の倫理思想をリードしていくことになった。その後王朝の官僚登用制度は「儒教の理念に基づいて設けられる」ことになったが、この流れは一方で儒教が「王朝権力にまるごと買い取られる」ことでもあった。またオリジナルな著作を世に問うということは禁忌となって、少数の経典への注釈すなわち経学という形で(創)「作」を進めていくことになったとする。
第2章「儒教の倫理として何が求められたか」では、「孔子とその後継者たち」によって説かれた儒教倫理の内容について述べられる。中国の倫理が人と人との繫がりの場で発揮されるべきものと捉えられていたことは、第1章ですでに言及されているが、孔子はその場を「親族組織」と「王朝統治下の社会」の二つに分けたとし、前者では孝と悌が主であり、後者では仁・義・忠・信の四つとする。孝・悌について考察した後、仁という倫理について、それが「自己の尊厳を十分に認めるところから出発」し、相手も「正当な判断能力を具え」ていることが前提となっていることが述べられる。また智については、仁義、孝悌、忠信とは同じカテゴリーでとらえることはできないとし、「それらが倫理という規範であるために不可欠なメタ倫理」として位置づけられる。
この辺りは儒教倫理を構成する諸概念をテンポよくわかりやすく説明し、それら相互の関係についても触れている。ここで儒教の倫理思想が「父であり夫であり兄であり、かつ君主である者が、最も得をするようにできていた」として、その不平等な性格を指摘しているが、これは第5章に繫がっていく。そして「儒教のなかにあって、一人ひとりの人という存在は、さまざまな対他的・倫理的役割を有する多面体としてとらえられ」、「個々の繫がりに即して父らしく、夫らしく、臣下らしく生きること」が求められたと総括する。
次に『荀子』から『孝経』、『大学』に見える忠の概念の変質や、孝との関係について論じていく。忠の「自己の心情を裏切らないという根幹の部分は変わらないが」、「臣下が君主に服従し、奉仕するという場面の限定と、方向性の限定」が加わった。これは戦国時代になって郡県制に切り替わり、「有能な臣下を繫ぎ止めるための倫理」が必要になったためであり、『孝経』が孝と忠を有機的に接続するという課題を担ったのだとする。しかし必ずしもうまく接続しない場合もあったとして、そのような例についても論じている。
さらに朱子が仁によって孝・悌を基礎づけ、「人の本性として心に具わった仁を、孝・悌として具現する」としたことを論じ、朱子学者たちが風水を儒教思想によく親和するかたちに組み立てなおしたことに触れるが、このあたりは著者の『儒学から見た風水』(風響社,2016)の成果を踏まえてもう少し詳細に述べてほしかった。
第3章「儒教の倫理は何によって表現されたか」では、まず孔子は倫理を表現する手段を、礼・楽に求めたとする。礼・楽は、孝・悌や忠といった倫理を、宗族や社会の中で、自身の地位や互いの上下・親疎に応じて表現していく手段であり、孔子は倫理思想における礼・楽の位置づけ、宗族・社会のなかでの効用を論ずることに力点を置いたという。儒家が礼の専門家として捉えられていたことはよく知られた事実であるが、著者は倫理を表現する手段とするだけでなく、礼によって倫理を涵養するという二つの方向でとらえ、「克己復礼」という言葉を後者の意味でとらえている。
そして葬礼の際に、死者と自分との親等などによって服喪の期間、喪服の種類が決まる五服の制などを例に挙げ、それに過不足なく従うことが重要であったとし、孔子・孟子・荀子そして『孝経』の礼に対する考え方を紹介していく。次に儒教が国教化されてから、礼に関する学問である礼学が成立した過程、また宋代になって『司馬氏書儀』や『朱子家礼』など著者の言う私礼が成立した事情を説く。
そして徳治と礼治の関係として、徳治の実現手段として位置づけられたのが、「礼を通じて人びとの内面に恥の意識を芽生えさせ、これによって彼らのあいだに秩序をもたらす」すなわち礼治であるとする。この君主の教化を効率的に進める役割を果たすものが学校教育であり、公立学校の太学、私立学校の書院さらに郷約などが触れられる。この後、聖人になることをめぐる朱熹や王守仁の説、礼と法を結び付けた荀子の説などが検討され、「礼も楽も、倫理の表現と涵養、そしてうえからの教化というテーマのもとで議論が進められた」という総括がなされる。
第4章「儒教の倫理思想はなぜ正しいとされたか」では、儒教倫理の正当性、普遍性をどのように証明したかが論じられる。孔子は過去の聖人の教えを単に述べたものとしており、それが天に由来するということに頼ったのだとする。著者によれば孔子の時代にはこれでも充分に通じたのであるが、次の戦国時代になると、諸子百家のライバルたちとの争いの中で、どのように自分たちの倫理思想を論理的に証明するかが問題となってきた。
それらの中で、孟子の性善説とは、本性の全体が善というわけではなく、倫理に向かう善なる性質が存在するとしていたが、『孝経』や『中庸』になると、本性が善なる性質を帯びて心に宿るということに一本化されてくるという。一方性悪説を唱えたことになっている荀子も、「倫理的な要素と欲望追及的な要素が共存」しているとすることは孟子と変わらないとする。儒教の国教化後、その倫理の正当性・普遍性は王朝によって保障されることになったが、この後主流を占めたのは性三品説という第三の考え方であった。しかし宋の時代になると、儒者たちは善の実現をめざして、一人ひとりが心の制御に努める権利と義務や、聖人となる可能性を君主の側から取り戻し、君主とともに教化する側に位置づけなおすようになる。
朱子学の性善説を論じたところでは、天から与えられた本然の性は、気質の性に左右されることはあっても、本質的には善であり、それが理である。このことは性・情を含む心全体を善であり、理とした王守仁と異なっていても、性善説に沿っていることには違いはないという。国教化してから千年以上を経て、儒者たちは儒教の倫理思想が正しいか否かという問いには向き合わなくなっていた。経典に基づいてどのように正しさを保証できるかという問題に、争点を閉じ込めてしまったと著者は述べる。
第5章「儒教の倫理思想は皆の幸せをめざしたか」、ここで論じられるのは儒教の倫理思想の負の面である。著者は「宗族や社会一般に然るべき倫理が回復され、人びとが抑圧や疎外にみまわれなくなることを」幸せと呼んでおくとしているが、一般に言う「幸せ」の概念とはかなり異なり、そもそも「倫理は皆の幸せをめざすものなのだろうか」という疑問も引き起こすので、章名には多少の違和感を覚える。しかしここで論じられる内容は明解である。章の終わりの方で邵雍の言葉を引き、彼が「中国人・男性・士人」等のアイデンティティに満足を表明していることに対し、儒教の倫理思想は彼らに有利に作られていたから当然であるが、この章では「その幸せだった人びとから、意図的あるいは無意識に」抑圧された人たちの状況を語っている。すなわち優越集団の人たちが自分たちのために作った倫理思想が、劣等集団の人たちにどのように働いたかを、つまり女性・庶民・夷狄が、どのような不利益を被らねばならなかったかについて論じている。
時代の思想がどのようにその時代の社会状況を反映しているかという問題は、各時代の思想史が取り組む課題の一つといえる。著者は「おわりに」において、各時代の思想家たちが同時代の人びとに語りかけたことを、「思想史という一枚隔てた視座から受け止めて」くれるように願うといっているが、そのためには彼らとその思想を受け止めた人びとが存在した中国という社会の特質について、著者がどのように捉えているかということを、もう少し述べていただきたかった。
全体として、議論はわかりやすさに力を置いており、文章も大変に読みやすい。その点では中国倫理思想の入門書・教科書として優れているといえよう。
(まつもと・こういち 筑波大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
