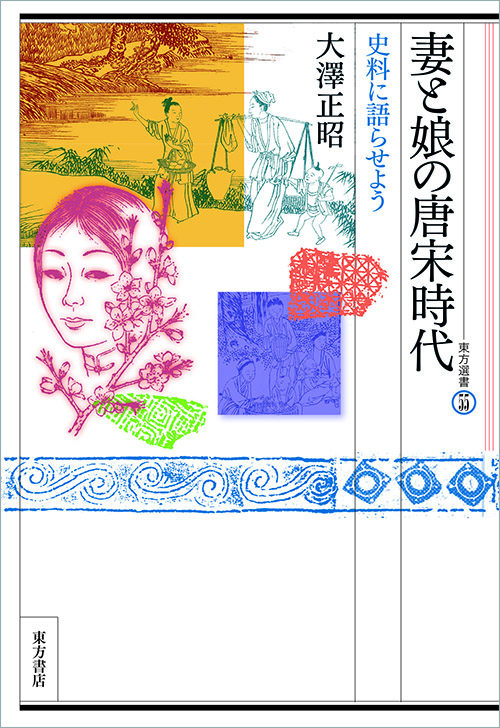
|
多彩な史料から窺い見る、主張する〈悍婦〉たちの世界
本書の著者大澤正昭氏は唐代藩鎮研究から出発し、唐宋時代を中心とする農業史・農書研究の分野で豊富な成果を世に問うてこられたことはよく知られるとおりである。近年はまた、訴訟社会としての前近代中国史像を鮮やかに提示し、その素材である裁判史料あるいは小説史料などから唐宋の女性・家族の実態に迫ることにも力を入れられている。本書はそれらをテーマとする近年の著作(前者は『主張する〈愚民〉たち:伝統中国の紛争と解決法』(角川書店、1996年)、『南宋地方官の主張:『清明集』『袁氏世範』を読む』(汲古書院、2015年)、後者は『唐宋時代の家族・婚姻・女性:婦は強く』(明石書店、2005年)等)の流れを汲みつつ、史学科新入生や社会人といったより幅広い層に向けて書かれたものであり、「唐宋時代の女性史、家族史、とくに妻と娘の生き方の問題」(本書ⅰ頁)を分かりやすく示すこと、および「彼女らに関わる当時の史料の紹介」(同前)に重点を置いている。本書とテーマが大きく重なる『唐宋時代の家族・婚姻・女性』に比較すると、本書は一般書としての工夫が際立つ。語り口の簡潔平明さはもちろんのこと、古代中国史や現代中国社会に馴染みが薄いかもしれない読者の関心をいざなうための身近な話題や映画情報の紹介、さらには著者の大学院ゼミやコミュニティ・カレッジ講座における生き生きとした史料解釈の共有といったユニークな要素が多々盛り込まれており、現役の学生だけでなく歴史教育に携わる者にとっても得るところが大きい。
さらに副題にあるとおり、著者は「史料に語らせ」ること、史料を読み解き歴史像を構築することの楽しさを読者と共有することを本書の基本方針としており、それは大いに成功している。本書では多くの箇所で史料本文の口語訳を掲げたうえで、たとえそれ自体は断片的な史料であっても、設定した課題(たとえば、唐代と宋代の夫婦関係はどう異なっていたか)の観点からはこのような読み解き方、情報の引き出し方が可能である、というように、史料解釈の指針を懇切に示しており、歴史学を専門としない人にもぜひ勧めたくなる魅力に溢れている。
紙幅の都合により章ごとの概要は割愛するが、本書の構成は以下のとおりである。
・序章 働く女たち――唐宋時代史料論も兼ねて
・1章 女が三度も結婚するとは!――南宋の裁判記録から
・2章 無能な夫を持つ妻は……――『袁氏世範』の女性観
・3章 「酢を飲む」妻と恐妻家――唐宋時代の「小説」史料から
・4章 女親分もいた――南宋豪民の実態
・5章 娘たちに遺産はいらない?――女性に関わる「法」と現実
・終章 唐宋時代は何人家族?――史料から数値を読み取る
各章タイトルからも明らかなように、本書は唐宋時代に妻や娘という立場にあった女性たちの姿、その行動力や闘争心を、“家庭でも社会でも無権利状態で深刻な家父長制に苦しめられてきた”的な近代欧米人目線の中国女性史観、いわば抑圧史観とは一線を画した視点からこまやかに描き出し、また彼女たちの家庭生活や夫婦関係・親子関係の(時に強い絆で結ばれ、時に激しく争い対立する)自然なありようを読者の眼前に浮かび上がらせるものである。また、本書が重点的に活用している南宋の裁判史料『名公書判清明集』や家訓書『袁氏世範』から窺い知れる現実と規範との距離感や、本来は民衆に規範を遵守させるべき地方官や士人が示す柔軟で実際的な対応などは、他の史料ではなかなか目にできないものである。すなわち、唐宋の女性史・家族史にとどまらない唐宋史研究一般という枠組みからみても、本書は唐宋の地域社会や行政・経済活動などの実態に迫る上でこれらの史料がいかに貴重で有用であるかを改めて示す形になった。
本書のもうひとつの特色として、『太平広記』『夷堅志』のような小説史料を大いに活用していることが挙げられる。この「小説」はむろんnovelではなく、「言葉の本来の意味での『小説』で、『ちっぽけな、つまらない話』というジャンル」(本書10頁)である。その大元は『漢書』芸文志・諸子略の「[諸子百家のうち]小説家の流派はおそらく、道端で聞かれ語られるような[こまごました]街談巷語を収集する官から現れたものである」にさかのぼるように、「小説」は本来蔑称であった。芸術の一ジャンルにも位置づけられる近現代のnovelとはその点で大きく異なるが、同時に、前近代中国においては、小説を集めて一書を成す編纂者は小説を必ずしも虚構だと考えていなかった点、むしろしばしば“事実を世に伝えること”を目的として小説を収集していたという点が、novelとの本質的な相違であるといえる。むろん前近代中国の小説も長い歳月を通じて多様な発展を遂げてゆき、明清時代に最盛期を迎える白話小説を始めとしてnovelに近い性格をもつものが主流になる。しかし、「白話小説が虚構に傾いたのに対し、これら[引用者注:文語で叙述された『捜神記』『夷堅志』等の]『志怪』は事実性を建前とした」(齋藤茂「前言」、『『夷堅志』訳注 甲志上』ⅲ頁、汲古書院、2014年)と指摘されるように、事実としての怪事なり人物なりを「志」ことに志怪小説や志人小説の本意があったことは間違いない。現代の我々から見ていかに信じがたい内容であっても、小説を収集して世に出す側すなわち編纂者はあくまで事実という体裁をとって提示するのである。志怪小説や志人小説の多くは、主題となる事件の時期や場所、当事者の姓名や社会的地位などを個々の小説(エピソード)ごとに必ず明示するものであり、「昔々あるところに……」的な抽象性とは無縁である。本書で重用される『夷堅志』はその点に加えて、収録する小説の多くにその話の提供者情報を付しており、事実性の高さをできるかぎり保証しようという編纂者(撰者)洪邁の意図が強く感じられる。
小説を史料として用いることの当否自体は、本書では踏み込んで論じられていない。だが、往年の『日野開三郎東洋史学論集』第五巻(三一書房、1982年)の附録「編集のしおり」に著者(大澤氏)が寄稿された「日野氏の業績」という文章の中で、「日野氏の研究は論旨が重要であるばかりではない。その引用史料が一際大きな意味を持っているのである。あの大作『唐代邸店の研究』において小説類を駆使されて大きな成果をあげられた如く、あらゆる関連史料を網羅し、活用しようとされている」(同しおり4頁)と自ら述べられているように、小説史料の活用は唐代(また宋代)史研究において一定の伝統を持ち、本書においても決して奇を衒って歴史研究の素材たらしめようとするものではない。むしろ、本書(および本書の研究者向け姉妹版ともいえる『唐宋時代の家族・婚姻・女性』)は唐宋史研究における小説史料の活用の新たな地平を示したという点で、伝統をさらに一歩推し進めたといえよう。
ここまで見たように、小説史料の活用は本書の欠くべからざる特色であるが、これは一方で、本書の一部にやや議論を呼ぶ性質を孕むことにもなった。『唐宋時代の家族・婚姻・女性』に対する大島立子氏の書評(『東洋史研究』65-2、2006年9月)でも既に指摘されるように、「小説の中の場面はある限定された状況を表すために書かれている」点にとくに注意を払う必要があるが、本書も小説史料の解釈において、この話をそこまで敷衍することが可能であろうかと思わせる事例が若干見られる。また、唐宋時代の妻の実態を特徴づけるものとして本書は「嫉妬深さ」を重視して一章分を割き、興味深い数々の事例を挙げているが、嫉妬の性質を一律に論じることは妥当であろうか。たとえば、死にゆく妻が“自分の死後に(妾を納れるのは構わないが)新しい妻を娶るのは許さない”という意思を夫に告げる事例が小説史料にはしばしばみられるが、これは現代的な嫉妬の感覚からするとやや奇妙である。自分以外の女性との関わりを一切許さないという(現代人に理解しやすい)嫉妬と、自分と同格の女性を迎えることを許さないという嫉妬は分けて考えるべきではないか。とくに後者の嫉妬の場合、やはり妻の地位の不可侵性、妻と妾の地位の隔たりの大きさを前提にして生まれる感情であり、独立して検討するに値する事例であるように思われる。その意味で、「唐宋時代の妻の地位は『原理』[引用者注:滋賀秀三『中国家族法の原理』にいう、妻妾の地位を規定する古典的礼制]に関係なく、あいまいにされていた」(本書158頁)という捉え方には肯首しかねる部分もある。
とはいえこれらは副次的な問題に過ぎない。中国史学に限らず歴史学の楽しさ、そして史料解釈の豊かな可能性を幅広い層の読者に提示するという大きな試みは、本書全体を通じて縦横に展開されている。自分も学生時代にこのような本に出会いたかったという思いをしみじみと抱いた。
(いたはし・あきこ 東京大学)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
