禅宗はいかにして生まれたのか
嶄新な中国禅宗史――孫昌武『禅宗十五講』
衣川 賢次
中国の禅は南北朝時代に達摩がインドから来て始まったと、通常言われている。達摩の言説は唐代初期に形成された「二入四行論」にまとまって存在し、これが禅の思想の原初形態と目されるわけだが、そこには「四つの修行」が述べられている。読んでみると、「修行の途上で苦しみに遭った時は、前世のみずからの悪業が生んだ結果であるから、他人を怨んだり不平をこぼしたりしてはならぬ」(報怨行)、「この世のすべては因縁によって形成されたものゆえ、運命と諦めて随順せよ」(随縁行)、「苦しみは欲求を起こすところから生まれるゆえに、無欲に徹せよ」(無所求行)、「人間の本性は清浄であるという理法に遵い、これを汚す慳貪を離れよ」(称法行)というような内容で、これはどう見ても、社会の最底辺にあって軽蔑迫害を受けた人が忍従生活から身につけた処世訓であろう。こういう信条の実践を「修行」と考えた初期禅宗の人びとは、いかなる階層に属し、いかなる生活を送っていたのであろうか。日本の従来の「中国禅宗史」、「中国禅思想史」なるものは、禅宗内部の禅僧の伝記と言説を、後世に作られた「宗統」(宗派的系譜)に沿って叙述してきたので、こういう疑問は考慮の外に置かれていた。一方、現代の中国の研究は、社会経済史的な視野のもとに宗教を考察する姿勢が貫かれ、初期禅宗は隋唐交替の動乱期に大量に発生した流民、流浪僧が結集して山林を開墾し、ここに自力更生の根拠地「禅寺」を建設して、修禅と農耕を基本とする生活形態の新仏教を発足させたという見解を打ち出した。ここから見ると、「二入四行論」は動乱期に遭遇して生きるために出家し、各地を流浪せざるを得なかった遊行乞食僧が、みずからに課した「修行」であったことが納得されるのである。
中国研究における「宏観」(広い視野をもった研究)と「微観」(細部の精緻な研究)はむろん融合さるべきもので、近年は学術交流が進むなか、互いに補い合うすぐれた成果が出現している。
拙訳『禅についての十五章』(東方書店、2021年/原著は孫昌武『禅宗十五講』、中華書局、2016年)は中国における禅宗の展開を講義形式でわかりやすく解説し、禅宗の性格を明快に論じた書物である。著者によれば、唐代に興起した禅宗という宗教の特徴は、思想上の自主独立、経済上の自力更生、組織上の師弟平等と共同修行の形式をもつ新型の「禅寺」という形態を創建したところにある。この唐代禅宗の展開を、「中国の歴史社会における生存形態が、禅宗僧団の思想を形成し、発展させ、さらには衰微せしめた」という論(すなわち古い術語にいう「存在が意識を規定する」)として、豊富な歴史的資料にもとづき、説得力をもって述べており、中国禅宗史というかなり専門的な分野であるにもかかわらず、これを新鮮な視角から一般読者に向けて書かれた、非常に印象深い読み物となっている。具体的には以下のような内容である。
唐代の初期に道信、弘忍らは、すべての人には「自性清浄心」が具わっており、心安らかなよき人となるための修行は心の汚染を払拭するだけでよいとした。かれらはもともと自身が遊行僧、流浪僧と呼ばれる私度僧(行脚の乞食僧)の出身で、王朝交替期に発生した大量の流民、流亡僧の組織者となって、習禅の根拠地を湖北黄梅山に築いた。そこは地主のいない開墾を必要とした荒涼たる僻地で、拓かれた田地は当時施行された「均田制」によって僧に分配され、僧団の自主独立の基盤を確立して運営し、ここに従来の国家の庇護下にあった既成の仏教教団とは異なる新仏教「禅宗」が生まれた。
この経済的自立が僧団にもたらした新仏教の革新的性格はつぎの点である。朝廷と貴顕への依存から離れて民間に基盤を置く反体制的性格、修行において僧団内部の切磋琢磨に重点を置く平等的性格、自身を信頼し経典の権威を離れ、拝仏礼讃儀礼を廃した反教条的性格、他力信仰に反対する自力的性格、人材育成において啓発を重んずる自由開放的性格。これが黄梅僧団の革新的宗風である。
その新思想は則天武后朝下の思想革新の機運にあった新興の庶族士大夫に支持されて発展をとげた。しかし弘忍の弟子神秀、その弟子普寂(いわゆる北宗)になると皇帝、貴族、官僚の帰依を得て供養を受ける国師となり、自身が大寺院の住持となって支配階層化し、思想的にも新しい開拓の力を失った。
次に登場した慧能、神会らのいわゆる南宗禅は嶺南の辺地において、道信、弘忍の草創期禅宗の草莽精神を承け継いで一歩を進め、心は本来清浄で、その自覚の工夫「頓悟」によって「見性」(悟り)を実現できるとした。慧能は嶺南から逃亡流民として生路を求めて湖北黄梅の弘忍のもとへ来たが、短期の滞在ののち、ふたたび官府の捜索を逃れて南へ帰り、山林に隠れたという経歴の人であった。刻苦の経験と倔強な自主、反権勢、進取の精神の持ち主であったかれは、南方で流民を組織し、安心自足の教えで地域安定に貢献して地方政府に容認され、また南宗の「人間性の平等」、「自らの本性にもとづいて自ら悟る」という禅思想は、当時の玄宗朝の落魄士大夫に精神的な支えを提供した。
ついで興った中唐馬祖道一の禅宗は「平常心で生活することが道である」と言い、服を着、飯を食い、眉を揚げ、瞬きする日常の営為のすべてが仏性のはたらきであって、ことさらな規格の修行は必要ないという過激な思想を掲げ、安史の乱後の人びとから大きな関心を集めた。馬祖は乱後の売度と私度によって膨張した遊行の流浪僧を集めて教団を組織したが、この時は「均田制」が崩壊して「両税法」が施行された時期に当たり、開墾した山林田地は教団所有の荘園となって、習禅の根拠地としての「叢林」が形成され、坐禅と農業労働と師弟平等の「禅問答」による相互啓発という、禅修行の生活基本を確立した。馬祖禅の支持者は当時の地方政権藩鎮の実力者とそこに集まった落魄士大夫たちであり、かれらが宋代の新しい学術の先駆となったのは、馬祖禅に接触したことと関わりがある。禅宗は地方を根拠に展開し分派していったが、しだいに唐末の藩鎮や五代十国の支配層の帰依を得、これに依附して、組織的には教団内に階層を生じ、思想的には「教禅一致」、「三教合一」の伝統に回帰してゆき、当初の非政治的、非倫理的、反権威、反伝統の革新性を失って五代宋初にはしだいに衰微していった。
以上が本書十五章の主要部分の骨子で、従来の中国禅宗史、禅思想史では注意されなかった禅宗の形成と展開の歴史社会的背景を、史料にもとづいて明らかにし、その結果きわめて説得力をもった新鮮で魅力的な叙述となっている。本書は日本人にもなじみのある「禅」の初心を思い出させてくれるであろう。
本書は十五のテーマを立てて唐代を中心とした禅宗の歴史を講ずる形式を取っており、全十五章の構成は以下の通りである(タイトル下の括弧内は要旨)。
開講にあたって(近年における禅への関心の広がり)
第一章 禅は仏教ではない?(「批判仏教」の問題提起と「教外別伝」の意味)
第二章 インド禅から中国禅へ(仏教の「中国化」による変貌)
第三章 禅宗の始まり(黄梅僧団の形成とその歴史社会的背景)
第四章 安心という法門(達摩の禅思想とその発展)
第五章 革新的宗風――黄梅山(経済的自力更生、非政治的・非繁瑣哲学的宗風、開放的組織)
第六章 東山法門(禅宗と初唐思想学術の革新、武后朝と庶族知識階層の支持)
第七章 南宗の興起(慧能と『壇経』の頓悟思想)
第八章 南北宗の分化(神会の活動と敦煌資料、南宗の支持者)
第九章 洪州宗の盛行(馬祖禅興起の歴史的背景、中唐学術の革新)
第十章 馬祖禅の新しさ(僧団の建設、清規の制定、平常の心、日常生活中の禅問答)
第十一章 分派の形成(中唐の馬祖・石頭二系から晩唐五代の五家へ)
第十二章 宗風の変容(地方藩鎮下の禅宗、宗派形成と各派の綱要)
第十三章 禅教合一、伝統への回帰(禅宗への批判、教禅の一致、禅浄の合一)
第十四章 禅思想と宋明の新儒学(中唐より宋明に至る禅宗と新儒学とのかかわり)
第十五章 禅の文学(白話文学、禅僧と士大夫の交流、唐代から明末までの禅文学)
講義を終えて(いわゆる「禅宗革命」の意味、プロテスタンティズムとの相違)
本書の禅宗研究の特徴は、従来の禅宗史が禅宗内部の思想的言説の演変を追うのみであったのに対し、その言説を生み出した歴史的社会的背景の解明に力を注いでいるところにある。禅僧の出自、支持層の政治史・思想史上の性格、政治史・経済史の動向と禅思想の関連等が、大量の資料の引用によって闡明された。禅宗という宗教がいかにして生み出されたのかが初めて明瞭となったのみならず、禅思想と中国の歴史社会との互動関係、新儒学思想や唐宋時代の文化との関連などを読者は知ることができ、著者の精力的な解明と描写によって、禅宗という革新的宗教の明確なイメージを読者に提供している。
第一章から第十三章までが、仏教の中国伝播から初唐の禅宗の興起、さらに中晩唐より宋元時代までの禅宗の動向を、第十四章と第十五章が新儒学思想・文学分野への禅宗思想の影響を概観しており、唐宋時代の文学と宗教の専門家である著者ならではの行き届いた禅宗史の講義となっている。
本書は2016年に刊行され、その年の中華書局の内部審査で同書局出版物2000種の中から推薦図書の第一に挙げられ、『中華読書報』が2016年末に実施した年間出版物40数万種からの「十大好書」に選ばれたというから、中国国内では当初から好評を得ていたことがわかる(「百年来の胡適、銭穆、馮友蘭が提起した〈禅宗思想の革命〉という命題が学術的に論証された」点が評価されたという)。
また本書は「2018年中国国家外訳資助項目」(中国書を外国語訳して海外に広めるプロジェクト)にも選定された。本書の嶄新な禅宗史は翻訳して日本の研究者に提供する充分な価値があり、また中国の新しい研究として、禅に関心をもつ日本の人びとにも有益であると思う。
著者の日本との縁は早く、1982年に神戸大学で2年間「唐代文学と仏教」の講義をされた時、まだ大学院生であったわたしは中国語でなされる講義がめずらしい時代であり、またそのテーマが魅力的であったので、毎週京都から神戸まで孫氏の講義を聴きに通ったことがある。その五年後に東方学会で「唐代の文学に与えた仏教の影響」の講演をされた時には通訳に当たった(講演稿の翻訳は『東方学』第73輯に掲載された。1987年)。その20年後に中国仏教典籍選刊『祖堂集』(中華書局、2007年)を共著で出版した。初識以来40年の交友があり、今回の『禅宗十五講』の翻訳においては、引用古文の解釈について孫氏の示教が得られた。本書は徹底した資料にもとづく立論・叙述であり、しかも叙述は多分野にわたり、わたしの学力では対応に難渋した箇所が多くあったが、引用の古文はほぼすべてを現代日本語に訳した。訳書の書名は『禅についての十五章』とし、11月中旬刊行予定である。翻訳の底本は2018年3月北京第二次印刷本(訂誤を経ている)をもちいた。
(きぬがわ・けんじ 花園大学)
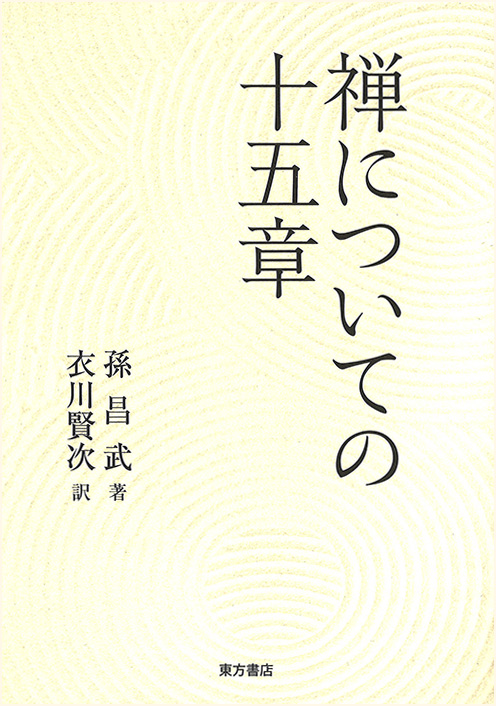
孫昌武 著
衣川賢次 訳
出版社:東方書店
出版年:2021年11月
価格 7,700円
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
