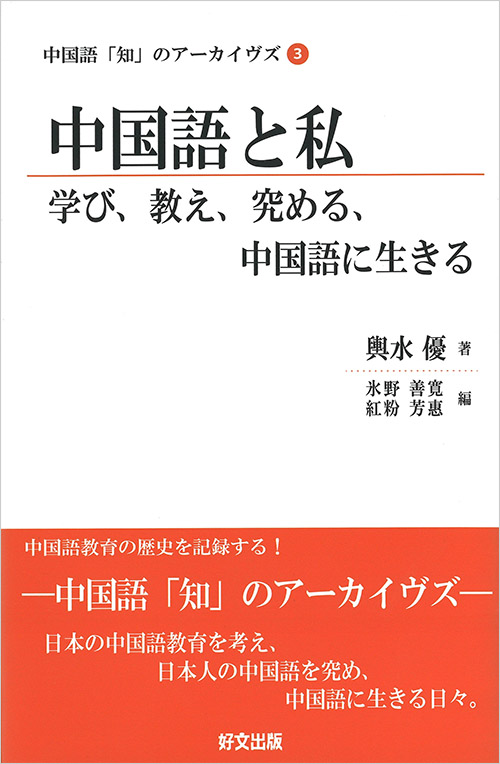
|
太い絆で結ばれた中国語・中国
中国語「知」のアーカイヴズシリーズの③にあたる本書は、中国語研究と中国語教育の第一人者である著者がふたりの編者の問いに答えて自らと中国語とのかかわりを縦横に語り明かした聞き書きに、手を入れたものである。編者の「まえがき」によればインタビューは2016年9月4日と2019年7月29日の2回にわたって行われた。驚くのは著者の率直さとその記憶の精細さである。著者は1954年に中国語を学び始めて以後のすべての資料をテキストだけでなくビラ1枚まで保存しているという。通常の人にはこれは容易にはなし得ない周到さである。
本書の目次は以下のとおりである。
まえがき
第一部 学び、教え、究める
はじめに
大学入試
戦時の生活
横須賀の思い出
中国語へ
たった一人の中国人教師
中国語辞書との出会い
趙玉明さんと文通
黎波先生の話
外語大で受けた中国語授業
教室会議のこと
私の中国語への視点
朱徳煕先生に尋ねたこと
東大中文に進学して
中国語と漢文
水世嫦先生の個人教授
テレビ中国語講座の経験
テレビ中国語講座出講に至るまで
テレビ・ラジオ講座のテキスト作り
漢字に感じること
作りたい本、作った本
わがままの回顧と悔悟
初めての中国
“外宾!”の効用
中国人のおもてなし
二度目、三度目の中国
北京大学で過ごした一年
朱徳煕先生を憶う
世界漢語教学学会の誕生と別れ
中国語検定試験とHSK
中国語教育学会の設立、学術交流の展開
第二部 課余閑談
初期のラジオ講座テキスト
中国語教材今昔談
社会の変化と呼称、敬称
あとがき
読み終わってこの目次を見ると、実は本書は1954年以来著者が中国語を学び、研究し、教育してきた時どきの歩みをこれ以上なく詳細に語った一つの記録であることがわかる。語り口は確信に満ちている。日本人の研究者、教育者として日本人のための中国語研究を探求されてきたことからくる自信なのであろう。ただ時間の流れに沿って回想されているわけではなく、編者の質問に答えて思いついたことを一区切りがつくまで語られているので、この目次の項目の一つ一つが時間的にかなりの幅をもつものであり、その内容が驚くほど充実していることは想像しにくい。
紙幅の関係で目次のいくつかの項目で語られていることをとり上げて気づいたことを指摘することにしたい。
(一)「大学入試」「横須賀の思い出」「中国語へ」
──中国語は第一志望ではなかった!
著者の名前を聞けば誰もが中国語を思い浮かべる。それは著者が東京外国語大学に入学して以来営々と努力を重ねて築きあげてきた業績によるものである。横須賀高校に在学中ESSに所属し横浜のYMCA英語学校に通っていた著者は、国立大学一期校の入試では英文科を志望し、二期校の外語大を受験するにあたって「二期校だから第二志望を選ぶような意識」でアジアの言語にしようと思ったという。「インドあたりを漠然と考えていた」が、倍率があまりにも低く、結果的に一定の倍率を維持していた中国語専攻を選んだ。その後思い返せば高校生のころパールバックの『大地』、老舎の『四世同堂』、黄谷柳の『蝦球物語』などを読んでいたので、実は中国に関心をもっていないわけではなかった。大学入学時には必ずしも太いとは言えなかった中国語・中国との絆は、著者の生涯をかけた努力によって太い絆となったと言えよう。
(二)「趙玉明さんと文通」──響き合う律義さ、誠実さ
外語大1年の時、著者は文通が趣味の同級生に勧められて北京大学中文系の趙玉明という学生と文通するようになった。ある時「ビニールというものがわからない」と書いてきたので「ビニール製品の、四角い風呂敷みたいな生地とか、小間物」を小包で送ってあげたことがあった。その後4年生になり、卒業論文は老舎の作品論か、作家論にしたいと考えていたが、参考資料がないので、仕方なく北京の趙さんに「老舎のそれぞれの時代の作品のコメントをしたい」と卒論の筋書きを書いて送った。すると「北京大学図書館所蔵の解放前の新聞雑誌類から老舎の作品に関する文章を全部手書きで写したノートを一冊送って来てくれた」のである。万年筆で書かれた達筆の文字に、著者は感激した。
後年、趙さんは北京広播学院(現在の中国伝媒大学)の学院長となった。10年ほど前に「北京広播学院と日大芸術学部の交流協定があって、趙さんが日本にやって来た」。著者はノートを持って行って見せ、趙さんも驚くという出会いがあった。ノートと同じころ趙さんは『東海巴山集』、『四世同堂』など何冊か老舎の著作の古本も送ってくれた。東大中文に進学後、著者は倉石武四郎先生から『ラテン化新文字による中国語辞典』にない用例を『東海巴山集』から拾う仕事を託され、仕上げて持って行くと、「こんなにやってくださらなかった方もいました」というねぎらいを受けている。著者と中国の研究者との交流はお互いの律義さ、誠実さで維持され、それが著者の業績につながっていることがわかるエピソードである。
(三)「外語大で受けた中国語授業」「東大中文に進学して」「中国語と漢文」
──如何に中国語を学んだか
「当時の外語大の授業は暗記、暗唱、そして聞き取り、書き取りばっかりだった」と批判的に回想しているが、その学習に誰よりも熱心に、徹底して取り組んだのが著者である。外語大で学力養成の中心を担った長谷川寛先生の作文の授業はハードなものだった。1954年春に活字印刷で出版された作文教科書は毎年改訂され、1961年書籍文物流通会から出版の『標準中国語作文』からは、要点という語法解説の項目が加わった。長谷川先生は毎授業時最低3回のテストを実施した。一年次の10月には白水社から『中国語作文』という新著が出て、教科書に加えて、毎週その新しい本からも5頁ずつ暗記してくることになった。5頁分で2、30の文例を毎回暗記しなければならない。著者がそれを完璧にやり遂げたことは、勉強ぶりの記述からうかがえる。そのテストの答案は全てとってあるとのこと、驚くほかはない。外語大の教員になってから『標準中国語作文』を何度か修正して定年退職まで使い続けたのは、この方法の有効性をよく知っていたからであろう。
東京大学での古典文学の講義、演習は古典研究への著者の眼を開いた、と思う。前野直彬先生が開いた『史記』、『漢書』など古典の読解力養成を図る、ご自宅での私塾に卒業後も参加し続けた。藤堂明保先生は古典詩文の講読で漢文を重視する姿勢を示された。言語学者の魚返善雄先生は漢文に堪能だった。外語大の田中清一郎先生も中国語学科で漢文を学ぶことの必要性に言及されたことを紹介し、著者は中国語教育における漢文(古文)学習の重要性を指摘している。
(四)「私の中国語への視点」「朱徳煕先生に尋ねたこと」
──日本人として中国語に懐く疑問の解明
著者は程度副詞の「很」はなぜ多用されるのかという疑問を持っていたが、旧ソ連のドラグノフ(龙果夫)による『現代漢語語法研究』の中国語訳(科学出版社、1958年)を読み、「很」について「はだかの単音節性質形容詞は比較、対照を表す。「很」を添えれば、その制約が消え、重ね型形容詞と同じ状態形容詞の働きとなり、文として完結する」ことがわかり、それがきっかけで「動詞(正しくは動詞句)を修飾する「很」がある」のを知った。著者が藤堂明保先生の指導を受けて初めて書いた語学の論文は「動詞を修飾する“很”について」で、東京大学の卒業論文である。論文は卒業直後の1960年4月発行の学会誌『中国語学』97号に掲載された。翌1961年中国で『中国語文』第8期に同じ問題を論じた饒継庭氏の「“很”+动词结构」が掲載された。中国の研究に先駆けた著者の業績である。
「日常よく使うけれど十分な説明がないとか、説明できないでいる言葉について調べたい」と考えている著者は1978年に北京大学に研究留学した際、朱徳煕先生に「肯定+否定」の疑問文「是铅笔不是」と「是不是铅笔」の違いについて倉石武四郎先生の説明を示して聞いたところ、「わからない」と言われた。後に朱先生は自分の学生たちが出身地の方言ではどちらを使うかを調べて、「汉语方言里的两种反复问句」(『中国語文』1985年第1期)」を発表された。1991年第5期の『中国語文』には朱徳煕先生の「“V-neg-Vo”与“Vo-neg-V”两种反复问句在汉语方言里的分布」が掲載され、著者も呼応して論文を書いた(『中国語学』247号「反復疑問文をめぐって」)。「ネイティブは気づかず使っていて、言われてみて初めて、自分たちは使い分けているか、いないか、気づくのです」。これは著者の質問が一つの語法の問題を解決するのに寄与した一例である。
以上、本書のほんの一部分、34項目ある目次の9項目についてだけ言及、論評した。本書には他にも多くの興味深い内容が盛り込まれている。例えば1967年の最初の訪中の項目では、文革中の意気盛んな紅衛兵の姿がとらえられている。1978年から1年間の研究留学中の生活は今では想像もできない苦労が多々あったことがわかる。『中国語図解辞典』のための資料収集には微苦笑を誘われるエピソードが満載である。NHKテレビ中国語講座の初期の混乱は、渦中にあった著者ならではの証言である。内容と語り口の面白さを知っていただくには本を直接手にとり、お読みいただくのが一番である。本書には人名を中心に辞書、事項など98項目に及ぶ注が付されて、理解を助けてくれる。
最後にひとこと──この本はこれで一つの貴重な記録であるが、とり上げられなかったことも少なくないのではと思われる。著者自身の手になる「中国語教学史」をまとめていただければと思うのは望蜀の言であろうか。
(わたなべ・はるお 元國學院大學教授)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
