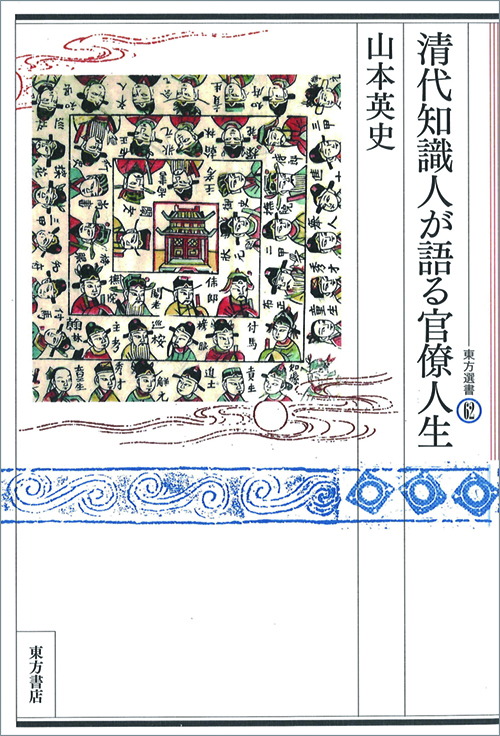
|
本書の主人公──というか、語り部は、明代も極末の崇禎3年(1630)年頃に江西省新昌県に生まれ、清朝の康熙帝の治世(1662~1722年)の前半期に官僚として地方や中央の官職を歴任した黄六鴻という人物である。中国の明清史を研究する者であれば彼の名前は必ず聞いたことがあるのだが、特に輝かしいキャリアをもった超エリート官僚というわけではなく、もっぱらその著書である『福恵全書』(1699年刊行)という官箴書(官僚の執務心得)の著者として知られている。『福恵全書』は、全32巻の大部の書物で、彼がそのキャリアの初期に知県(県の長官)を務めた際の経験をもとに書かれている。『福恵全書』は明清時代の数ある官箴書のなかで中国でもよく知られたものの一つだが、日本では特にこの本にお世話になった経験のある研究者が多い。というのは、幕末の嘉永3(1850)年に小畑行簡という学者が『福恵全書』全巻に句読点・返り点及び送り仮名をつけ、かつ日本人にとって難解な語に説明をつけて出版しているからである。清代の地方行政の実際の業務について詳しく知るためには、大変ありがたい本なのである。
さて本書『清代知識人が語る官僚人生』(以下『官僚人生』)は、清代の地方行政の実態について長年研究してこられた山本英史氏が、この黄六鴻に成り代わって、「私」=黄六鴻の目を通してみた地方官の業務や生活を、わかりやすく語った書物である。『福恵全書』は、あくまで官僚の執務指南として書かれたもので、黄六鴻が自らの人生を振り返った自分語りの本ではなく、波乱万丈の経歴が語られるわけではない。しかしその『福恵全書』をベースとした『官僚人生』が、無味乾燥な行政制度の記述に終わらず、大変楽しく読めてしまうのには、いくつかの理由があろう。一つは、『福恵全書』は官僚の心得を記した書ではあるが、自らの体験に根差した記述が多いので、そこに黄六鴻の人柄や考え方が自ずとにじみ出ていることである。もう一つは、山本氏が、今までの研究成果を生かし、『福恵全書』以外のさまざまな史料──他の官箴書や地方志、小説から清末の画報まで──を引用して、黄六鴻の体験に基づく記述に豊かな肉付けをしていることである。それらの史料のなかには、黄六鴻の生きた時代より後のものも含まれていて、「私」=黄六鴻の語りの中にそれらが出て来るのは変といえば変であるが、「そこはそれ、ナレーターとしての役目の都合上、どういうわけか、これらの知識をも備えているという設定になっている」(まえがき、vi頁)ということである。
全体は、以下の六章構成となっている。「第一章 官僚への道」、「第二章 官僚人生の始まり」、「第三章 知県という職業」、「第四章 知県の人間対応」、「第五章 黄六鴻の事件簿」、「第六章 その後の人生」。
第一章は、黄六鴻の家柄や任官以前の経歴を記すが、それに関わる直接の史料は少ないので、主にその背景として、科挙合格を目指す知識人家庭の子供の教育課程や科挙試験の仕組みに関する一般的説明がなされている。第二章は、主に『福恵全書』「筮仕部」(初任官者の心得)を構成する巻1と「蒞任部」(着任時の心得)中の巻2に依拠し、北京の吏部(人事関係の官庁)で籤を引いて任地が決定してからの赴任準備、及び任地到着直後の様々な手続きや儀礼について述べる。第三章は、県署(県の役所)の人的構成や建築配置、「民の父母」としての知県の基本姿勢、徴税・裁判をはじめとする基本業務、及び知県の日課・収入などを手際よく概説する。
第四章は、『福恵全書』「蒞任部」の巻3、巻4を中心として、まず周囲の人間との付き合い方について述べる。周囲の人間とは、第一に官僚であり、上級地方官である上司のほか、他県の知県、下僚に当たる補佐官等を含む。第二は吏役、即ち県署で事務作業や単純労働に携わる職員であるが、彼らは科挙に合格して派遣されてくる官僚とは異なり現地採用の人々で、血縁その他さまざまなコネクションを使って県署内で隠然たる勢力を持っていることが多い。第三は郷紳、即ち官僚経験を持ち地方社会で強い影響力を行使する名士たちであり、彼らは退職後・休職中であっても、地方官と対等に交際できる社会的地位を持っていた。これら周囲の人々に対し、知県は、官僚機構の一部として決められたルール通りにふるまっていればよいというものではなく、相手の一人一人の性格を見極め、信頼を得られるように、かつ軽んじられないように筋を通して、良好な人間関係を築いてゆくことが求められた。
知県は周囲の人々との人間関係をこのように慎重に調整しつつ、「民の父母」として、その職務である地方統治を行ってゆくが、慈しみの心をもって接すればそれに応えてくれる“良き民”ばかりではなく、社会秩序を乱す“悪しき民”も少なからずおり、彼らを根絶することはできなかった。人民と直接関わる知県の主要な職務は、徴税と裁判であったが、裁判においては、これら“悪しき民”をいかに扱うかが知県の手腕の見せ所となり、『福恵全書』でも全32巻のうち10巻が裁判関係の記述に当てられている。第五章では、『福恵全書』に載る裁判事例のうち8件を具体的に紹介し、黄六鴻がどのように“悪しき民”に対処したかを述べる。これらの事案は、吏役と結託したゴロツキ集団の悪行、村役の地位をめぐる紛争に起因する誣告事件、生員(科挙の予備試験の合格者)による租税横領、土地争い、妻殺しなど様々だが、事実を見抜く能力とともに、事情を酌量して処罰を加減する柔軟さも、知県の評判を高める大きな要素であった。
この第四章・第五章が、当時の地方官の在り方の特色をよく示すものとして、『官僚人生』のなかで頁数も比較的多い主要部分といえる。最後の第六章は、地方官の離任に際しての心得で、『福恵全書』末尾の「陞遷部」第32巻に載る様々な離任手続きのほか、善政を行った地方官の離任に際して民衆がそれを阻止しようと車を引き留めるという伝統的パフォーマンスにも触れている。こうした民衆行動は人々の真情に出たものか或いは忖度ないし「やらせ」なのか、というと、その区別をはっきりつけるのは難しい。
以上、『官僚人生』の生き生きした記述から、清代の官僚の在り方の特色として、読者は何を読み取ることができるだろうか。一般に、伝統中国の官僚については、清廉潔白で民のために尽くす聖人のような「清官」から、民を食い物にして私利を図る冷酷な「貪官汚吏」まで、両極端のイメージがあるといえよう。これはどちらが間違っているというよりは、今日の私たちが「官僚制」「官僚主義」といった言葉で思い描きがちな、規則にしばられて融通が利かないといった「官僚」イメージと異なって、当時の中国の官僚はその人間的な道徳的能力によって統治するもの、即ちその生身の人間としての個性が統治の仕方に直接表れてくるものと考えられていたことに由来するのだろう。一方、『福恵全書』に、そして『官僚人生』に描かれる官僚の姿は、きれいごとの理想論でもなく、また『官場現形記』などの風刺小説に描かれるようなドロドロした暗闘でもなく、今日の私たちにも共感しやすい常識人としての官僚の姿である。ただしそれは、単に中間的な平凡さ、というよりは、理想も暗部も知った上での成熟した知恵ともいうべきものである。
著者は『官僚人生』の最終章で、黄六鴻に成り代わって次のように述べている。「私は、理想は理想として大切にして床の間に供えながらも、現実にはその理想を無理に追求することはせず、みずからの能力と当時の官場における特有の人間関係に適したやり方で臨機応変に対応することで、知県という任務をできるだけ安定して続ける方がむしろ賢明と考えたのです。私に対する評価の多くが儒教の求める模範人格よりも現場の行政手腕の方に力点を置いていたことに自分としては満足しています」(268頁)。これは、穏やかな表現ながら、本書のエッセンスを鋭く総括した言葉といえよう。
『官僚人生』は、一般向けの書物ということで細かい注などはつけられていないが、より詳細に清代の地方官の思想と行動について知りたい読者は是非、著者山本氏が専門書として著した『赴任する知県──清代の地方行政官とその人間環境』(研文出版、2016年)を手に取って見られたい。実のところ、『官僚人生』はこの書物のダイジェスト版という側面もあり、『赴任する知県』の中の文章が「ですます」調で柔らかく書き改められてほぼそのまま現れるところも多々ある。一方、『官僚人生』には、当時の書物の挿絵や著者撮影の写真など、大量の図版が収録されており、これは一般書としての本書に対する著者の丁寧な配慮であって、読者が当時の雰囲気を窺う助けとなるものであろう。
(きしもと・みお お茶の水女子大学名誉教授)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
