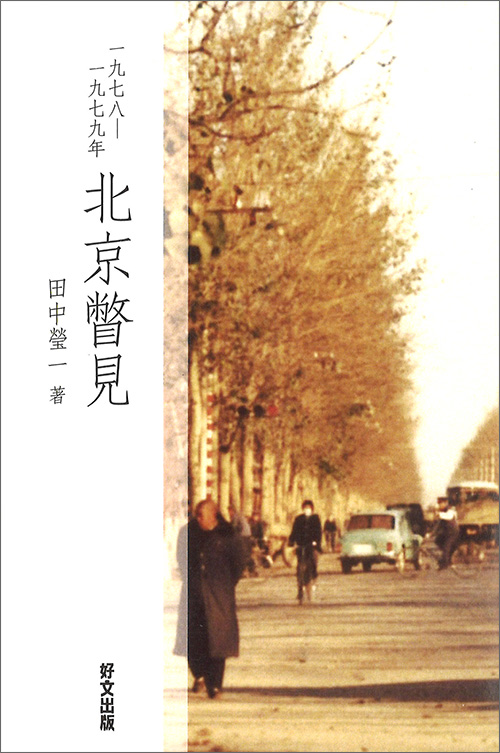
|
45年前の中国滞在記──いま出版する意味
著者の田中瑩一島根大学名誉教授(国語教育学、口承文芸表現研究)は1978年7月から79年8月まで、北京大学から日本語教育担当の専家(専門家)として招聘を受け、北京で暮らした。
これは、日中間の交流が極めて限られており、まだ誰でも中国に行けるわけではなかった時代に北京に滞在し《中国の一般の人々の日常はどうか、あなたは中国でどう過ごしているのか等、尋ねられたり、寄稿を求められることが多かった》著者が《求めに応じて話したり書いたりした素稿の中から、何らかの意味で「時代の記録」たり得えているかと思われる文章》(「はしがき」。《 》内は評者の要約。以下同じ)を選び一冊にまとめたものである。
その「記録」を著者は以下の目次のように大きく六つに整理している。
Ⅰ 北京大学日本語科の学生たち=著者の体験した北京大学日本語科の授業、学生や若い先生たちとの交流から見えてくる生活の一端の描写。
Ⅱ 北京市「紅民村」の子どもたち=著者の宿舎だった友誼賓館傍らの労働者住宅団地に住む子どもたちの戸外遊びの観察記。著者と子どもたちとの交流の記録でもある。
Ⅲ 北京通信抄=北京滞在中、日本の雑誌や同人誌に寄稿した現地生活記及び私信の抄録。
Ⅳ 北京日録抄=北京滞在時の著者の日記から抄録。
Ⅴ 北京回顧摘録=帰国後、中学生に語った回顧談と中国民話の語りから抄録。
あとがきにかえて=北京大学日語系・潘金生教授や教え子による著者に関する回想。
目次だけを見れば、本書は70年代末期の北京に滞在した人の見聞録にすぎないようにみえる。だが仔細に読んでいくと著者には極めて明確な問題意識があり、それに基づいて取捨した見聞を綴っていることが分かる。その問題意識とは、中国社会を庶民の側から見てみたいというものだ。
著者は本書の「跋」に《この書名はハーン(小泉八雲)の『日本瞥見記』(『知られぬ日本の面影』)への畏敬に負うている》と書き、ハーンの「序」の主旨(《その国の美徳を代表している庶民の暮らしにどっぷりつかって生活すれば、彼らの「内なる生」が理解できるようになる》)を紹介している。
ハーンは外部世界に十分知られていなかった明治の日本庶民の生活様式や精神の在り方(ものの考え方、感じ方など)を「内なる生」と呼んだのだが、著者は北京赴任に当たり、ハーンに学んで中国庶民の「内なる生」の実際にふれ、それを理解したいと考えていた。
だが、著者より前、1973年から5年間同じく日本語専家として北京に滞在したぼくの経験では、専家として招聘された外国人が、その身分のまま、通常の意味での「庶民の暮らしにどっぷりつかる」ことなど、当時の中国ではまず不可能だった。
著者もこう書いている。
《現地で比較的親しく交流できたのは「庶民」というよりは「学生」や「子どもたち」だった。》《彼らの「内なる生」は自分たちも(知識としては)よく知っているが、傲慢にも忘れかけていたかも知れない、人としての基盤を率直な形で表現するものだった。本書は改革・開放前夜の中国で、特定の時代的背景を背負う彼らと日常のある時間を共有しながら著者が体感した「中国の人びとの内なる生」をめぐって書き綴っていた記録の一部をまとめたものである》(「跋」評者による要約)。
従って著者にとって「中国庶民の暮らしにどっぷりつかる」こととは、彼が「日常のある時間を共有」した、さまざまな中国人(宿舎友誼賓館の服務員、宿舎近くの労働者団地の子どもたち、北京大学の教え子の労農兵の学生、日本語科の若手教員、著者と深い友誼を結ぶ潘金生教授、飛行機で隣り合わせた「残留孤児」の日本人婦人、旅行先の雲南で出会った下放知識青年等々)と誠実に交流し、その中から彼らの「内なる生」を体感しようと努め、記録することだった。
注意したいのは、それらを発表する際に、著者が彼らを過剰に持ち上げることも、強いて欠点をとりあげることもせず、相手に親和的であるが、冷静・客観的な筆遣いで、相手の中国人の置かれた状況と、彼らの伝えようとしている思いを誠実に紹介している点である。
そのような記録の例として第Ⅱ章や、第Ⅲ章の「ある婦人のはなし」、「辺境の「下放青年」たち」などがあるが、ここでは第Ⅱ章の一部を紹介しよう。
《著者は滞在していた宿舎傍の労働者団地の子どもたちと仲よくなり、帰国前の6週間、彼らから日常やっている遊びや、「遊び歌」を教えてもらっていた。来週で最後と予告して遊び場に出かけたその最後の日、子どもたちが廃紙を利用して折った折り紙を著者に渡した。送別の記念だった。その中の一人小学4年の張光徳は「送給您」と言って新品の手帳を差し出した。これを見ていた小学2年の冉瑞宝(ゴム跳びの名手)が家に帰り、すぐに又飛び出してきて、自分の使っていたゴムひもを、砂をはらいながら無言でさし出した。著者はこみあげるものを感じた》
なお、ここで紹介されている多彩な遊び(鬼遊び、陣取り、めんこ、ゴム遊び、縄跳び、言葉遊び、お手玉、民話、わらべ歌等々)は著者のフィールド調査(参与観察)の詳細な記録だが、趣味的にも学術的にも有益貴重な文献だと思う。この分野に関心のある人には是非一読をお勧めしたい。
以上は著者の体感した中国庶民の「内なる生」のほんの一例だが、本書はこのような出会いを通じて当時の中国庶民の考えかたやものの感じ方を描き出す、内側から見た中国滞在記でもある。
次に、本書の潜在的なモチーフについて書きたい。それは、奥付の発行日時2023年8月12日に込められているだけで、直接、明示的には書かれていない、日中関係の現状と将来についての著者のある思いなのだが、同時に本書がいまのような時代に出版される意義を語ることにもなると思うからだ。
第Ⅳ章北京日録抄79年7月の項に、北京大学日本語科が著者のために開いた送別会とそこで述べられた謝辞の記録がある。それによれば、著者は1978年7月21日に北京に着くが、それは日中平和友好条約の締結交渉が始まった日だった。条約は帰国前に北京大学が手配した南方旅行の途中、8月12日に締結され、それを付き添いの北大職員から知らされた。新しい日中関係の門出となる条約の締結日は、その交渉開始の日に中国に入った著者にとって印象的な日である。奥付の発行日は、その締結45年目だったのだ。
平和友好条約は78年10月23日に批准された。去年の45周年記念祝賀会も10月23日に開かれ、扱いは大きくはなかったが、新聞テレビで報道された。しかしメディアが注目したのは喜びや今後の発展への期待ではなかった。
この条約締結についての調査では「知らない」人が8割強だったし、22年が日中国交正常化50周年であることを知っていた日本人は調査対象者の3割弱、「知らない」と答えた人が7割弱だったのだ(言論NPO調べ)。このような数字を根拠に報道各社は、日中関係に潜在する日本世論の無関心、その根底にある中国への友好感情の著しい減少を指摘し、日中関係の今後への危惧を報じていた。
今年に入って発表された内閣府の「外交に関する世論調査」によれば、調査対象者で「中国に親しみを感じない」人は「どちらかと言えば」を含めて9割に近い86.7%で、調査開始以来最高だったという。参考までに、同じ調査では条約締結後の80年に「親しみを感じる人」が、8割近く、「感じない」人は、15%に過ぎなかった。
90年代の初めに起きた天安門事件をきっかけに、対中世論は中国に冷淡になっていく。著者はその趨勢を感じ取って心を痛めていたのだ。
本書の奥付の2023年8月12日は、それ自体が著者のこうした空気への批判、主張にほかならない。それは中国に対する親近感を持たず、無関心な人が増えるといった現状に著者の発した警告であり、かつて両国の間に存在した友好の空気を知らない人、あるいは経験しながら忘れてしまった人たちに、覚醒を促す呼び声である。ただ著者はそれを大声で説くのではなく、奥付に託すという暗示的な形でしか示さなかった。
評者は思う。友好であれ、親近感であれ、スローガンや標語で訴えれば実現するような単純なものではあるまい。最も基本的には、相手の国の庶民の暮らしとその中で営まれている「内なる生」への理解、その上での彼らと個としての交流、それを通じて生まれる個と個の信頼の基礎の上に築かれるものではないだろうか。
本書の内容は日中関係の昂揚の時代に書かれ、その凋落の空気の中で出版された。この間、両国庶民の往来は増えた。それなのに、相手を理解し、個として深く交流する機会は必ずしも増えたとは言えない。45年前の知見と侮ってはいけない。本書には日中関係の困難な時代、中国庶民の「内なる生」を理解するための多くの知恵が含まれているのである。
(いわさ・まさあき 九州大学名誉教授)
掲載記事の無断転載をお断りいたします。
