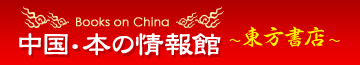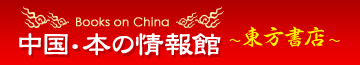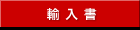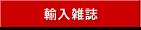| |
|
| 中国映画のコラム 第7回 . |
「台湾映画祭 in 高田世界館」レポート
|
| |
|
| |
|
|
 高田世界館として初となる映画祭を4月下旬、1週間ほどの期間で開催した。 高田世界館として初となる映画祭を4月下旬、1週間ほどの期間で開催した。
「台湾映画祭 in 高田世界館」。新潟県上越市というさほど大きくもない一地方都市。このような街で、台湾という冠を掲げて“映画祭”(特集上映ではない)を行うというのは全国でもほとんど例がないという。
実際、「一体なぜ台湾を」という声はあちらこちらから聞かれた。私自身、侯孝賢や楊徳昌をはじめとする台湾映画を好んで観ていたということもあり、なぜそのような問いが出てくるのかが当初は不思議に思えたものだが(だって台湾映画を観たいじゃないか!)、台湾や台湾映画にそこまで思い入れもなければ当然と言えば当然の問いでもあろう。
|
| |
|
|
一応、もっともらしい由縁もあった。台湾(中華民国)の初代総統である蔣介石が、高田世界館が立地する上越市高田地区にあった陸軍第13師団(現・陸上自衛隊髙田駐屯地)に研修生として留学していたのである。駐屯地の中には蔣介石が在籍していたことを紹介するコーナーがあり、そのようなこともあって昨年のお花見の時期(高田が最も観光客で賑やかになる季節である)には台湾からTVクルーも取材に訪れていた。
今回の映画祭には「蔣介石の高田留学時代」と題した記念講演を催し、講師として台湾社会や台湾映画に造詣の深い、ジャーナリストの野嶋剛氏が高田に訪れた。これが言うなれば映画祭開催の大本のアイディアであり、また映画祭を象徴するイベントであったわけである(少なくとも目論見の上では)。
|
|
 さて、ここで高田世界館のことに触れておきたい。当館は明治44年(1911年)設立、今年で104年目を迎える映画館で、日本最古の映画館のひとつとして数えられている。もともと芝居小屋として建築されたこの劇場は2階桟敷席があり、板組みの天井に設けられた装飾が目を引く(同時代における劇場建築においても同様の特徴が見受けられる)。西洋文明が日本に入り込んできた明治期に建てられたということもあり、洋風をモチーフとした意匠が他の劇場との違いを生み出している(とは言え真正の洋風建築ではなく、それを真似た「擬洋風建築」という建築様式であるらしい。屋根にも瓦が葺かれているので、奇妙といえば奇妙である)。 さて、ここで高田世界館のことに触れておきたい。当館は明治44年(1911年)設立、今年で104年目を迎える映画館で、日本最古の映画館のひとつとして数えられている。もともと芝居小屋として建築されたこの劇場は2階桟敷席があり、板組みの天井に設けられた装飾が目を引く(同時代における劇場建築においても同様の特徴が見受けられる)。西洋文明が日本に入り込んできた明治期に建てられたということもあり、洋風をモチーフとした意匠が他の劇場との違いを生み出している(とは言え真正の洋風建築ではなく、それを真似た「擬洋風建築」という建築様式であるらしい。屋根にも瓦が葺かれているので、奇妙といえば奇妙である)。
高田の街にはその他にも洋風建築が建てられ(ほぼ現存せず)、それをこのさほど大きくもない街で経済的・文化的に可能にしていたのが陸軍誘致の結果によるものであった。蔣介石、そして日本スキー発祥の父・レルヒ少佐といった外国人が出入りしていたのも同様の理由によるが、それを象徴しているのが彼らが当地に在住していた時期(1910~11年頃)と高田世界館が設立した年がほぼ同じだということである。だからこの映画祭と記念講演はそうした時代を遥かに見据える機会でもあったということだ。
|
|
 ただ、そうした時代やテーマと今回の映画祭における現代台湾映画を中心としたラインナップには大きな隔たりがあったのは否めない。例えば、日本と台湾との間の歴史を浮き彫りにしたドキュメンタリー『台湾人生』(こちらは日本人の監督が撮った日本映画である)では蔣介石をトップとする国民党政権が行った白色テロを出演者が批判しているなど、作品の内容のレベルにおいてもイベントとして厳密にはひとくくりにできないはずであった。 ただ、そうした時代やテーマと今回の映画祭における現代台湾映画を中心としたラインナップには大きな隔たりがあったのは否めない。例えば、日本と台湾との間の歴史を浮き彫りにしたドキュメンタリー『台湾人生』(こちらは日本人の監督が撮った日本映画である)では蔣介石をトップとする国民党政権が行った白色テロを出演者が批判しているなど、作品の内容のレベルにおいてもイベントとして厳密にはひとくくりにできないはずであった。
今回の映画祭の試みは、台湾が抱える問題を一般市民にどう身近なものとして(もっと言えば自らの問題として)とらえてもらえるかということでもあった。台湾をいまだに「タイ」との区別がつかない(これは決してこの拙い文章を面白くするためのジョークではない)市民が見受けられる地においては、日本が戦前・戦中と台湾を占領していた歴史すらも知らない恐れがある。戦後70年を迎えるこの年にあって、いま一度過去の出来事を振り返り、現在の日本がよって立つ位置を見定める必要があると考えた。その意味で先に挙げた『台湾人生』(酒井充子/2009)と、日本統治時代の台湾野球チームが甲子園で快進撃を遂げるスポーツドラマ『KANO 1931 海の向こうの甲子園』(馬志翔/2014)をそうした議論へのとっかかりとして上映することは意義深いものであると思い、本映画祭の目玉として取り上げることとなった。
上映作品はこの他に『祝宴!シェフ』(陳玉勳/2013)、『天空からの招待状』(齊柏林/2013)、『光にふれる』(張栄吉/2012)、『orzボーイズ』(楊雅喆/2008)をセレクトした。いずれも近年台湾および日本国内で話題になった作品であり、かつてその芸術性によって世界を驚嘆させた作品群、つまり台湾ニューウェーブおよびそれに連なる作品群からの選定はなかった。日本各地の映画館でも上映されたものも多く含まれており、いわゆる映画ファンからは不満があるラインナップであったかもしれない。
|
|
 しかしながら、「最新の台湾映画が描き出すもの」と題して講演を行った野嶋剛氏が指摘していたように(野嶋氏は先述の蔣介石に関する講演含め映画祭期間中に2度講演を行った)、ここ10年の台湾映画は「ルネッサンス」と呼ばれるほどの活況を呈しており、見方によっては今回のラインナップはそのバラエティの豊かさを体感できるようなものであったとも言える(ちなみに野嶋氏からは非常にいい選定だと評していただいた)。 しかしながら、「最新の台湾映画が描き出すもの」と題して講演を行った野嶋剛氏が指摘していたように(野嶋氏は先述の蔣介石に関する講演含め映画祭期間中に2度講演を行った)、ここ10年の台湾映画は「ルネッサンス」と呼ばれるほどの活況を呈しており、見方によっては今回のラインナップはそのバラエティの豊かさを体感できるようなものであったとも言える(ちなみに野嶋氏からは非常にいい選定だと評していただいた)。
正直、数ある作品から上映作を選び、それをお客に見せる側の人間にとっては近年の台湾映画の好調はありがたかった。台湾の一般の観客からそっぽを向かれたがゆえに台湾映画の凋落は始まったわけだが(それは具体的に年間の製作本数に如実に表れた)、もし台湾映画が以前のような作品しか供給していなかったとしたら、このような小さな街で台湾映画祭を開催するのは不可能であっただろう。
今回の映画祭期間中において、何度も「この映画は本当に素晴らしかった」といったような言葉を来場者からかけていただいた。それも一つの作品に限らず、である。それこそが現在の台湾映画の底力を示すものだと考えて良いだろう。今後も台湾から良質なドラマが日本に紹介されるようであれば、今回のようなイベントを継続していくことは(作品選定の上では)難しくないはずだ。
しかしながら今回の映画祭を通じて、観客の方で台湾映画への理解が深まったかどうかは判断しづらい。例えば『光にふれる』は観客からの反応はすこぶる良く、会場を後にする人々の目に涙が浮かんでいるのを何度も見かけたわけだが、感動からもう一歩進んだ「何か」が足りないような気もしている。当作はよくできたドラマだと思うし、端的に作品を楽しんでもらえればそれでいいのかもしれないが、果たしてそこに台湾映画らしさがあったのだろうか、などと考えもする。もちろん映画に国籍があるわけではないし、海外の映画作品をエキゾチズムのなかで序列化するわけではないのだが……。
映画祭を打ち上げ花火のような単発のイベントとしてではなく、長期的な展望の中で考えたいと思う。これをきっかけとして台湾との文化交流が進めばいいと思うし、観客がそれぞれの中で台湾や台湾映画に関してアンテナを張るようになってくれれば映画祭として大成功だと思う。現実的なレベルで言えば、次に台湾映画を上映するときもお客さんになってもらいたいのである。
|
|
総じて、変な気負いもなくスンナリと良質のドラマが続々と出てくる台湾映画の状況は歓迎すべきだとは思うし、今回の映画祭で観客にいい印象を持ってもらったことで、次にもつなげやすくなった。もしこれが蔡明亮のような延々と長回し撮影が続くような作品を上映していたとしたら、次は来なくなってしまうかもしれなかっただろう(しかしながらそれはそれでまた別の観客を獲得することになると思うので、それは次回開催への検討材料となるだろう)。
 映画祭としては予想以上の反響があり、観客動員数も悪くなかった。日本三大夜桜と称される高田の観桜会とGWに前後を挟まれ、開催までは一体どうなることかとずっと不安に思っていた(繰り返すが、今回が映画館として初めての映画祭なのである)。「映画祭」という名のついた単なる上映会になる可能性も大いにあったわけだが、形ばかりではなく(台湾政府要人を招いてのセレモニーも行った)、実体を伴ったイベントとして昇華することができた。それを可能にしていたのはやはり地域在住の台湾人たちの協力によるものであった(彼らを巻き込んでの『台湾人生』のトークセッションは大いに盛り上がり、この映画祭の一大ハイライトとなった)。彼らにはこの場を借りてお礼を言いたいと思う。 映画祭としては予想以上の反響があり、観客動員数も悪くなかった。日本三大夜桜と称される高田の観桜会とGWに前後を挟まれ、開催までは一体どうなることかとずっと不安に思っていた(繰り返すが、今回が映画館として初めての映画祭なのである)。「映画祭」という名のついた単なる上映会になる可能性も大いにあったわけだが、形ばかりではなく(台湾政府要人を招いてのセレモニーも行った)、実体を伴ったイベントとして昇華することができた。それを可能にしていたのはやはり地域在住の台湾人たちの協力によるものであった(彼らを巻き込んでの『台湾人生』のトークセッションは大いに盛り上がり、この映画祭の一大ハイライトとなった)。彼らにはこの場を借りてお礼を言いたいと思う。
今後は小規模な台湾映画特集を続けながら、映画館として引き続き台湾の情報を発信し続けたいと思う。近々には『セデック・バレ』(魏徳聖/2011)の上映も控えている。言わずもがな、『KANO』のスタッフたちが送る一大歴史絵巻である。既に日本国内でのロードショーを終えDVDも出ているにも関わらず、強気に2週間上映する。こちらの意図を汲んで、台湾映画祭のつながりを辿って来てもらえるか、ここが勝負である。
(うえの・みちなり 高田世界館支配人)
|
| |
|
| |
| |
|
| |
 |
| |